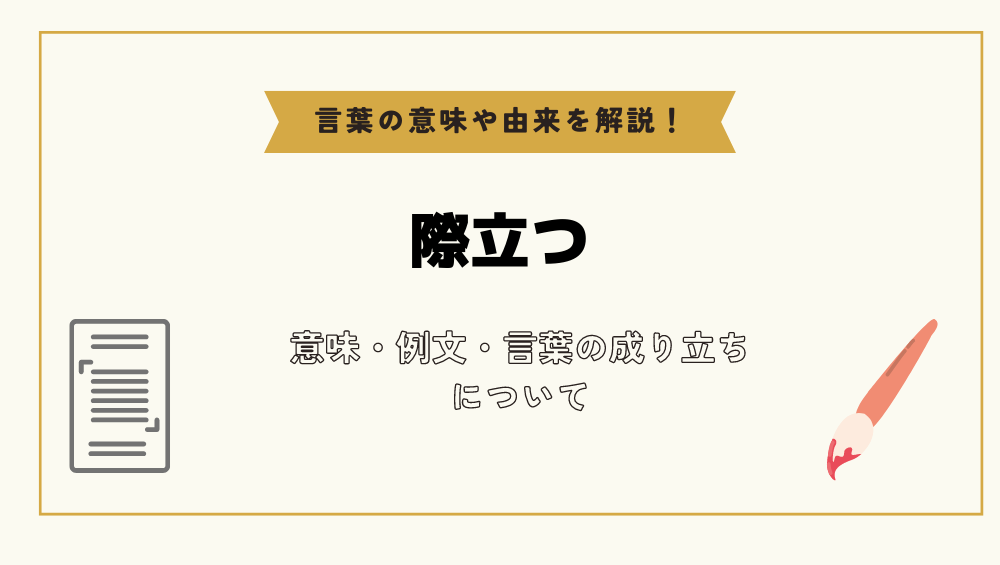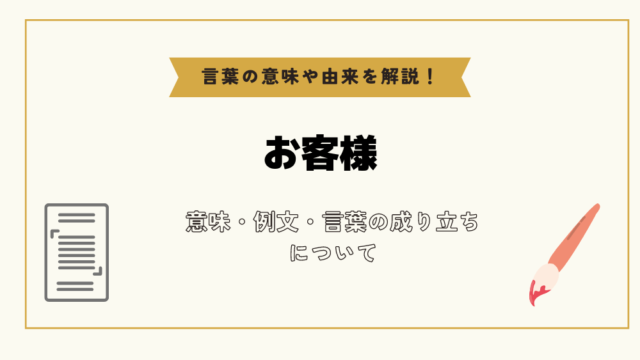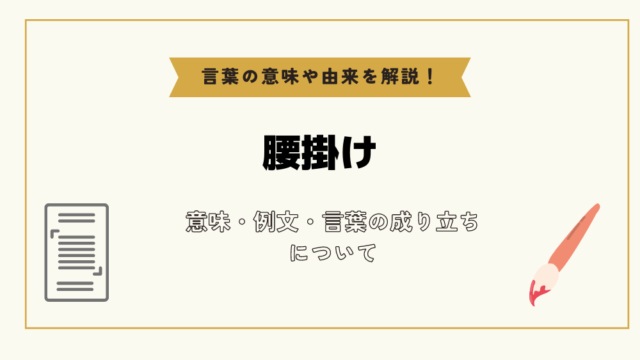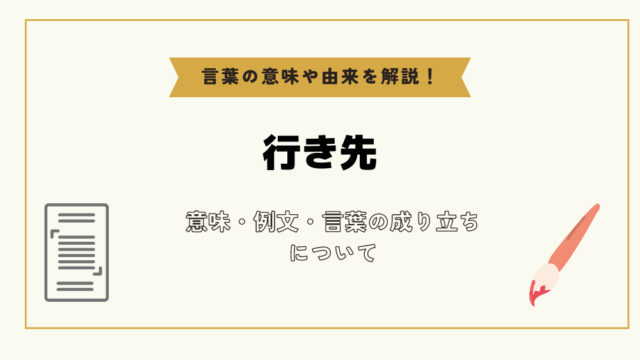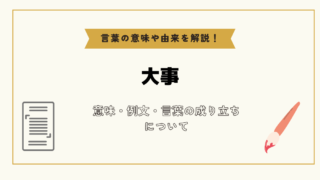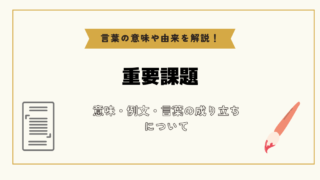「際立つ」という言葉の意味を解説!
「際立つ」とは、周囲と比較したときに特徴や存在感が明確に表れ、ひときわ目を引く状態を指す言葉です。特定の対象が他のものよりも鮮明に浮かび上がる様子を示し、物理的・視覚的な差異だけでなく、性格や能力など抽象的な面でも用いられます。たとえば色彩のコントラストが強いデザインや、突出した業績を挙げた人物の行動などが「際立つ」例です。
この語は評価語としてポジティブに使われることが多いものの、「場違いで浮いている」というニュアンスでネガティブに捉えられる場合もあります。そのため文脈や意図を踏まえた使い分けが求められます。
「目立つ」との違いは、単に視認されるか否かではなく、“比較して優位性が浮き彫りになる”点にフォーカスすることです。このニュアンスを理解することで、言葉選びに深みが生まれます。
「際立つ」の読み方はなんと読む?
「際立つ」は「きわだつ」と読みます。「さいだつ」と読んでしまう誤用が見られますが、国語辞典や文科省告示の「常用漢字表」においても「きわだつ」が正しい読みです。
「際(きわ)」は境目や端を意味し、「立つ」は状態が現れることを示します。この組み合わせから「境目が立つ=境界がはっきりする」というイメージが生まれ、現在の意味に発展しました。
漢字をひらがなで「きわだつ」と表記しても問題ありませんが、公的な文書や報告書では漢字を用いるほうが一般的です。口語では軽快さを重視して「きわだつ」とひらがなを選ぶ場面もあります。
読み方の誤りは信頼性を損なうため、ビジネス文書では必ず確認することが大切です。
「際立つ」という言葉の使い方や例文を解説!
「際立つ」は形容詞ではなく動詞なので、連体修飾では「際立った~」の形が一般的です。名詞を直接修飾する場合は過去形「際立った」を用いて違和感のない表現になります。現在進行形で状況を述べる際は「際立っている」を使うと自然です。
評価・比較・分析の文脈で頻出し、“定量的データを示した後で結論を強調する”役割を担います。新聞や学術論文でも「リスクが際立つ」「成果が際立った」といったフレーズが用いられています。
【例文1】コスト削減効果が際立ったチームの戦略を全社で共有する。
【例文2】赤いアクセントが室内の白い壁に際立っている。
日常会話では「その服、色が際立ってておしゃれだね」のように褒め言葉として使えば、具体性を持った評価が伝わります。ビジネスでは「他社と比較したとき当社の強みが際立つ」というように差別化を示す表現として活用できます。
文末を「~が際立つ」「~が際立っている」でまとめると、結論を読者に印象づけられます。
「際立つ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「際」は古くから和語として存在し、「端・境目」を意味する言葉でした。平安時代の『源氏物語』にも「きは」の形で登場し、階級差や色彩の境界を暗示する表現として使われています。これに動詞「立つ」が結びついた形が「きはだつ」で、室町期の古文書に例が確認できます。
語源的には“境界がハッキリと立ち上がる”という空間的イメージが核となっており、そこから比喩的に“特徴が浮き上がる”意味へ転じました。鎌倉・室町期の武家社会では、家格の差異を表す文脈で「際立つ」が用いられ、社会的優劣が視覚的に区分されていたことがわかります。
江戸時代以降は文学作品や落語にも登場し、「際立った美貌」「際立つ筆致」など芸術的評価へと広がりました。明治期には新聞言論で多用され、優位性や特徴の強調語として定着しました。
この歴史的変遷を踏まえると、「際立つ」は空間表現から心理・評価表現へと領域を拡大してきた語だと理解できます。
「際立つ」という言葉の歴史
古語辞典によると「きはだつ」は中世日本で頻出した語ではなく、むしろ公家や武家の公式記録などフォーマルな文体で散見される程度でした。近世に入ると人々の識字率向上とともに、江戸の町人文化で芸術や商品を評価・宣伝する場面で使われるようになります。
明治維新以降、西洋文化との比較を意識した啓蒙思想の広まりによって、「際立つ」は国際競争力や国家意識を語るキーワードになりました。「日本人の勤勉さが際立つ」といった近代文献はその証左です。
戦後の高度経済成長期には、商品性能の差別化を語る広告用語として「際立つ」が定着し、現代に至るまでビジネス語彙として不可欠な存在になりました。IT化が進んだ21世紀には、データ分析やアルゴリズムの文脈で「数値が際立つ」「傾向が際立つ」といった用例が急増しています。
このように「際立つ」は時代ごとに焦点を当てる対象を変えながらも、「比較し、差を浮き彫りにする」という核心を保ち続けてきました。
「際立つ」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「突出する」「際立っている」「群を抜く」「目を引く」「ひときわ映える」などがあります。これらは全て“他と比較して優れている・注目される”という共通点を持ちつつ、強調の度合いやフォーマル度に違いがあります。
「突出する」は統計やデータで長所が明確に数値化される場面に適しています。「群を抜く」は競争関係がある中で頭一つ抜けている状況を表します。「ひときわ映える」は主に視覚的な印象で使われ、爽やかで柔らかい表現になります。
文章のトーンや対象読者に合わせて類語を選ぶことで、同じ内容でも説得力や親しみやすさが変わります。レポートで硬めにまとめたい場合は「際立っている」、広告コピーで華やかに強調したい場合は「ひときわ映える」などの使い分けが有効です。
「際立つ」の対義語・反対語
「際立つ」と反対の意味をなす語として「埋没する」「目立たない」「平凡だ」「均一化する」などが挙げられます。
中でも「埋没する」は“周囲に紛れて存在感を失う”という意味で、ニュアンスが最も明確な対義表現です。ビジネス戦略で競合との差別化が図れない場合、「ブランドが市場で埋没している」という比喩がしばしば用いられます。
「平凡だ」「無難だ」はネガティブ度合いがやや低く、感情的表現を避けたい場面に適しています。「均一化する」は社会学や経済学で用いられる専門的表現で、個性や差異が吸収・消失する過程を指します。
反対語を理解しておくと、文章にコントラストを付けて論旨を鮮明に示すことができます。
「際立つ」と関連する言葉・専門用語
デザイン分野では「コントラスト比」という指標が「際立つ」度合いを定量化します。数値が大きいほど色や明暗の差が強く、可読性が向上するとされます。
マーケティングでは「USP(Unique Selling Proposition)」が近しい概念です。競合製品と比較して一際優れている訴求点を見抜き、顧客に提示するという考え方で、「ブランドのUSPが際立つ」という表現が用いられます。
統計学の「外れ値(アウトライヤー)」も、データ群の中で際立った数値として注目されるポイントです。外れ値は分析の際に除外すべきか注目すべきか判断が求められ、まさに「際立つ」の概念そのものと言えます。
このように、分野ごとの専門用語と結びつけることで「際立つ」の応用範囲が広がり、説明に深みが加わります。
「際立つ」を日常生活で活用する方法
日常会話で「際立つ」をうまく使うと、自分の観察力や語彙力をアピールできます。たとえば料理を褒めるときに「スパイスの香りが際立っているね」と言えば、味覚の具体的なポイントを指摘するため説得力が高まります。
ファッションでは「全体がモノトーンなので差し色のスカーフが際立っている」と言うだけで、相手のセンスを丁寧に評価できます。ただ「おしゃれだ」と言うよりも具体性があり、コミュニケーションが円滑になります。
自己プレゼンの場面でも、成果やスキルを「際立たせる」ためにグラフや実績数値を用意すると効果的です。面接で「リーダーシップが際立っていると言われます」と自己分析を述べると、差別化のポイントとして強調できます。
ポイントは“比較対象を明示”することと“具体的な事実や数値”を添えることです。これにより「際立つ」が持つ優位性のニュアンスがしっかり伝わります。
「際立つ」という言葉についてまとめ
- 「際立つ」は周囲と比較して特長が鮮明に現れる状態を示す動詞。
- 正しい読み方は「きわだつ」で、漢字・ひらがな両方の表記が可能。
- 語源は「境目(きは)+立つ」で、中世から空間表現として用いられた。
- 現代ではビジネスや日常会話で差別化を強調する際に使用、誤読に注意。
「際立つ」は単なる「目立つ」とは異なり、比較対象を通じて優位性を浮かび上がらせる言葉です。読み方は「きわだつ」が正しく、場面に応じて漢字・ひらがなを使い分けると良いでしょう。
歴史的には境界を強調する空間的語義から始まり、社会的地位、芸術的評価、そして現代のマーケティングやデータ分析へと適用範囲を広げてきました。日常生活やビジネスで使う際は、具体的根拠を示しつつ“差”を可視化することで、言葉の力を最大限に発揮できます。