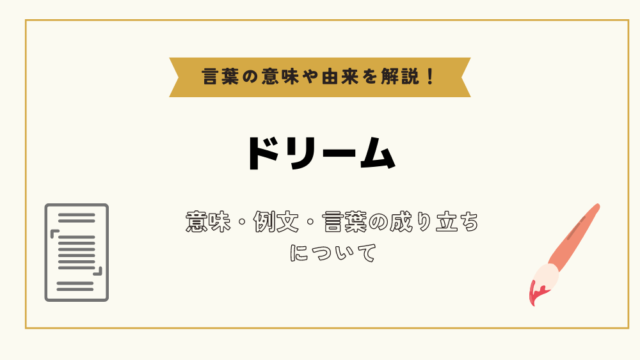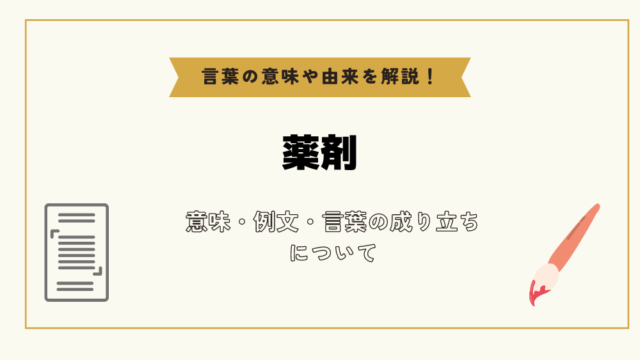Contents
「受難」という言葉の意味を解説!
「受難」という言葉は、困難や苦難に出会うことを意味します。
人生の中で辛い試練や不幸な出来事に直面することを表す言葉です。
例えば、健康上の問題や経済的な困難、人間関係の悩みなど、受難は人生において避けて通ることのできない要素といえるでしょう。
「受難」という言葉の読み方はなんと読む?
「受難」という言葉は、読み方は「じゅなん」となります。
漢字の「受」と「難」、それぞれが「じゅ」と「なん」と読まれます。
難しい状況や困難に直面する際に使われる言葉です。
「受難」という言葉の使い方や例文を解説!
「受難」という言葉は、試練や苦難に直面する場面で使用されます。
例えば、「彼は仕事で大きな受難を経験したが、それを乗り越え成長した」といった風に使われます。
また、「この映画は主人公の受難が描かれており、感動的なストーリーになっている」といったように、物語や文学作品の中でも受難がテーマとなることがあります。
「受難」という言葉の成り立ちや由来について解説
「受難」という言葉は、中国語の影響を受けた言葉です。
漢字の「受」と「難」が組み合わさっており、元々は仏教の用語として使用されました。
この言葉は、救済や解脱への道のりである「受苦(じゅく)」という概念に由来しています。
仏教では、過去生の行いによって現世の苦しみを受けるとされ、それを受け入れることで解脱を目指すとされています。
「受難」という言葉の歴史
「受難」という言葉は、仏教の概念を元にした言葉ですが、日本においては宗教の枠を超えて一般的に使われるようになりました。
特にキリスト教の「受難節」が有名であり、キリストの受難や死を記念して行われる40日間の期間が「受難節」と呼ばれます。
このように、「受難」という言葉は、宗教的な要素と共に歴史の中で広まってきました。
「受難」という言葉についてまとめ
「受難」という言葉は、困難や苦難に直面することを表す言葉です。
人生の中で辛い試練や不幸な出来事に出会うことは避けられませんが、それらを受け入れ、乗り越えることが成長や前進への一歩となるのです。
宗教的な要素も含まれる言葉であり、キリスト教の「受難節」などにも関連しています。