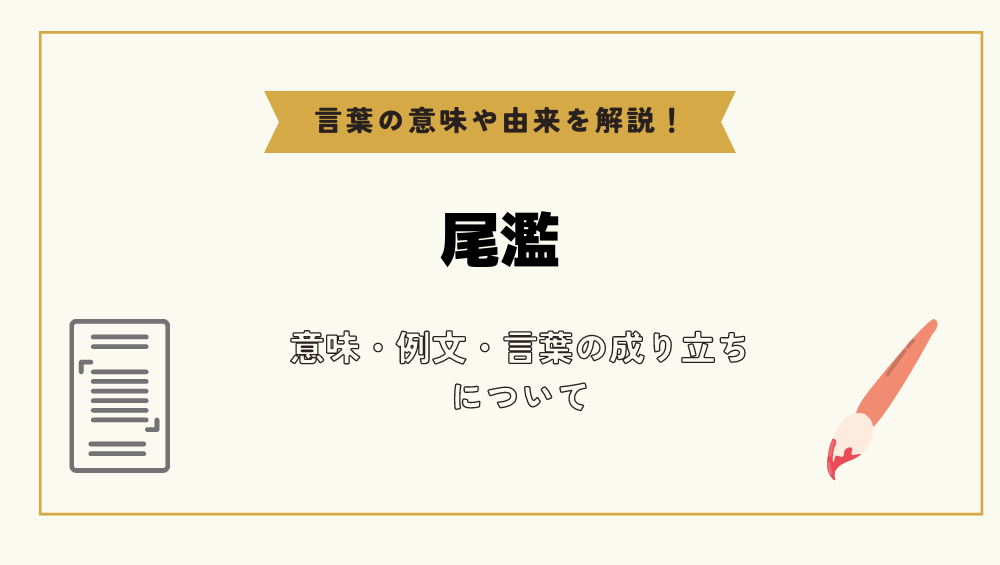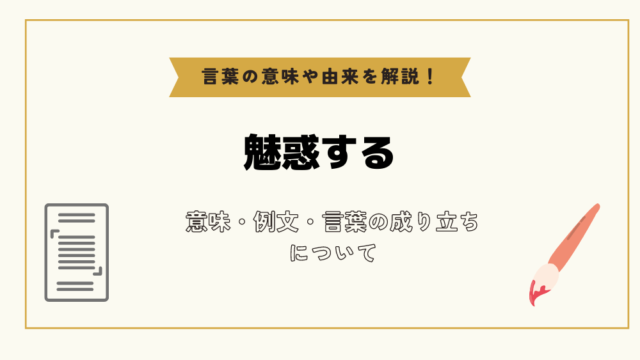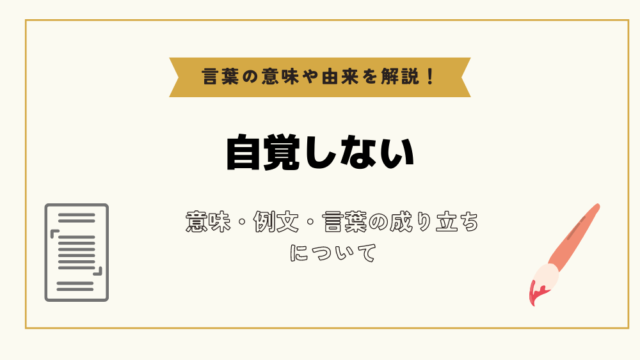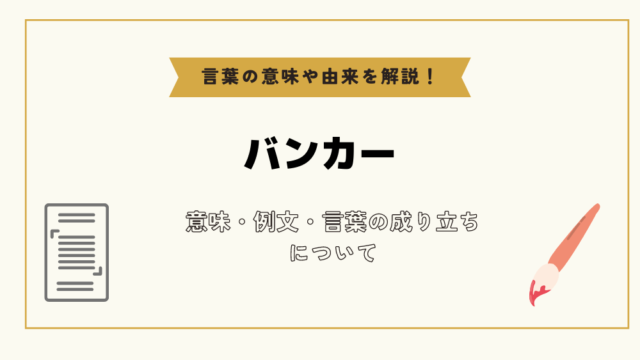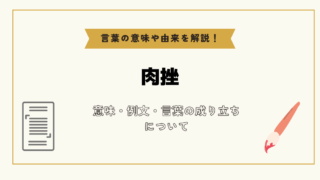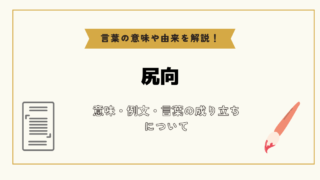Contents
「尾濫」という言葉の意味を解説!
「尾濫」とは、何かが限度を超えてあふれ出すことを指す言葉です。
例えば、大雨によって川が氾濫し、堤防を越えて周辺の土地へ水が広がることなどが尾濫の一例です。
物理的な現象以外にも、感情や情報が溢れ出る様子を表す場合もあります。
堪えかねた感情や一度に大量の情報の提供などが尾濫と言えるでしょう。
「尾濫」の読み方はなんと読む?
「尾濫」は、「びらん」と読みます。
この読み方が一般的であり、広く認知されています。
日本語には複数の読み方がある言葉も多いですが、尾濫に関しては「びらん」と覚えておけば間違いありません。
「尾濫」という言葉の使い方や例文を解説!
「尾濫」は、物事が限度を超えて広がる様子を表すため、日常会話や文学作品で使われることがあります。
例えば、「彼の語り口はいつも尾濫していて、一つの話をするだけでも時間がかかる」という風に言えます。
また、「情報の尾濫が起こると、本当の意味が伝わりにくくなる」というような例文も考えられます。
「尾濫」という言葉の成り立ちや由来について解説
「尾濫」という言葉の成り立ちを考えてみましょう。
一般的には、「尾(お)」は何かの終わりや末尾を意味し、「濫(あふ)れる」はあふれ出ることを表しています。
つまり、「尾濫」は、あふれることが終わりに達するという意味合いが込められています。
この言葉の由来や詳しい成り立ちは、今でも解明されていない部分もありますが、言葉の意味合いから見て、滑らかに流れ出て目に見えないところまで広がる様子をあらわしていると考えることができます。
「尾濫」という言葉の歴史
「尾濫」という言葉は、日本の古典文学や歴史書にも見られる古い言葉です。
昔の人々は川が氾濫する様子を「尾濫」と表現しており、堤防が決壊したり水が周辺の田畑に広がったりする様子を指していました。
こうした自然災害の一端として「尾濫」は捉えられ、歴史を通じて伝えられてきました。
「尾濫」という言葉についてまとめ
「尾濫」とは、何かが限度を超えてあふれ出すことを指す言葉です。
物理的な現象や感情、情報など、さまざまなものが尾濫することがあります。
読み方は「びらん」で、使い方は日常会話や文学作品などで見られます。
成り立ちや由来は謎があるものの、日本の古典文学や歴史書にも登場する古い言葉です。
尾濫は、過去から現在まで人々にとって身近な状況に関わる言葉となっています。