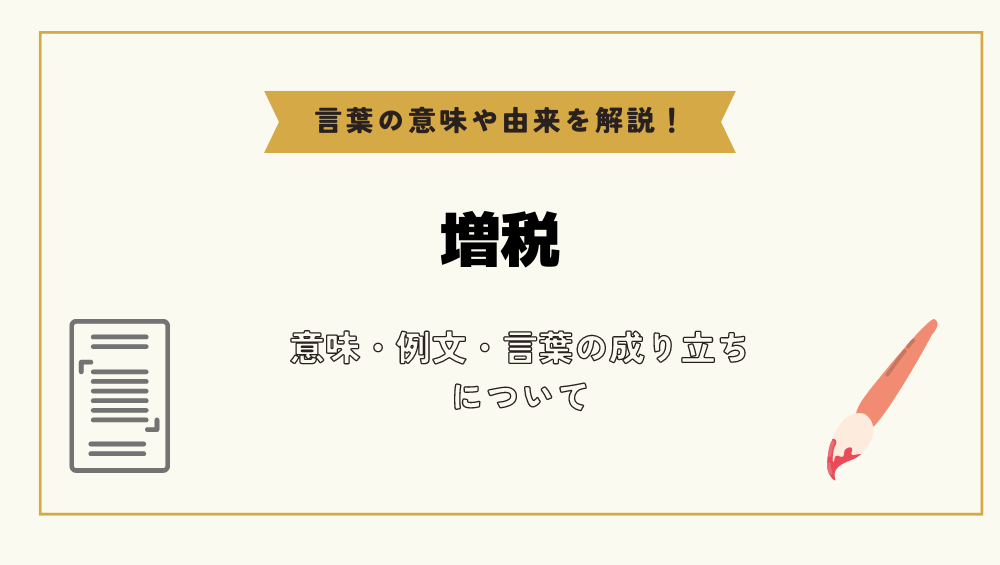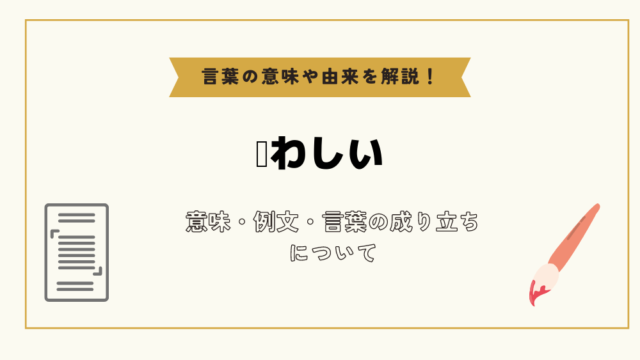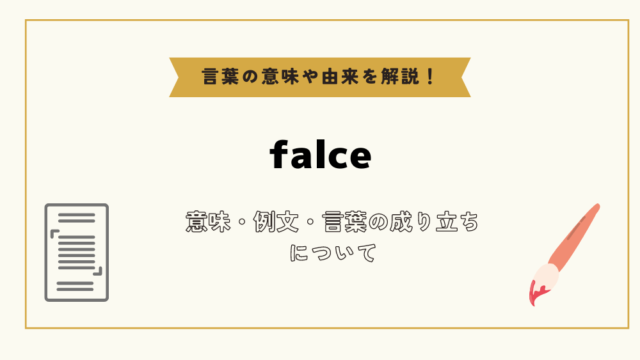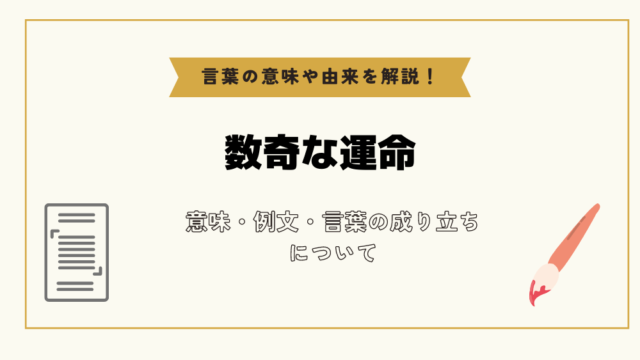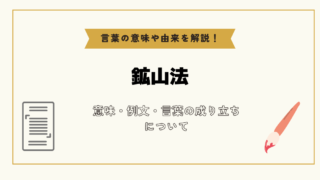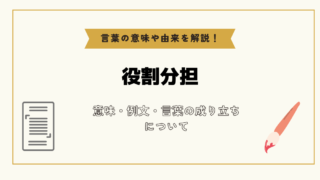Contents
増税とは何を意味するのか?
「増税」とは、国や地方自治体が税金を上げることを指します。
税金は、国や地方自治体が公共の事業や社会保障などへの財源として利用するために徴収されます。
増税は、国や地方自治体の収入を増やすために行われる手段であり、社会の経済状況や財政事情によって必要とされる場合があります。
「増税」はどうやって読むの?
「増税」は、「ぞうぜい」と読みます。
カタカナ表記では、「ゾウゼイ」となりますが、一般的には「ぞうぜい」と読まれることが多いです。
増税は、税金が増えることを意味する言葉であり、経済や社会の動向を考慮して、税制改革や財政調整の一環として行われます。
「増税」の使い方や例文を解説!
「増税」は、税金が上がることを指す言葉です。
政府が消費税を引き上げると発表した場合、それは「増税」と言います。
「来年から消費税が増税される予定です」というように使われることがあります。
また、地方自治体が市民税を増やす場合も「増税」と呼ばれます。
「市民税の増税を検討している」というニュースも聞かれます。
「増税」とはどのように成り立つ言葉なのか?
「増税」という言葉は、「増える(増)税金(税)」という意味で成り立っています。
「増税」は、税金が増えることを表し、国や地方自治体の予算や財政状況に合わせて行われます。
増税が行われれば、国や地方自治体の歳入が増えるため、公共のサービスや社会保障の充実につながることが期待されます。
「増税」という言葉の歴史
「増税」という言葉は、日本の歴史の中で度々使われてきました。
戦後の高度経済成長期には、経済の成長に伴い税務収入が増えることから、増税が行われることがありました。
また、近年では社会保障費の増加や財政赤字の解消のために、増税が議論されることが多くなってきました。
「増税」という言葉についてまとめ
「増税」とは、国や地方自治体が税金を上げることを指し、公共の事業や社会保障などの財源を確保する手段です。
日本の経済や財政事情に合わせて増税が行われることがあり、政府や地方自治体の予算や財政状況に大きな影響を与えます。
増税の是非や具体的な内容は政策や社会の議論の中で決まりますが、私たちの生活や社会の仕組みに密接に関わる重要な要素となっています。