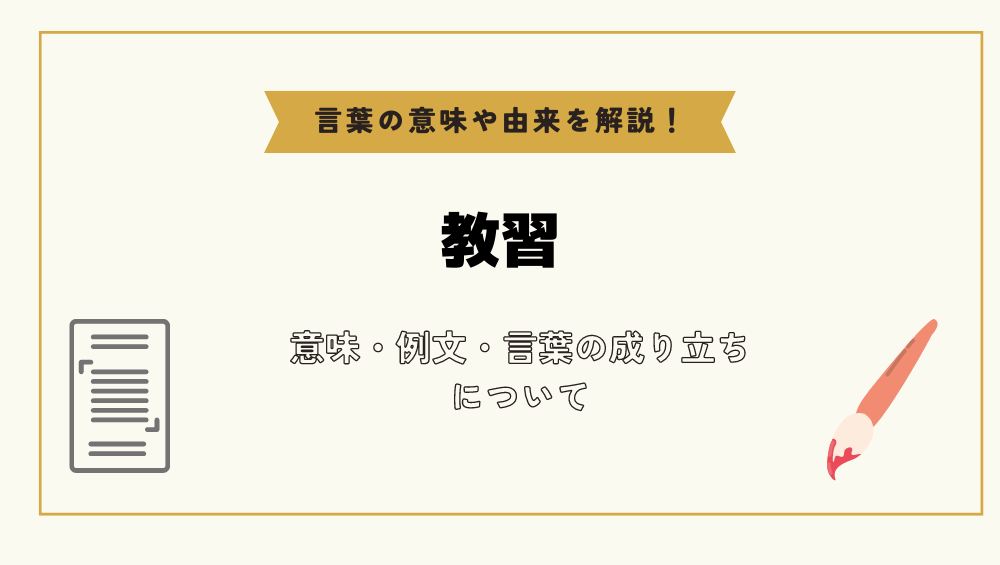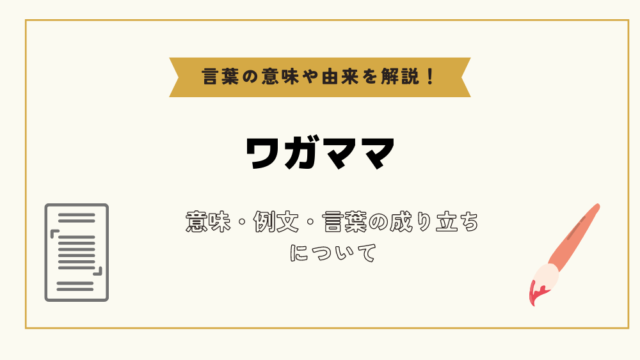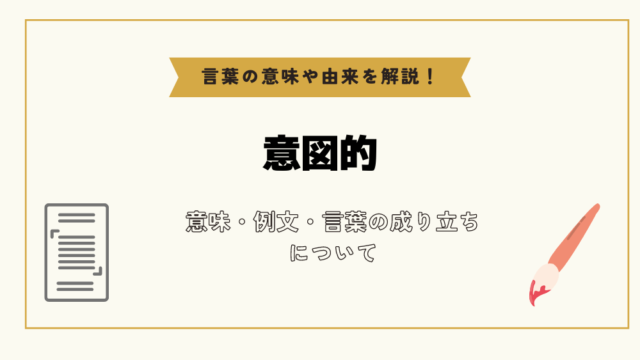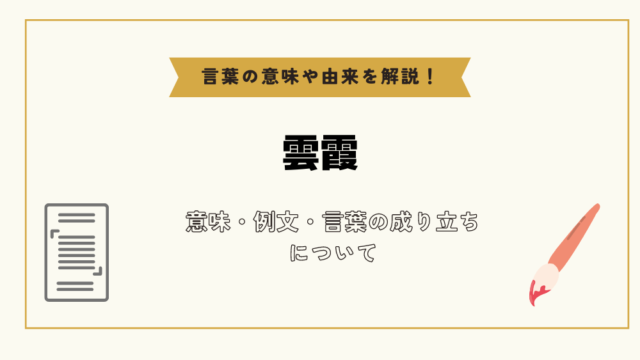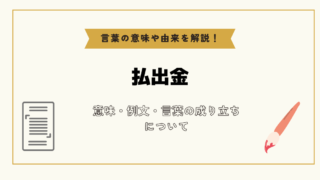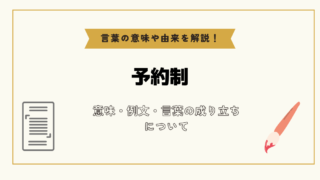Contents
「教習」という言葉の意味を解説!
「教習」とは、ある特定の分野や技術を学ぶために行われる講習や訓練のことを指します。
具体的には、運転免許や資格取得、スポーツ、書道、楽器など、さまざまな分野で行われる学習のことを指すことがあります。
教習を受けることによって、専門的な知識や技術を身につけることができます。
例えば、車の運転免許を取るための教習では、交通法規や実際の運転技術を学ぶことができます。
「教習」という言葉の読み方はなんと読む?
「教習」という言葉は、「きょうしゅう」と読みます。
日本語の読み方としては、一般的なものです。
覚えておくと、コミュニケーションでの使用時に役立ちます。
「教習」という言葉の使い方や例文を解説!
「教習」という言葉は、以下のような使い方があります。
。
例文をいくつか紹介します。
「先週、運転教習を受けてきました。
道路交通法や安全運転の基本を学び、実際に車を運転する練習もしました。
」
。
「教習」という言葉の成り立ちや由来について解説
「教習」という言葉は、「教える」と「習う」の二つの要素で構成されています。
「教える」とは、知識や技術を他人に伝えることを意味し、「習う」とは、他人から知識や技術を学ぶことを意味します。
この二つの語を組み合わせた言葉が「教習」となります。
「教習」という言葉の歴史
「教習」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や古代の教育制度にも見られます。
江戸時代には、武士や町人の子弟に対して、剣術や礼法などの教習が行われました。
現代では、社会の多様化や技術の進歩に伴い、より多くの分野で教習が行われるようになりました。
「教習」という言葉についてまとめ
「教習」とは、ある特定の分野や技術を学ぶための講習や訓練のことを指します。
日本語の読み方は「きょうしゅう」となります。
運転免許や書道、楽器など、さまざまな分野で行われる教習によって、専門的な知識や技術を身につけることができます。
また、「教習」という言葉は古くから存在し、江戸時代から教育制度で使用されてきました。