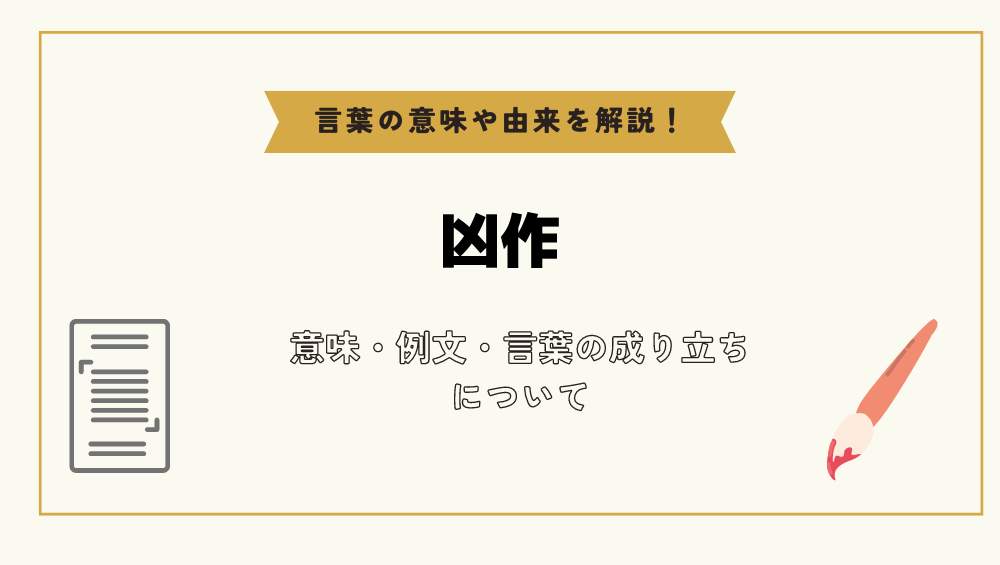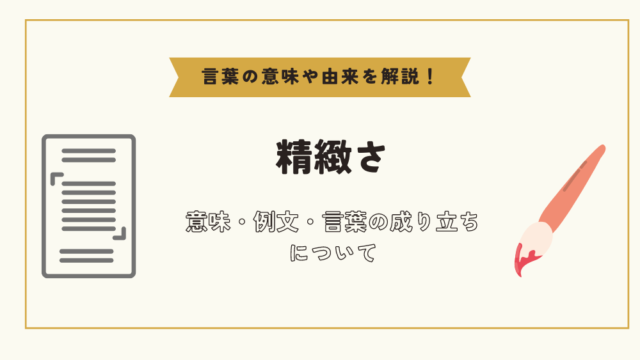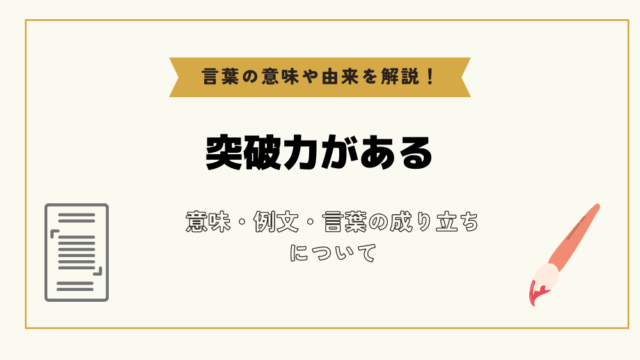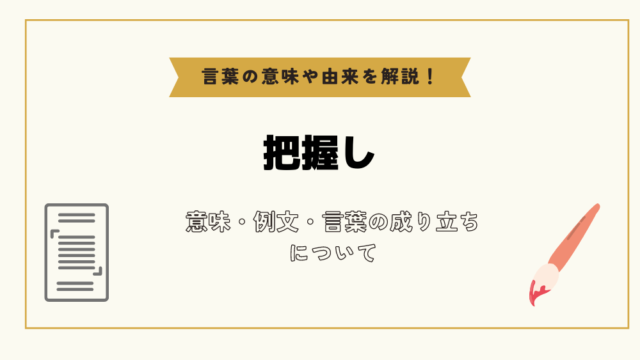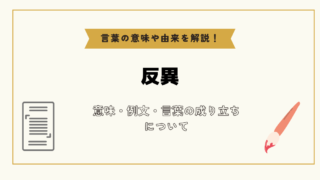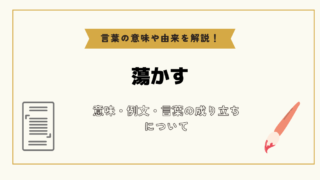Contents
「凶作」という言葉の意味を解説!
「凶作」とは、農作物の収穫が極端に悪い年や、不作のことを指します。
天候の悪さや害虫の大発生などが原因で、作物が思うように育たず、収穫量が極端に減少してしまう状態です。
農業にとっては大変厳しい状況であり、農家の生活にも深刻な影響を及ぼします。
収穫が少なくなると生計が立てにくくなり、食料の価格が上がることもあります。
凶作は農業にとっては避けられないことですが、農家の努力や技術によって最小限の被害にとどめることができる場合もあります。
「凶作」という言葉の読み方はなんと読む?
「凶作」という言葉は、「きょうさく」と読みます。
「凶」の部分は、「きょう」という読み方です。
「凶」という漢字は、不吉や災いを意味することが一般的です。
一方で、「作」は「さく」と読まれます。
この漢字は「作物を育てる」という意味があります。
「凶作」という言葉は、作物に何らかの不運な要素が加わり、育ちが悪くなる状況を表します。
「凶作」という言葉の使い方や例文を解説!
「凶作」という言葉の使い方は、農作物の収穫が悪い年や、不作の状況を表す際に使われます。
例えば、「今年は豪雨や台風の影響で、米の収穫が大きくダメージを受けました。
本当に凶作でした」というように使うことができます。
他にも「凶作が続いている地域では、農家の方々が大変困っています。
支援が必要です」といったように、凶作の被害を伝える際に使うこともあります。
「凶作」という言葉の成り立ちや由来について解説
「凶作」という言葉は、漢字の組み合わせによって成り立っています。
「凶」という漢字は、元々は猟師の間で「不吉なこと」「災い」という意味で使われていたものです。
一方で、「作」という漢字は、「作る」という意味があります。
農作物に対しては「作物を育てる」という意味合いも含まれます。
この二つの漢字を組み合わせることで、「凶い災いが作物の生育に悪影響を与える」という意味を持つ言葉として使われるようになりました。
「凶作」という言葉の歴史
「凶作」という言葉は、日本の農業の歴史とともに存在してきました。
農業は天候や自然条件に左右されるため、古くから「凶作」の被害に悩まされてきました。
縄文時代や弥生時代には、自然災害や気候変動による凶作が度々発生していたと考えられています。
その後も、戦乱や自然災害によって凶作が続き、人々の生活に大きな影響を与えました。
現代でも、地球温暖化による異常気象や自然災害が増加しているため、凶作のリスクは依然として残されています。
「凶作」という言葉についてまとめ
「凶作」とは、農作物の収穫が極端に悪い年や、不作のことを指します。
農業にとっては大変厳しい状況であり、農家の生活にも大きな影響を及ぼします。
収穫が少なくなると生計が立てにくくなり、食料の価格が上がることもあります。
「凶作」という言葉は、「きょうさく」と読みます。
「凶」は不吉や災いを意味し、「作」は作物を育てるという意味があります。
この言葉は古くから存在し、農業の歴史とともに利用されてきました。
現代でも凶作のリスクはあるため、農業への支援や対策の重要性が高まっています。