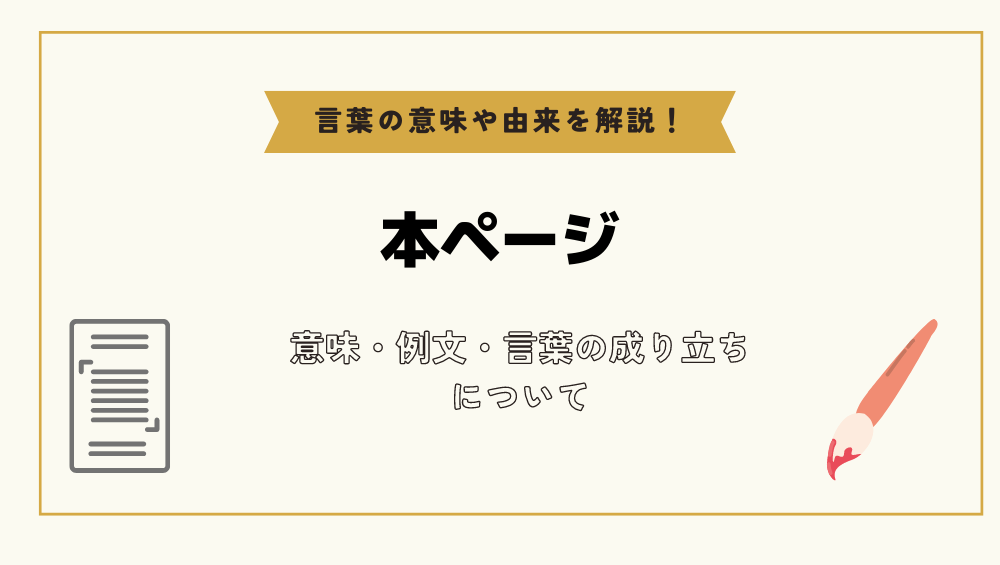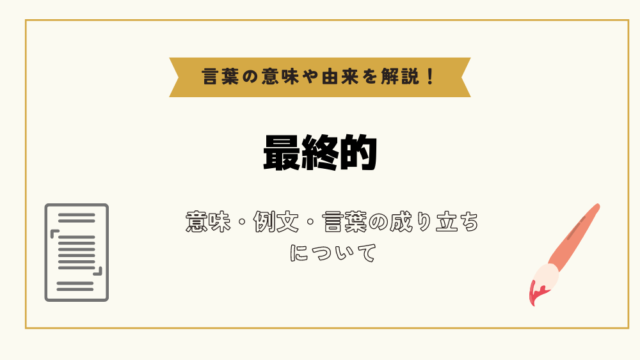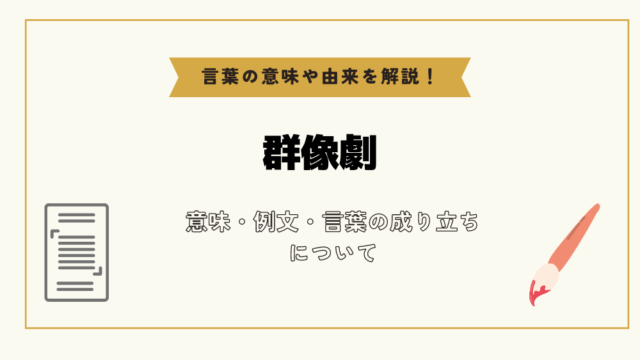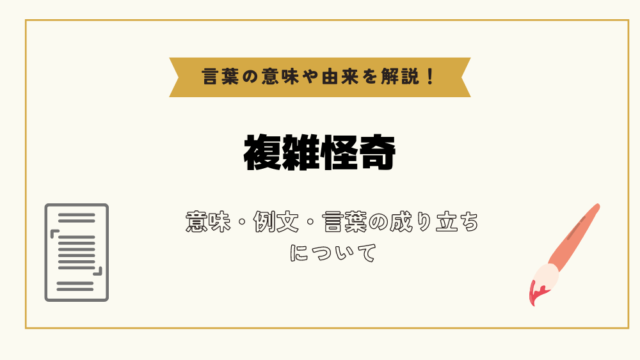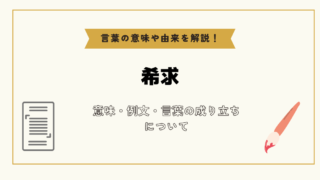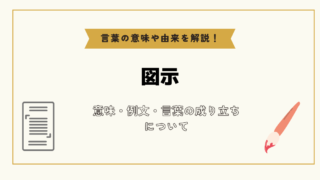「本ページ」という言葉の意味を解説!
「本ページ」とは、閲覧者が現在開いているウェブページそのものを指し示す表現です。日本語の中でもIT分野特有の語として定着しており、リンク先や別ページと区別するために用いられます。パンフレットや書籍でいう「本書」と同じく、対象を限定して読者に誤解を与えない効果があります。
多くの場合、「詳しくは本ページ下部をご覧ください」「本ページでは〇〇について解説します」のように補足説明や案内文中に使われます。指示対象がブラウザに表示されているページ1枚分に限定されるため、同サイト内でも他ページとの混同を防ぎやすいメリットがあります。
さらに「本」は「当」「現在の」と似たニュアンスを持つ一方、より丁寧でフォーマルな響きを与えます。公共機関や企業の公式サイトで多用されるのは、この丁寧さが求められる場面で有効だからです。
Webアクセシビリティの観点では、スクリーンリーダー利用者にとっても理解しやすい語句であり、ページ内ナビゲーションの指標として役立ちます。ただし国外ユーザーには通じにくい場合があるため、英文併記などの配慮が推奨されます。
「本ページ」を口頭で説明する際は「ほんぺーじ」と言い切るだけで主体が明確になります。特に社内会議やプレゼン資料で参照先を示すとき、紙資料の「本資料」と同等の扱いができるため便利です。
「本ページ」の読み方はなんと読む?
読み方は平仮名で「ほんぺーじ」、アクセントは「ほ↗んぺ↘ーじ」と頭高型で発音するのが一般的です。アクセントが平板型になる地域もありますが、ビジネスシーンでは頭高型が多く採用されています。
カタカナ表記「ホンページ」はほとんど用いられず、漢字+平仮名での表記が標準的です。これは「本」という漢語が持つフォーマルさと、「ページ」という外来語が結びついたハイブリッド表現だからです。
読み間違いとして「もとページ」と言うケースがありますが、「本」を「もと」と読むのは「本棚(もとだな)」など一部の古語的用法に限られます。ウェブ文脈では「ほん」と読むのが唯一の正解と覚えておくと安心です。
表示フォントによっては漢字と平仮名の境目が視認しにくい場合があります。そのためデザイン的に強調したい場面では太字やカラーリングを使い、「本ページ」という語が見落とされない工夫が必要です。
外国籍スタッフとの協働では「this page」と併記するケースが増えています。社内ガイドラインで読み方をルビや注釈として示しておくと、チーム全体の理解度が高まります。
「本ページ」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方の基本は「対象を限定し、読者に具体的な行動を促す」点にあります。ページ内に複数のリンクやフォームがある場合、「本ページ内のフォームからお申し込みください」のように行動を明示できます。
【例文1】本ページでは製品Aの最新機能を詳しく紹介しています。
【例文2】ご質問のある方は、本ページ下部の問い合わせボタンをご利用ください。
注意点として、「このページ」との混在は避けましょう。同一文書内で呼称が揺れると読者が混乱する可能性があります。一貫して「本ページ」で統一するか、「このページ」で統一するかを事前に決めてください。
また、スマートフォン表示では「本ページ上部へ戻る」ボタンを配置する際、「ページ最上部」と言い換えるとより直感的です。ターゲットユーザーのリテラシーに応じて細かな調整を行うと良いでしょう。
最後にメールマガジンやCMS(コンテンツ管理システム)のプレビューでも「本ページ」が自動差し込みタグで置換される場合があります。配信前に必ず実際の表示を確認し、誤リンクや誤情報を防止してください。
「本ページ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「本ページ」は、日本語の敬語表現「本(ほん)」と英語の「page」が融合して生まれた和製混合語です。「本」は「該当する」「当該の」という意味を持ち、文語的な公文書やビジネス文書で頻繁に用いられてきました。
一方「page」は明治期に印刷技術と共に外来語として導入され、出版業界で一般化しました。インターネット黎明期の1990年代後半、日本語ウェブサイトを整備する中で「page」をカタカナのまま取り入れ、「本ページ」という表現が自然発生的に使われ始めました。
この背景には、英語UIを翻訳する際に「this page」を直訳して「このページ」ではややカジュアルすぎる、という企業側の判断がありました。「当ページ」では硬すぎる、あるいは古めかしいとの意見もあり、「本ページ」がバランスの取れた選択肢として定着したと推測されます。
出版業界の「本書」や「本誌」と同様、人称を排除して対象を示せる点が、ウェブガイドラインとの親和性を高める結果になりました。
現代ではHTMLテンプレートやCMSの言語リソースにも組み込まれ、企業・自治体サイトで標準表現の一つとして扱われています。
「本ページ」という言葉の歴史
本格的な普及は2000年代初頭、行政機関や大手企業が公式サイトを整備し始めた頃から加速しました。当時はウェブアクセシビリティJIS規格の制定準備が進められ、用語の統一が課題となっていました。
2004年に「JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針)」が公開されると、多くのサイトがガイドラインを参考に表現を整理しました。「本ページ」は正式に規格に明記されたわけではありませんが、用語統一例として紹介資料に掲載されたことで信頼性が高まりました。
その後、スマートフォンの普及でページ遷移数が増えると、ユーザー案内の必要性も増加しました。パンくずリストやフッターリンクが整備される中、「本ページ」という呼称がコンパクトで扱いやすいことが再評価されました。
2020年代に入ると、ウェブアプリやPWA(Progressive Web Apps)でも「本ページをホーム画面に追加」のような文言が採用され、ネイティブアプリとのハイブリッド技術にも対応するようになりました。
今後も音声アシスタントやARグラスなど新しいインターフェースが登場しても、「本ページ」という言葉は画面単位の概念が残る限り、使用され続けると予測されます。
「本ページ」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な言い換えには「当ページ」「現在のページ」「このページ」があります。フォーマル度や読みやすさの観点で使い分けると、ユーザー体験を最適化できます。
「当ページ」は公文書や契約書で古くから用いられており、最も硬い表現です。敬語としては申し分ありませんが、一般ユーザーには馴染みが薄く距離感を生む恐れがあります。一方「このページ」は話し言葉に近く親しみやすい反面、企業サイトではカジュアルすぎると判断される場合があります。
「こちらのページ」は中間的な語感で、コールセンターFAQなど柔らかい案内に適しています。また英語のまま「this page」と併記すれば多言語対応ページで統一性を保つことができます。
選択基準は「サイト全体のトーン&マナー」と「想定読者のリテラシー」です。複数の表現が混在すると混乱を招くため、スタイルガイドでメインの呼称を定めるのが理想的です。
「本ページ」と関連する言葉・専門用語
関連用語を押さえることで、ページ構造やナビゲーション設計の理解が深まります。ここでは代表的な語を五つ紹介します。
1. セクション(section): ウェブページを論理的に区切る領域。HTML5では<section>タグを使用。
2. パンくずリスト: ユーザーが現在位置を把握するための階層リンク集。「本ページ」がその最下層を指す。
3. トップページ: ウェブサイトの入口。区別するため「本ページ」と併用される場合がある。
4. ランディングページ(LP): 広告や検索結果から最初に訪問するページ。リンク先として「本ページへ遷移」の文言が使われる。
5. モーダルウィンドウ: 画面上に重ねて表示される小窓。閉じると「本ページ」に戻るため、案内文で本語が登場しやすい。
これらを正しく理解すると、サイト内リンク設計やUI/UX改善に役立ちます。
「本ページ」を日常生活で活用する方法
仕事以外でも「本ページ」を使いこなすことで、オンライン情報共有がスムーズになります。たとえば家族や友人にブログ記事を紹介する際、「本ページの後半に写真を載せたよ」と伝えればリンクを貼り直す手間が省けます。
個人のSNS投稿でも「本ページ下部のコメント欄で意見を募集中」と書けば、読者は迷わず目的地へ到達します。小規模ながらもUXを意識した表現が、読者のストレス軽減につながります。
また、オンライン授業で資料を配布する教師が、学習管理システム(LMS)内の説明文に「本ページ内にある課題リンクから提出してください」と記載すると、学生は余計なナビゲーションをせずに済みます。
注意点は、印刷物やPDFに変換した場合、「本ページ」が指す対象が不明になることです。ダウンロード可能な資料には「本資料」など別表現を用いると誤解を防げます。
「本ページ」についてよくある誤解と正しい理解
最も多い誤解は「本ページ」と書けば自動的にリンクが張られるという思い込みです。実際には開発者がHTMLアンカーやJavaScriptで処理を追加しない限り、クリックできる要素にはなりません。
次に、スマートフォンアプリ内のWebView表示を「本ページ」と呼ぶのは厳密には誤用です。アプリ側から見れば「画面」や「ビュー」が正しく、ウェブサイトの「ページ」と混同しないよう区別が必要です。
また、「本ページ」を英訳する際、単に「Hon Page」と直訳するのは間違いです。正確には「this page」と訳すか、状況に応じて「this webpage」「this site page」と説明的に書くと誤解を防ぎます。
最後に、音声読み上げソフトが「ほんぺージ」と不自然に区切ることがあります。辞書登録やSSMLタグによる読み上げ調整を行うことで、ユーザー満足度を高められます。
「本ページ」という言葉についてまとめ
- 「本ページ」は現在表示しているウェブページを丁寧に示す日本語表現。
- 読み方は「ほんぺーじ」で、漢字+平仮名表記が一般的。
- 「本」と「page」の混合による和製語で、2000年代以降に急速に普及。
- 使い方は案内文で対象を限定する際が中心、表現揺れに注意すること。
「本ページ」という言葉は、ウェブサイトの発展とともに誕生した比較的新しい日本語表現です。フォーマルさと親しみやすさを兼ね備え、行政・企業・教育機関など幅広い場面で利用されています。
読み方の統一や類語との使い分けを意識することで、読者にとってわかりやすい情報提供が可能になります。これからもUI/UXの観点で適切に活用し、より良いオンラインコミュニケーションを目指しましょう。