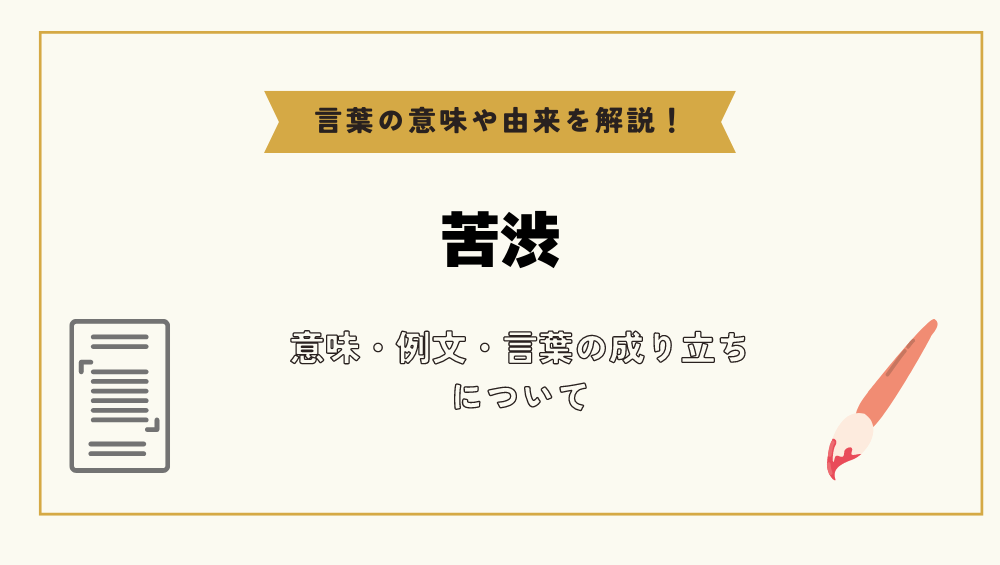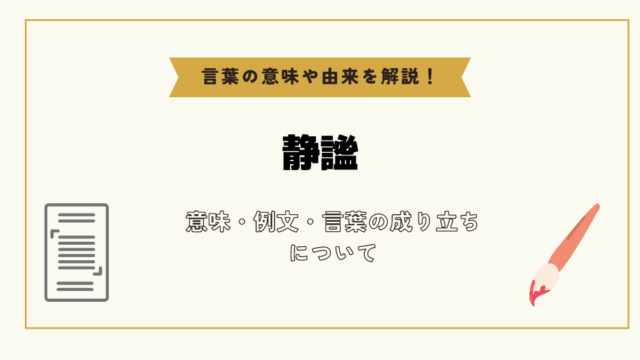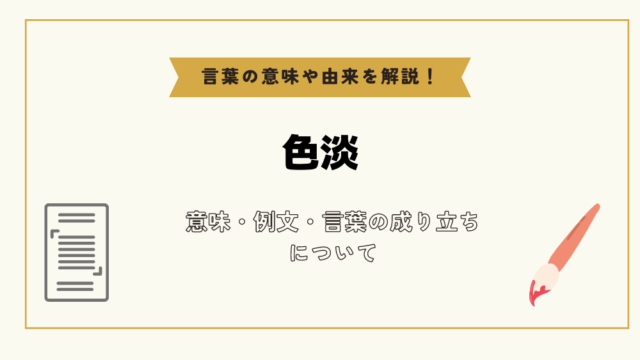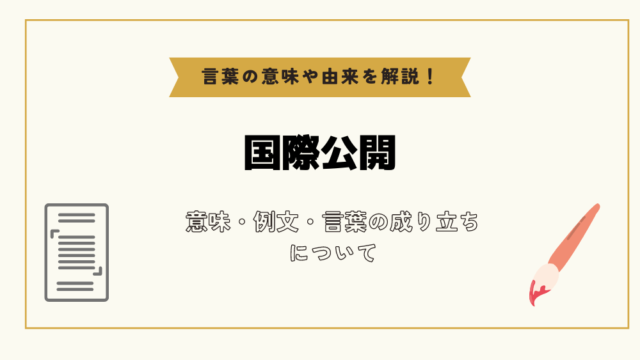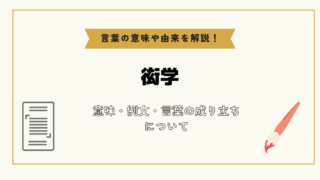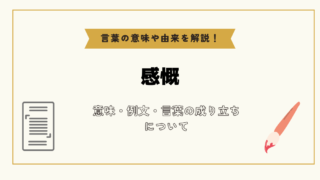Contents
「苦渋」という言葉の意味を解説!
「苦渋」とは、困難や葛藤を感じながらなされる苦しい決断や行動のことを指します。
何かを我慢し、心を痛めながら進む様子を表現する言葉です。
苦渋は悲しみと辛さが交錯する感情を表し、時には自己犠牲を伴うような状況に立たされることもあります。
勇気を持って決断することは大切ですが、その決断にはしばしば苦渋の思いが伴います。
「苦渋」という言葉の読み方はなんと読む?
「苦渋」という言葉は、「くじゅう」が正しい読み方です。
日本語によくある四声のルールに基づいて発音されます。
心情的な言葉であるため、正しい読み方を知って、表現力豊かに使用しましょう。
「苦渋」という言葉の使い方や例文を解説!
「苦渋」は主に文章や口語表現で使われます。
例えば、仕事の悩みを抱えた人が上司に相談しているときには、以下のような表現が考えられます。
「苦渋の決断ですが、私はこのプロジェクトの担当役割を変更したいと思っています。
」
。
このように、苦渋の形容詞として使われることが多いです。
他にも、困難な選択や追い詰められた状況を表す際にも使用されます。
「苦渋」という言葉の成り立ちや由来について解説
「苦渋」という言葉の成り立ちは、「苦い」と「渋い」の二つの言葉が組み合わさっています。
苦いということは辛いことを表し、渋いということは苦みや酸味を表しています。
苦渋という言葉は、この二つの意味を合わせ持つことで、厳しい状況やつらい選択を表現しています。
日本語特有の表現力が反映されている一つの言葉と言えるでしょう。
「苦渋」という言葉の歴史
「苦渋」という言葉の起源は古く、日本の文学作品や歴史書にも見られます。
古典的な用法では、人々が様々な困難や試練に遭遇した場合に使用されました。
時代が進み、現代の日本語においては、苦渋という言葉が広く一般的に使用されるようになりました。
文化や状況の変化に伴い、この言葉も時代の流れに合わせて変化してきたのです。
「苦渋」という言葉についてまとめ
苦渋は、困難や葛藤を感じながら行われる苦しい決断や行動を表す言葉です。
その読み方は「くじゅう」であり、文章や口語表現で頻繁に使われます。
この言葉は古くから使用されており、日本の歴史や文学作品に見られるものです。
その由来や意味には日本語特有の表現力が詰まっており、その使い方には文化や社会の変化が反映されています。
「苦渋」という言葉は、困難な状況や迫られた選択に直面した時に使われる表現です。
1つの言葉には多くの意味や背景が含まれているため、正しく使うことでより豊かな表現が可能になります。