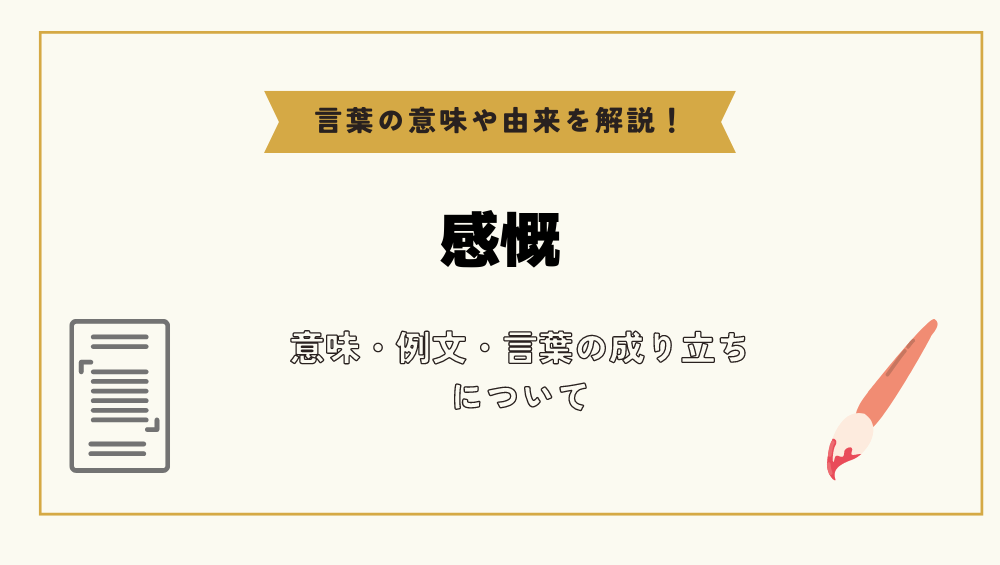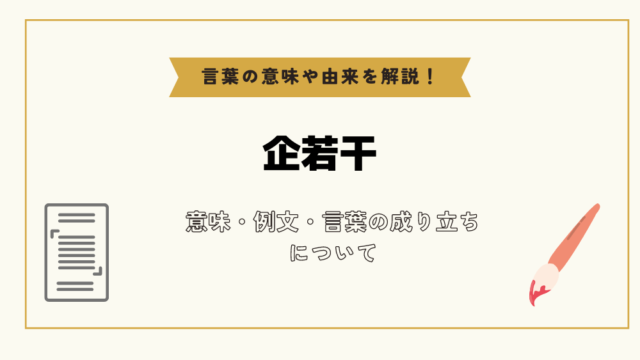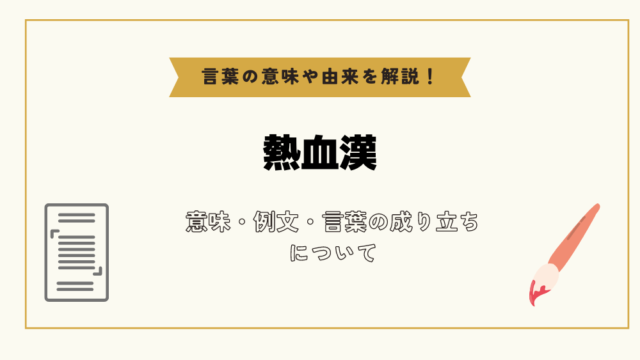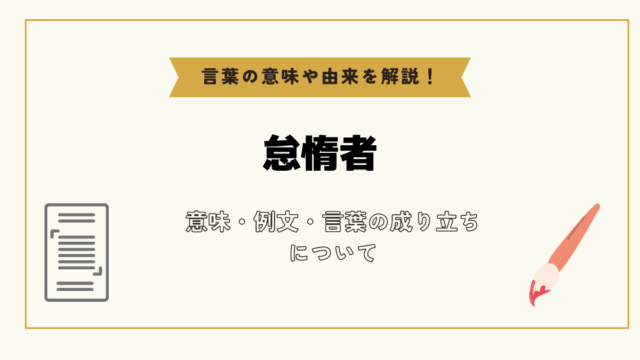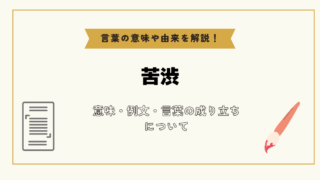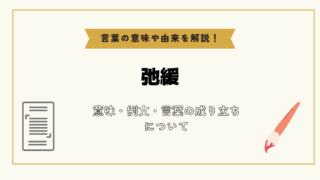Contents
「感慨」という言葉の意味を解説!
「感慨」とは、ある出来事や物事に対して深い感じ方や感じ入る気持ちを表す言葉です。
その出来事や物事によって、しみじみと感じたり、心が揺さぶられたりするような感情を指します。
たとえば、昔の思い出を懐かしく思ったり、感動的な映画を観た時に胸が熱くなったりするような感情が「感慨」です。
感慨は、ただの感動や感傷とは異なり、深い意味を含んでいる言葉なのです。
「感慨」という言葉の読み方はなんと読む?
「感慨」という言葉の読み方は、「かんがい」となります。
漢字の「感」は「かん」と読み、「慨」は「がい」と読みます。
「感慨」は、4つの音節(カギョウ)から成り立っています。
カタカナ表記すると「カンガイ」となりますが、一般的には漢字表記の「感慨」が使われることが多いです。
「感慨」という言葉の使い方や例文を解説!
「感慨」という言葉は、いろいろな場面で使われます。
たとえば、友人の卒業式に出席し、その友人の成長を感じ入った時に「感慨深いですね」と表現することができます。
また、「感慨にふける」という表現もあります。
これは、ある出来事や人物を思い出すなどして深く感じ入り、しばらく思いを巡らせる状態のことを指します。
仕事で成功した後など、ひとり考え込んで感慨にふけることもあるでしょう。
「感慨」という言葉の成り立ちや由来について解説
「感慨」という言葉は、中国の古典文学に由来しています。
中国では、古くから人々の心の内に生まれるさまざまな感情を重んじる文化があり、そこから「感慨」という言葉も生まれたのです。
「感慨」の成り立ちは、漢字の「感」と「慨」の組み合わせによって表されます。
漢字の「感」は感じることを意味し、「慨」は心に起こる深い感情や思いを指しています。
この2つの漢字が組み合わさって、「感慨」という言葉が生まれたのです。
「感慨」という言葉の歴史
「感慨」という言葉は、日本においても古くから使われてきました。
日本の古典文学や漢詩などにもしばしば登場し、人々の心を揺さぶってきました。
また、近代以降の文学や詩においても、「感慨」という言葉は広く用いられてきました。
感動的な作品や歌詞、随筆などには、しばしば「感慨の深い」という表現が使われています。
「感慨」という言葉についてまとめ
「感慨」とは、深い感じ方や感じ入る気持ちを表す言葉です。
昔の思い出に浸ったり、感動的な出来事に触れたりした時に生まれる深い感情を指します。
日本の古典文学や漢詩、近代以降の文学などでも頻繁に使用され、人々の心を揺さぶってきました。
そのため、「感慨」という言葉は、幅広いシチュエーションで使われるようになりました。
親しまれる言葉として、今後も活用されていくことでしょう。