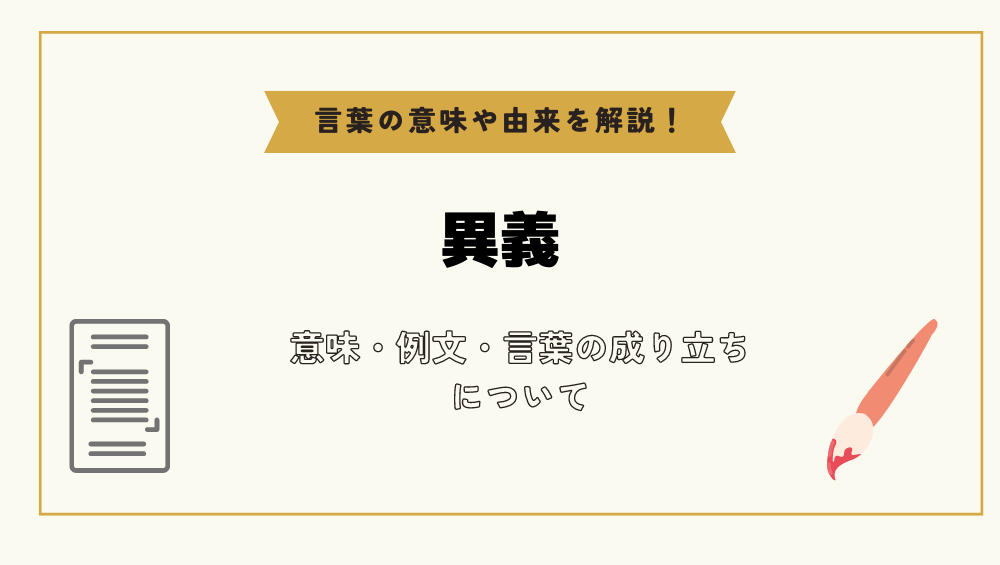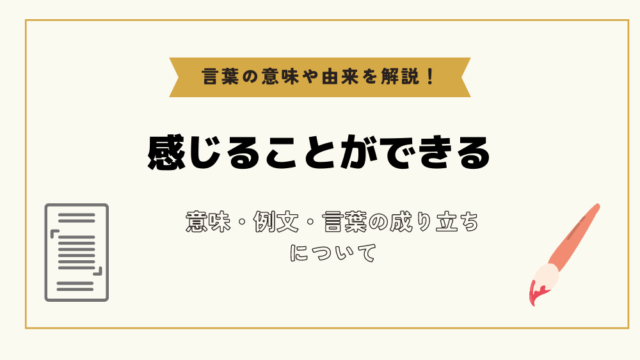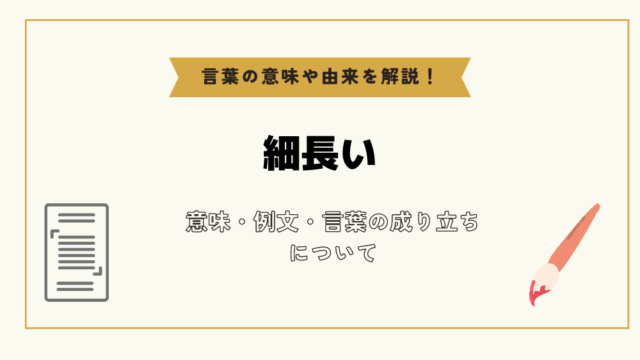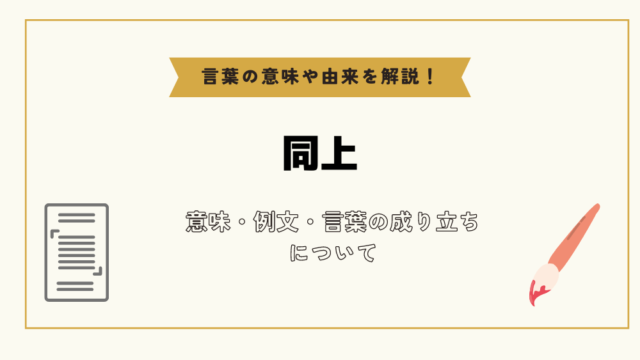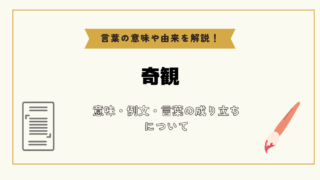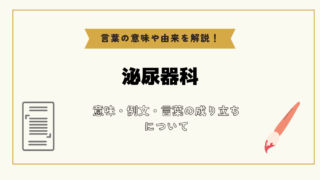Contents
「異義」という言葉の意味を解説!
「異義(いぎ)」とは、一つの語句や表現が複数の意味や解釈を持つことを指します。
言葉の意味が明示されず、文脈や状況によって解釈が異なる場合に使われます。
例えば、「鮭(さけ)」という言葉は、魚の名前として一般的に使われますが、状況によって「サーモン」という意味にもなります。
このように、「異義」は言葉の使われ方が曖昧な場合に使われる言葉です。
「異義」という言葉の読み方はなんと読む?
「異義」は、日本語の漢字読みである「いぎ」と読みます。
この読み方は一般的であり、広く認知されています。
「異義」の読み方が分からない場合は、カタカナ表記で「イギ」や「イテギ」と読んでしまうこともありますが、正しい読み方は「いぎ」です。
「異義」という言葉の使い方や例文を解説!
「異義」の使い方は、文章や会話で他の人が誤解しないよう、十分な文脈や説明を伴うことが大切です。
例えば、「この言葉には異義があるので、よく考えてから使ってください」といった風に使います。
また、例文としては「彼の発言には異義が含まれており、どのような意図で言っているのかはっきりとわかりません」といったものがあります。
ここでも、「異義」を使って、発言の意図が曖昧であることを表現しています。
「異義」という言葉の成り立ちや由来について解説
「異義」は、漢字の「異」と「義」から成り立っています。
「異」は「違う」という意味を持ち、「義」は「意味」という意味を持ちます。
つまり、「異義」の意味は、言葉や表現において違う意味や解釈があることを示しています。
「異義」という言葉の歴史
「異義」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や漢文などでも使用されてきました。
言葉には常に曖昧さがあり、異なる解釈が生まれることがあるため、このような言葉が生まれたのでしょう。
近代では、科学や技術の発展により、専門用語や専門的な表現が増え、その中には異義性を持つものもあります。
そのため、「異義」の重要性が再認識され、言語学やコミュニケーションの分野でも研究されるようになりました。
「異義」という言葉についてまとめ
「異義」は言葉や表現において、複数の意味や解釈があることを指します。
日本語に限らず、言葉の持つ曖昧さはどの言語にも存在します。
ですが、「異義」を理解し、適切な文脈や説明を加えることで、誤解や混乱を避けることができます。
言葉を使う際は注意深く、相手が正しく理解できるように意識しましょう。