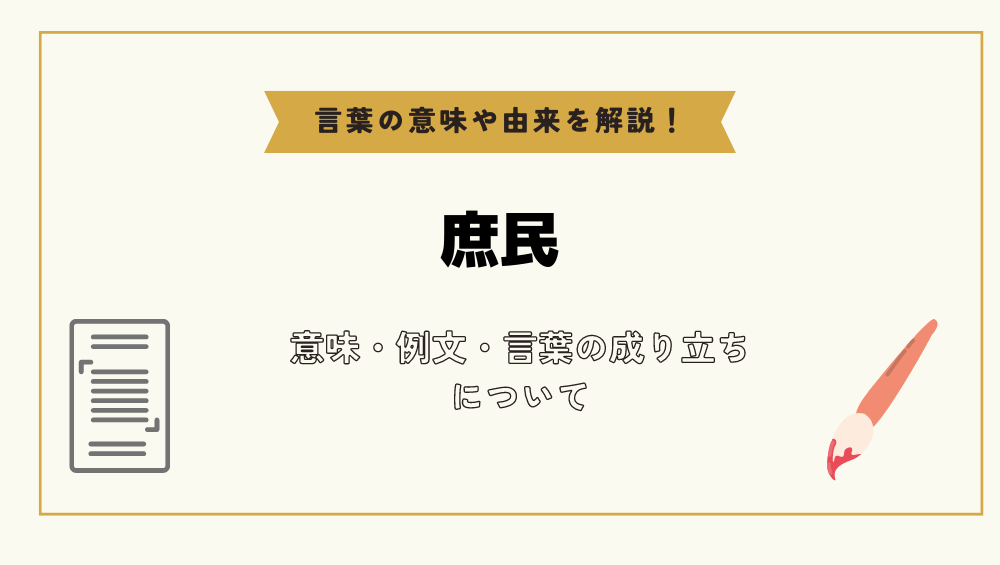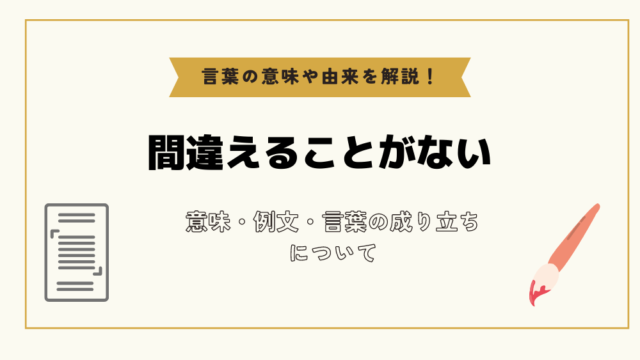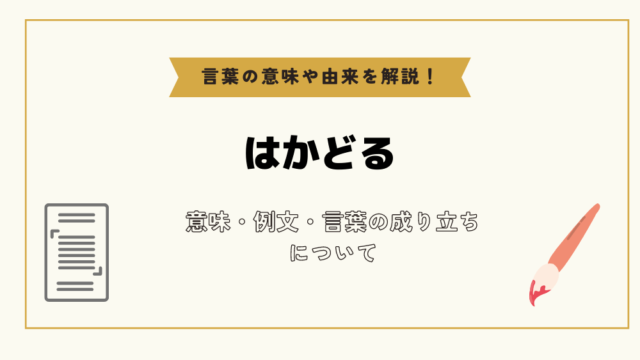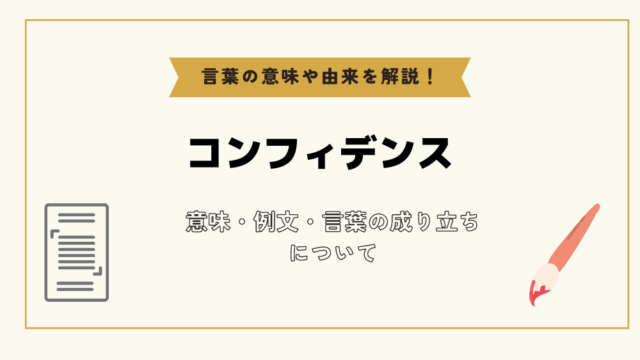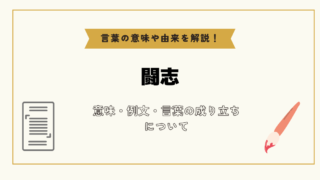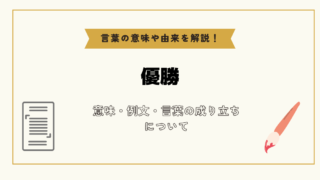Contents
「庶民」という言葉の意味を解説!
「庶民」という言葉は、一般的には「一般庶民の人々」という意味で使われます。
庶民は、特別な地位や財産を持たず、平凡な生活を送る人々を指します。
彼らは王侯貴族や富裕層とは異なり、必要最低限の生活をすることが多いです。
「庶民」の読み方はなんと読む?
「庶民」の読み方は「しょみん」となります。
この読み方で一般的に使われています。
正式な読み方としては「しょたん」と読むこともありますが、一般的な会話ではあまり使われません。
「庶民」という言葉の使い方や例文を解説!
「庶民」の使い方は、一般庶民の人々を指して使用されます。
例えば、「庶民の生活を支えるためには、安定した収入が必要です」といった具体的な用例があります。
また、「庶民的な考え方」といった表現を使うことで、王侯貴族や富裕層とは異なる価値観や生活態度を表現することもできます。
「庶民」という言葉の成り立ちや由来について解説
「庶民」という言葉の由来は、古代日本の社会制度にあります。
庶民は、特定の身分や地位を持たず、一般の人々を指しました。
この言葉は、古代の国家の統治者らが自身を区別するために用いた言葉でした。
その後、現代でもこの言葉が一般的に使われるようになりました。
「庶民」という言葉の歴史
「庶民」という言葉は、古代から現代に至るまで広く使用されてきました。
古代においては、王侯貴族や公家とは異なる一般の人々を指す言葉でした。
中世になると、武士や町人といった身分の区別も生まれましたが、庶民はこれらに含まれる範疇とされました。
そして現代でも、庶民という言葉は一般の人々を指すために使われています。
「庶民」という言葉についてまとめ
「庶民」という言葉は、一般の人々を指す言葉として古代から現代まで広く使用されてきました。
庶民は特別な地位や財産を持たず、平凡な生活を送る人々を指します。
この言葉は、社会の階級や身分の区別を意識する場面で用いられることが多く、王侯貴族や富裕層とは異なる価値観や生活態度を表現する際にも使われます。