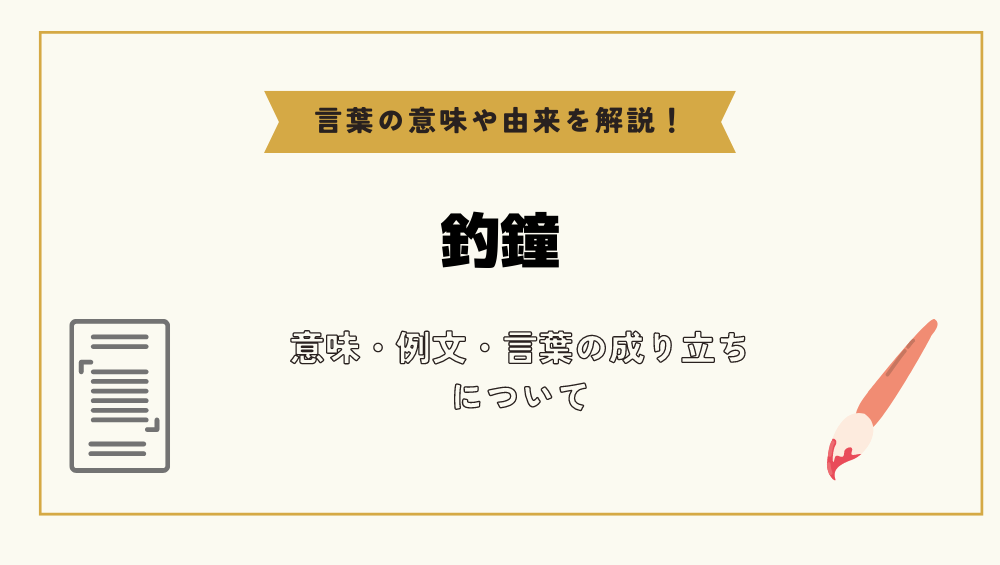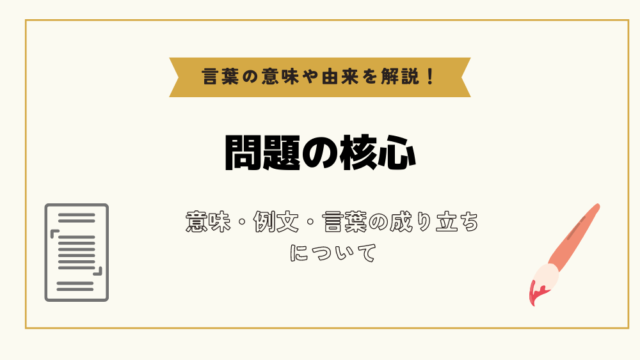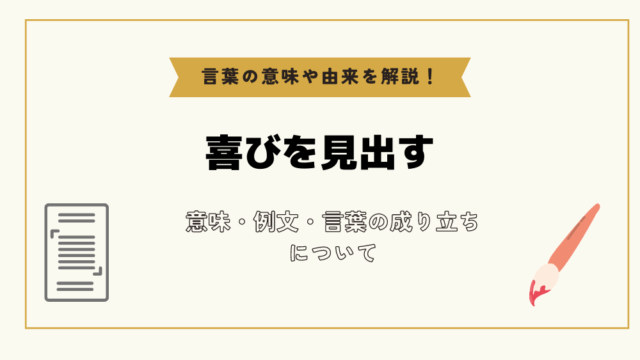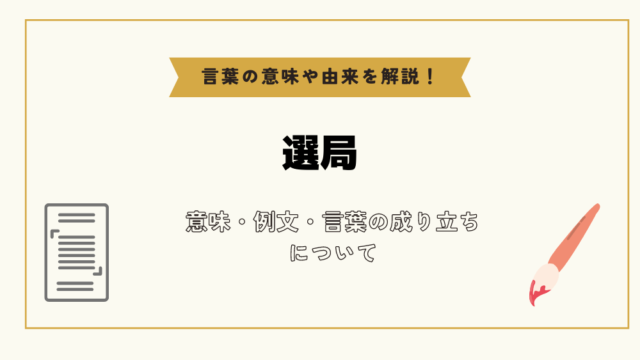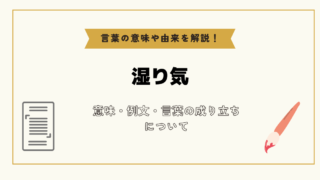Contents
「釣鐘」という言葉の意味を解説!
「釣鐘」という言葉は、鐘を釣るための装置を指す言葉です。
釣鐘は、通常、ロープや鎖を使って吊り下げられ、その形状からその名前が付けられました。
釣鐘は主に建物や寺院の鐘楼で使用され、時を知らせたり宗教的な儀式や儀礼に使用されることがあります。
「釣鐘」の読み方はなんと読む?
「釣鐘」という言葉は、「ちょうしょう」と読みます。
この読み方は、一般的に使用されており、広く知られています。
日本語の言葉には、読み方が複数存在することもありますが、この場合は「ちょうしょう」という読み方が主流です。
「釣鐘」という言葉の使い方や例文を解説!
「釣鐘」という言葉は、鐘を吊るすための装置を指す一般的な用語です。
例えば、建物の屋根に釣鐘を設置する場合、釣鐘を吊り上げるためのフックやロープを使用します。
「彼は釣鐘をつかむために手を伸ばした」といった表現でも使用することができます。
「釣鐘」という言葉の成り立ちや由来について解説
「釣鐘」という言葉の成り立ちや由来については、特定の歴史的な経緯や元となる言葉は存在しません。
ただ、その形状が釣りをする際に使われる釣り針や釣り具に似ていることから、「釣鐘」という名前が付いた可能性があります。
また、鐘を吊るす際に天井や棒のようなものに釣り掛けるため、釣りのイメージが重ねられたのかもしれません。
「釣鐘」という言葉の歴史
「釣鐘」という言葉の歴史については、具体的な情報が限られています。
ただし、日本では古くから寺院や神社の鐘楼に釣鐘が使用されてきました。
日本の歴史や文化において、釣鐘は宗教儀式や祈りのために使われる重要なアイテムとして位置づけられています。
「釣鐘」という言葉についてまとめ
「釣鐘」という言葉は、鐘を吊り下げるための装置を指す言葉です。
「ちょうしょう」と読みます。
釣鐘は主に建物や寺院の鐘楼で使用され、時を知らせたり宗教的な儀式や儀礼に活用されます。
由来や成り立ちは特定の歴史的な経緯はないようですが、釣りのイメージから名前が付いた可能性があります。
日本の歴史や文化において重要な役割を果たす存在です。