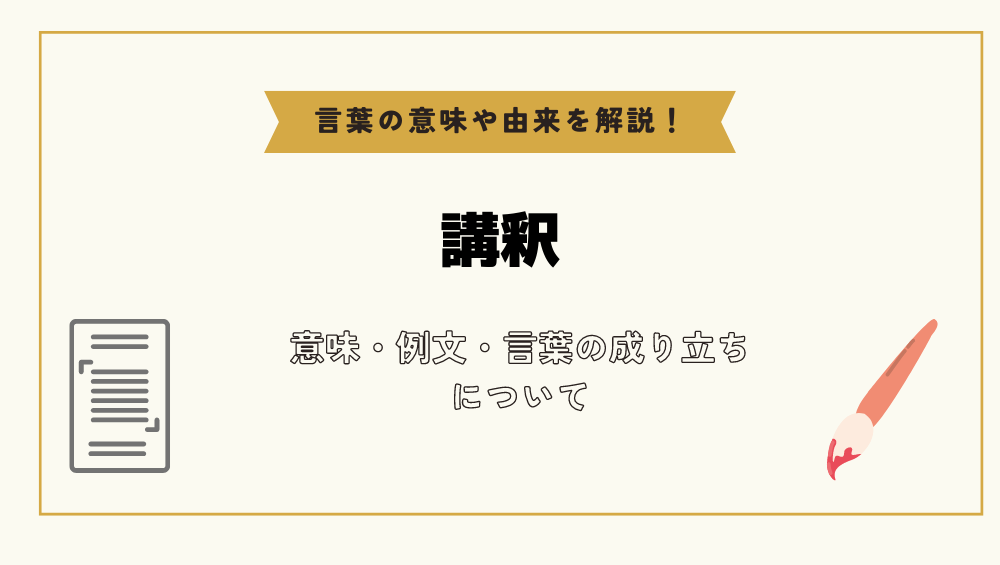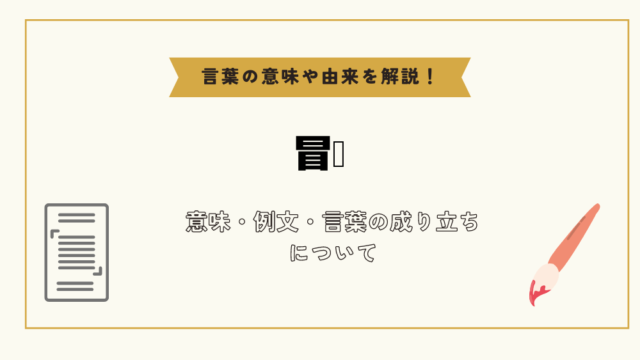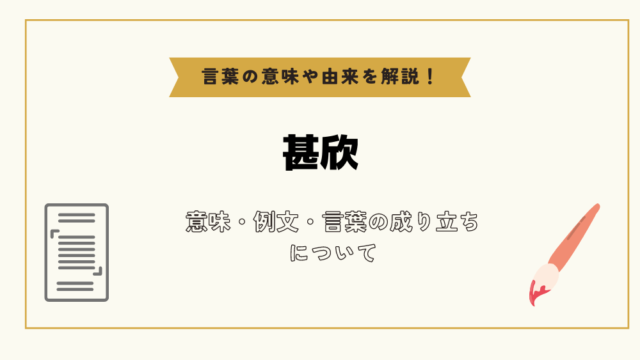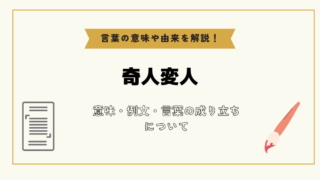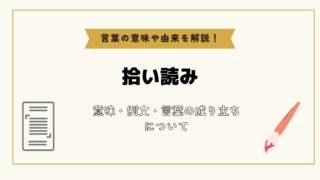Contents
「講釈」という言葉の意味を解説!
講釈(こうしゃく)とは、物事や主題についての解説や説明をすることを指します。
日本では、特に古典文学や歴史に関する解説を指すことが多いです。
講釈は、読者や聴衆に対して情報を提供し、理解を深める役割を果たします。
また、講釈は教育や文化の一環としても重要であり、伝統的な文化の継承にも関わっています。
「講釈」という言葉の読み方はなんと読む?
「講釈」という言葉は、「こうしゃく」と読みます。
「こう」という音は、高い音で「しゃく」という音は、しゃがんでいるような感じで音を出します。
日本語の読み方は、単語ごとに音を区切り、正確な発音で読むことが大切です。
「講釈」という言葉の使い方や例文を解説!
「講釈」という言葉は、特に文学や歴史に関連する解説や説明をする場合に使われます。
「彼は講釈が上手で、話し方がとても興味深い」というように、講演や説明で人々を引き付ける力があることを指します。
また、「昨日の講釈はとても分かりやすかった」というように、説明が分かりやすく、聴衆に伝える力があることを意味します。
「講釈」という言葉の成り立ちや由来について解説
「講釈」という言葉は、中国の古典文学である漢文文献に由来しています。
日本では、江戸時代に講釈が盛んに行われるようになり、現在の意味での使用が広まりました。
講釈師や専門の講釈集団が存在し、著名な作品や歴史的な事件について解説を行っていました。
「講釈」という言葉の歴史
「講釈」という言葉は、日本の文化や芸能の歴史に深く関わっています。
江戸時代には、講釈を専門に行う講釈師や講釈集団が現れ、人々に娯楽や知識を提供しました。
特に、寺社や町人の間で講釈が盛んに行われ、さまざまな話題についての解説が行われました。
講釈は、教養や伝統文化を広める役割も果たしてきました。
「講釈」という言葉についてまとめ
「講釈」という言葉は、解説や説明をすることを指します。
古典文学や歴史に関連した話題の解説や講演を行う際に使用されます。
その起源は中国の漢文文献にあり、江戸時代に日本で発展しました。
講釈は、伝統文化や教育の一環としても重要であり、読者や聴衆に知識や情報を提供する役割を果たしています。