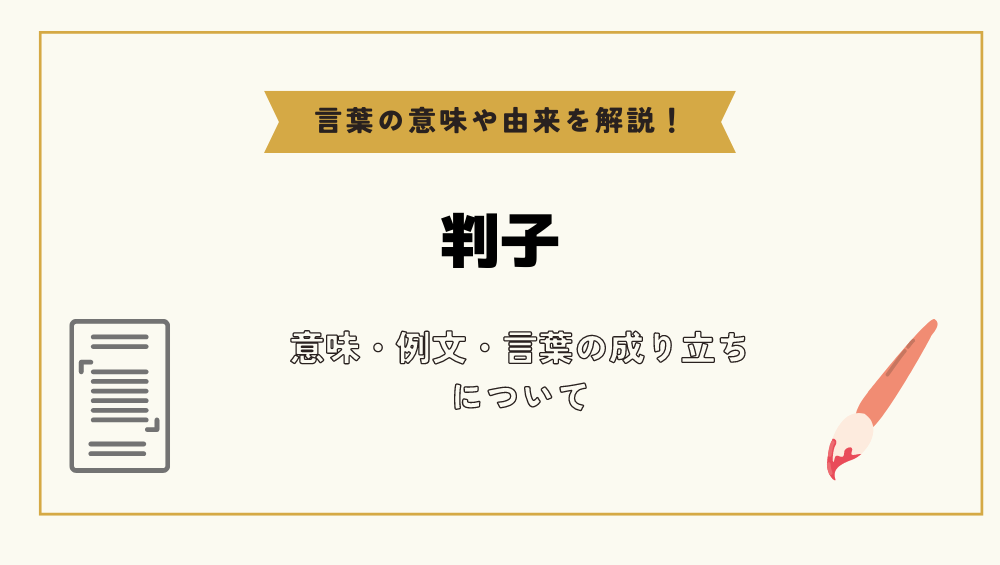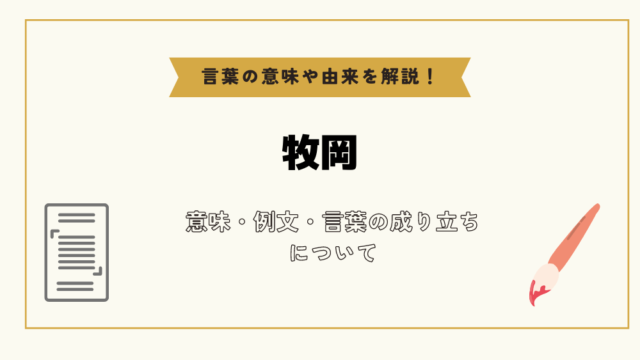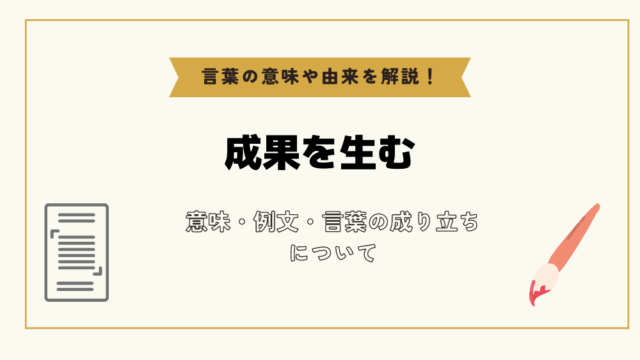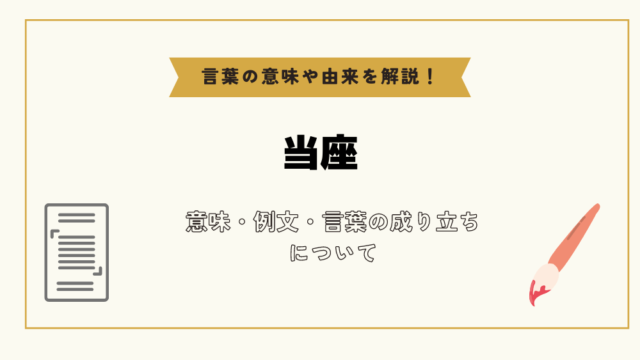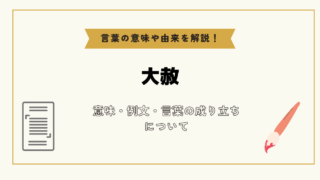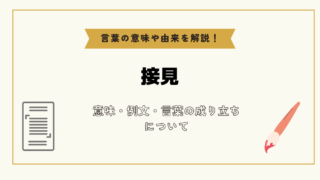Contents
「判子」という言葉の意味を解説!
「判子」とは、日本で古くから使われてきた印鑑のことを指す言葉です。
印鑑は、個人や法人の身分や権限を証明するために使用されます。
日本では、書類に署名をする代わりに、判子を押すことが一般的なので、非常に重要な存在となっています。
「判子」という言葉の読み方はなんと読む?
「判子」という言葉の読み方は、「はんこ」となります。
日本語の発音では、「んこ」の部分が鼻濁音となるため、「はんこ」となります。
一般的にはこの読み方が使われています。
「判子」という言葉の使い方や例文を解説!
「判子」という言葉は、日常生活やビジネスの中でよく使われます。
例えば、契約書に自分の判子を押すことで、契約内容に同意したことを示すことができます。
また、重要な書類に判子を押さないと、手続きが進まない場合もあります。
そのため、判子は非常に大切な文化的なアイテムと言えます。
「判子」という言葉の成り立ちや由来について解説
「判子」という言葉は、中国から伝わったとされています。
中国においても、日本と同様に印鑑が重要な役割を果たしており、それが日本にも伝わったと言われています。
また、「判子」という言葉は、印章の形状が「刀」と似ていることからきているとも言われています。
「判子」という言葉の歴史
「判子」という言葉は、日本の歴史において非常に重要な役割を果たしてきました。
古代日本においては、天皇の判子が重要なシンボルとされ、権威の象徴とされていました。
また、江戸時代になると、武士や商人の判子も一般的になり、個人の身分や地位を示すために使用されるようになりました。
「判子」という言葉についてまとめ
「判子」という言葉は、日本の文化や社会に深く根付いている重要なアイテムです。
個人や法人の身分や権限を証明するために使用される点が特徴であり、日本独自の文化として広く認知されています。
印鑑としての機能だけではなく、歴史や文化の一環としても大切な存在と言えます。