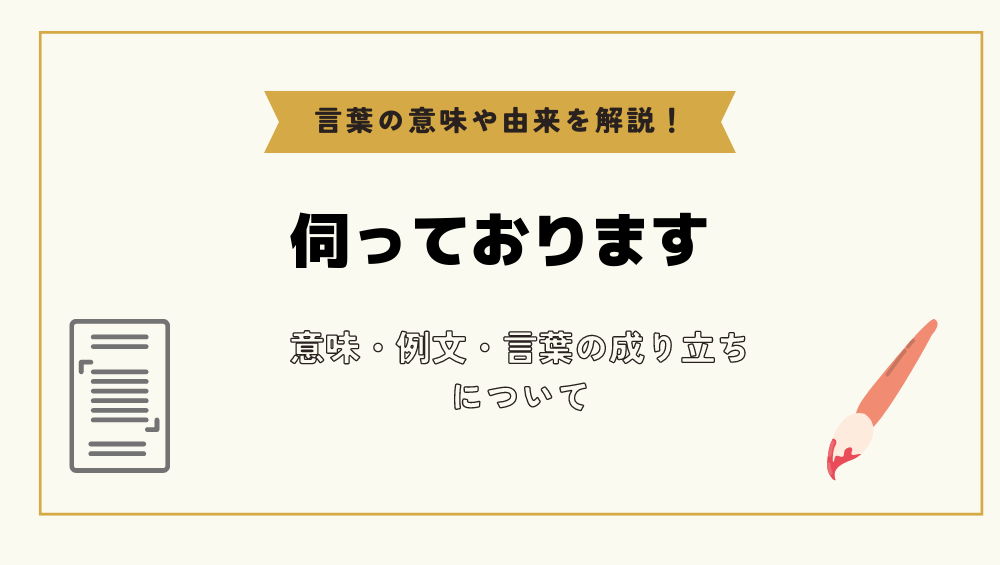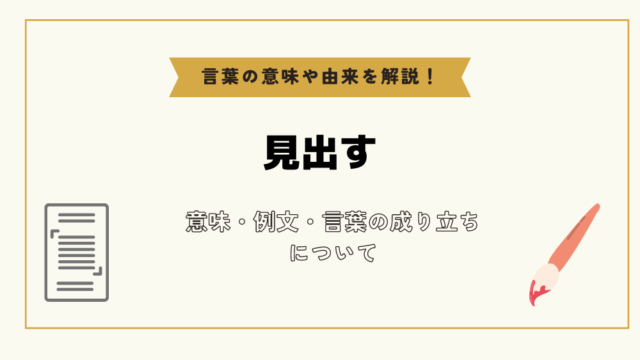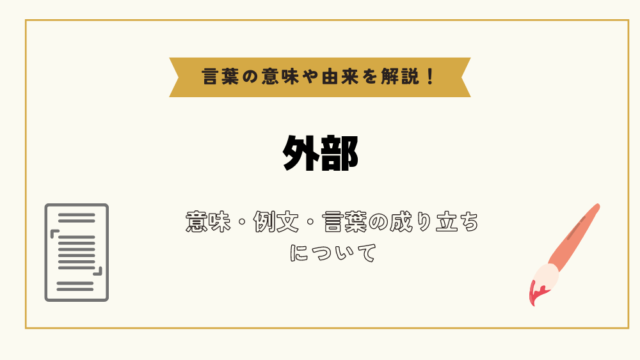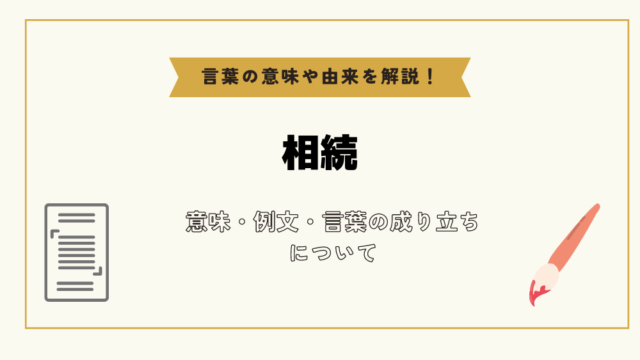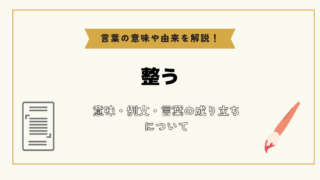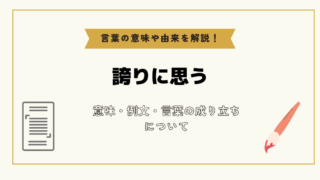「伺っております」という言葉の意味を解説!
「伺っております」とは、相手から聞いた情報を自分が承知していることを示す最上級の敬語表現です。相手への最大級の敬意を払いながら「聞いている」「承知している」という事実を伝えるため、ビジネスや公的な場面で多用されます。敬語の中でも「謙譲語Ⅱ」に分類されるため、自分側の行為を低め、相手側を高めるニュアンスが含まれています。
「聞く」の謙譲語「伺う」に、継続・進行を表す「ておる」と丁寧さを加える「ます」を付けた形が「伺っております」です。これにより、単なる過去形ではなく現在進行形や状態の継続を示せる点が特徴です。
敬語は誤用するとかえって失礼になるため、「伺っております」の用途は「私は確かに情報を受け取っています」という場面に限定すると良いでしょう。適切に使えば相手に安心感を与え、円滑なコミュニケーションを実現できます。
「伺っております」の読み方はなんと読む?
読み方は「うかがっております」で、「伺」の字は常用外ですが一般的に訓読みの「うかがう」を当てるのが慣例です。日本語学習者には少し難しい漢字ですが、ビジネス文書やメールでも常用されるため覚えておくと役立ちます。
「伺」は「人を敬って、人のところへ行く」「尋ねる」「聞く」などの意味を持つ漢字です。「伺い知る」「伺候(しこう)」といった語でも同じ読み方が登場します。
さらに「ております」は「ておる+ます」の音便形で、「ております」の表記が正式です。「伺っております」はひらがなで「うかがっております」と書いても誤りではありませんが、ビジネス文書では漢字を用いる方が格式を保てます。
「伺っております」という言葉の使い方や例文を解説!
使う際は「すでに情報を受領している」事実を示すとともに、相手に敬意を払う目的で選択するのがポイントです。主語は多くの場合「私ども」「弊社」など自分側の集団になり、自身を低める姿勢を保ちます。
【例文1】担当者からご提案内容については伺っております。
【例文2】○月○日に開催予定の会議の詳細は伺っております。
最敬語に近い表現のため、カジュアルな会話では「聞いています」で十分です。目上の人や取引先に向けて使うと、相手との距離感を適切に保てます。
誤用として「私はあなたに伺っております」とすると「訪問しているのか?聞いているのか?」と意味があいまいになりがちです。「情報を伺っております」「お越しを伺っております」のように、何を承知しているのかを具体的に示すと誤解を防げます。
「伺っております」という言葉の成り立ちや由来について解説
「伺う」は平安時代の古典にも登場する語で、宮中での謙譲表現が一般社会へ広まった経緯があります。古語では「うかがふ」と仮名表記され、「目上の人の意向をお聞きする」「ご機嫌をうかがう」などの用法で使われていました。
やがて武家社会を経て商家文化が栄えるにつれ、礼儀作法としての謙譲表現が商取引にも浸透しました。「伺っております」は「伺う」に進行形を表す「ておる」を組み合わせ、さらに丁寧語「ます」を加えた重層的な敬語となりました。
文法的には「伺う(動詞)」+「て(接続助詞)」+「おる(補助動詞)」+「ます(丁寧語)」で構成されます。補助動詞「おる」はラ行五段活用動詞「居る」の謙譲表現に由来し、自分の状態をへりくだって述べる目的で使用されます。
「伺っております」という言葉の歴史
江戸時代には商家のお得意様への書状で「早々御用、伺って居ります」という形が確認され、明治期の公用文にも継承されました。江戸後期には全国で往来の書状が盛んになり、謙譲語が固定化されるなかで「伺っております」が定着します。
明治期の官庁文書では「伺候(しこう)仕りおる」のような漢語的表現も併存しましたが、昭和期に入り「伺っております」が簡潔で汎用的な敬語として広く用いられるようになりました。
現代ではビジネスメールやニュース番組のアナウンサーが常套句として使用し、特に「ただいま速報を伺っております」といった形で公式発表前の段階を示す表現としても機能しています。
「伺っております」の類語・同義語・言い換え表現
主な類語には「承知しております」「お聞きしております」「拝聴しております」などがあり、状況に応じた使い分けが重要です。「承知しております」は内容を理解し了承しているニュアンスが濃く、指示を受けている場面で便利です。「お聞きしております」は単に情報を聞いた事実を丁寧に伝える際に適しています。
「拝聴しております」は「聴く」の謙譲語「拝聴」を用いるため、講演やスピーチなどフォーマルな場で耳を傾けている状態を示します。「うかがっておりますですと重い」と感じた場合の調整表現として「聞いております」も候補になりますが、敬意の度合いは下がるため相手との関係性を踏まえて選択しましょう。
「伺っております」についてよくある誤解と正しい理解
「伺っております」を「訪問している最中」と誤解するケースがありますが、本来は「聞く」「承知する」の意味に限られます。動詞「伺う」には「訪問する」という意味もあるため混同が生じやすいのです。
例えば「明日伺います」は訪問の意、「その件は伺っております」は情報の意となり、文脈が明確なら誤解は避けられます。「すでに社長に伺っております」という表現は「社長に尋ねた」のか「社長から聞いた」のかを補足しなければ曖昧になるため注意が必要です。
また、メールの冒頭で「ご連絡を伺っております」と書くと「連絡を待っている」という意味に読まれる恐れがあります。正しくは「ご連絡を頂けると伺っております」のように、情報源を示す語を付加すると誤解を防げます。
「伺っております」を日常生活で活用する方法
家庭内や友人同士では堅すぎる場合が多いため、相手が明確に目上であるときだけ用いるのがコツです。例えば子どもの学校の先生や自治会長など、公式性のある相手には丁寧さを示す効果があります。
【例文1】保護者会の日時につきましては先生から伺っております。
【例文2】ご近所の○○様がお見舞いに来られると伺っております。
日常会話での過度な敬語は距離を生むこともあるため、親しい相手には「聞いてるよ」「知ってるよ」と言い換える柔軟さも必要です。メールやチャットでは「伺っております」と入力する際、スマホの変換候補が出にくい場合があるので、辞書登録しておくとスムーズに入力できます。
「伺っております」という言葉についてまとめ
- 「伺っております」は相手から得た情報を承知していることを示す最上級の敬語表現。
- 読み方は「うかがっております」で、漢字を用いると格式が高まる。
- 平安期の「うかがふ」に由来し、江戸期の書状を経て現代のビジネス敬語として定着。
- 誤用を避けるため訪問の意味との区別や場面に応じた類語との使い分けが重要。
本記事では「伺っております」の意味、読み方、使い方、歴史、類語、誤解のポイントまで幅広く解説しました。敬語は相手との関係性を潤滑にし、日本文化の礼節を伝える大切なツールです。
正しい知識を身につけておくことで、ビジネスでも日常でも誤解なく自信を持ってコミュニケーションが取れるようになります。今後はメールや会話で迷ったとき、本記事のポイントを思い出しながら最適な表現を選んでみてください。