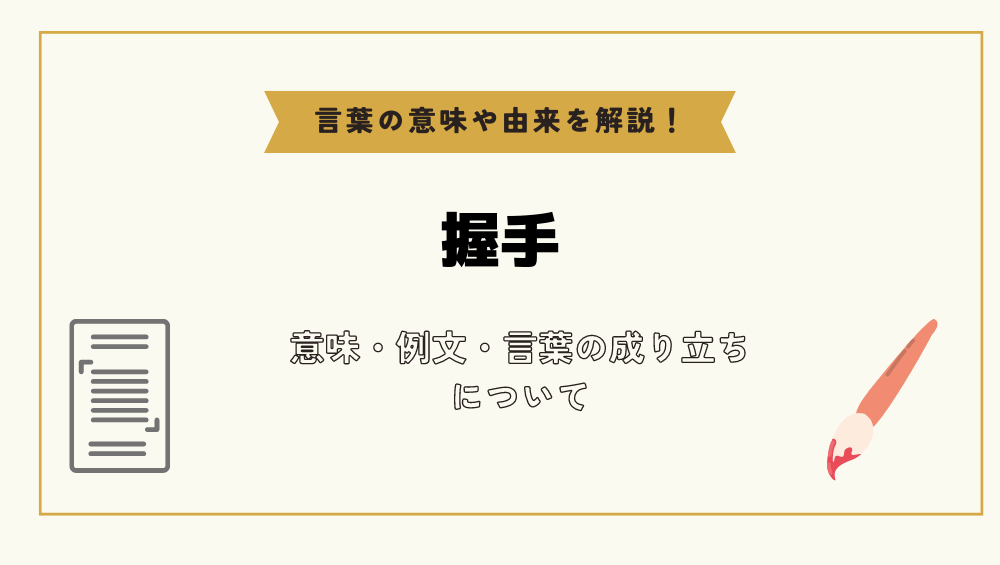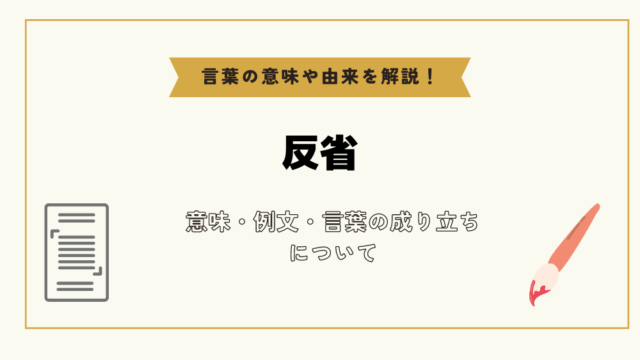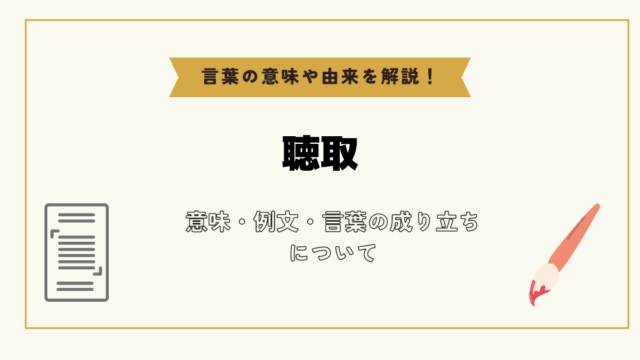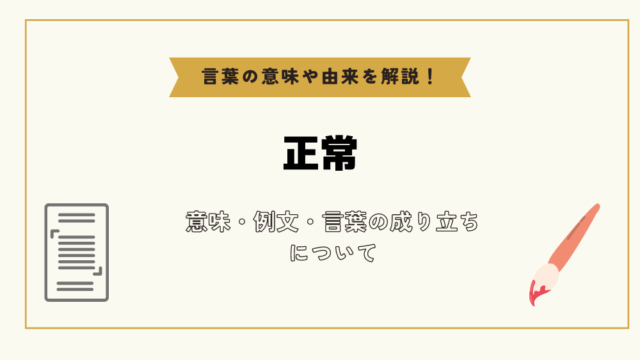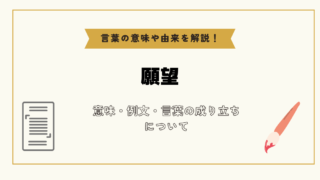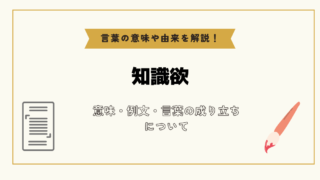「握手」という言葉の意味を解説!
握手(あくしゅ)とは、互いの片手を取り合い、軽く振るか静止させることで友好・敬意・合意などを示す身体的コミュニケーションの一種です。
この行為は単なる挨拶にとどまらず、ビジネスシーンで契約の成立を確認する合図としても機能します。
また、スポーツ競技では試合前後に交わして相手を称える意味を持つなど、場面により微妙にニュアンスが変化します。
握手は第三者から見ても瞬時に関係性を理解できる視覚的サインです。
そこには「敵意がない」「相手を信頼している」という無言のメッセージが含まれます。
最近では感染症対策の観点から握手を控える場面も増えましたが、肘タッチや会釈に置き換わっても「相手を尊重する」根本的な精神は変わっていません。
つまり握手は、人類が言語を超えて共有してきた「安心のシンボル」と言えるのです。
「握手」の読み方はなんと読む?
「握手」は一般的に「あくしゅ」と読みます。
音読みのみで成り立ち、訓読みや送り仮名は存在しません。
「握」の字は「手でしっかりと握る」という意味を持ち、「手」はそのまま手を示します。
両者が結び付いた熟語のため、読み方は比較的覚えやすい部類に入ります。
ひらがな書きの「あくしゅ」を使えば小学生でも読みやすく、公的文書では漢字表記が好まれます。
ただし誤って「にぎりて」などと訓読みする例も見られるので注意しましょう。
ビジネスメールや掲示物では「あくしゅ(握手)」のようにルビを振ると誤読を防げます。
「握手」という言葉の使い方や例文を解説!
ビジネス、スポーツ、日常会話など幅広い場面で用いられます。
とくに「契約の締結を示すジェスチャー」として世界共通の意味を持つため、国際的な取引でも頻繁に登場します。
【例文1】新しいパートナー企業と握手を交わし、正式に提携がスタートした。
【例文2】試合終了後、両チームのキャプテンが握手で健闘を称え合った。
文章上では「握手を求める」「固い握手を交わす」のように動詞とセットで使われるのが一般的です。
その際、「握手する」よりも「握手を交わす」と書くほうが丁寧な印象になります。
敬語表現では「握手させていただく」「握手していただく」の形を取り、相手への敬意を保ちます。
カジュアルな会話では「ハイタッチしよう!」のように別のアクションへ置き換えることも増えています。
「握手」という言葉の成り立ちや由来について解説
「握」という字は手偏に「屋」を組み合わせ、「手の中に収める」という象形的な意味を持ちます。
「手」は人間の手そのものを示し、二字が連なることで「手を握る」と直感的に理解できます。
由来を遡ると、古代西アジアや地中海沿岸で「武器を持っていない」ことを示す合図として手を開き、その後握り合う形が定着したといわれます。
敵対関係を避ける目的が、友好を示すサインへと発展したのが握手のルーツです。
日本語としては明治初期に翻訳語として普及しました。
それまでは「手をとる」「手を取り合う」と表現されていましたが、西洋文化の流入とともに「握手」が一語として定着しました。
「握手」という言葉の歴史
最古の記録は紀元前9世紀頃のアッシリア石碑で、王と家臣が握手する姿が刻まれています。
古代ギリシャでも神々の手を取り合う図が陶器に描かれ、紀元前5世紀頃には挨拶の型として一般化していました。
ローマ時代には「デクストラム・ジュンクシオン(右手の結合)」と呼ばれ、結婚契約や軍同盟の象徴でした。
中世ヨーロッパで騎士が武器を持たないことを示す所作として受け継がれ、近代に入ると外交儀礼として世界中へ広がります。
日本では1868年(明治元年)に岩倉具視が米国使節団と初めて握手を交わした記録が残っています。
20世紀以降の国際交流拡大により、握手は名刺交換と並ぶビジネスマナーとして定着しました。
「握手」の類語・同義語・言い換え表現
最も近い類語は「ハンドシェイク」で、英語をそのままカタカナ化した言い換えです。
ほかに「手合わせ」「手打ち」も条件付きで同義に使われますが、文脈により意味が変わるので注意が必要です。
「契約成立」を示す場面では「合意のサイン」「クロージングジェスチャー」といった表現も広がっています。
日本語でフォーマルに言い換えるなら「固い握手を交わす」よりも「固く手を取り合う」が自然です。
一方、カジュアルシーンでは「あいさつ代わりにグータッチ」「ハイタッチ」が視覚的・感覚的に近い行為として機能します。
「握手」の対義語・反対語
言語学的に完全な対義語は存在しませんが、「対立を示す行為」として「突き放す」「手を拒む」が逆のニュアンスを持ちます。
外交文脈では「決裂」「破談」が抽象的な反対語になり得ます。
身体動作として比較すると、手を差し出されても受け取らない「ノーハンド」が最も明確な反対行為です。
つまり握手は「受容と協調」を示し、拒否は「拒絶と不信」を象徴する点で反対関係にあります。
「握手」を日常生活で活用する方法
まず大切なのはタイミングです。
自己紹介の直後に軽く握手すると、相手にポジティブな第一印象を与えられます。
握手をする際は、相手の目を見て2〜3回軽く上下させるのが国際標準のマナーです。
力が強すぎると威圧感を与え、弱すぎると自信のなさを印象付けるので、適度な力加減を心がけましょう。
感染症が気になる場合は手指消毒を行い、「衛生面が気になるので失礼します」と声を添えることで配慮を示せます。
子どもとのコミュニケーションでは握手と同時に名前を呼びかけると安心感を育む効果があります。
「握手」に関する豆知識・トリビア
アメリカ大統領選の選挙運動では、候補者が握手した人数を「ハンドシェイク・インデックス」として記録し、支持率の指標とする文化があります。
また、ギネス世界記録では「8時間連続で最も多く握手した人数」というカテゴリーが存在します。
宇宙空間で行われた初の握手は1975年の米ソ共同ミッション「アポロ・ソユーズテスト計画」で、両国の宇宙飛行士がドッキング完了後に交わしました。
日本ではプロ野球のドラフト会議後に、交渉権を獲得した球団代表と指名選手が握手する姿が風物詩となっています。
心理学研究によると、温かい手で握手すると相手の印象評価が平均15%上昇するという実験結果も報告されています。
「握手」という言葉についてまとめ
- 「握手」は相手の手を取り合い友好・敬意・合意を示す非言語コミュニケーション手段です。
- 読み方は「あくしゅ」で、漢字表記とひらがな表記の両方が用いられます。
- 古代西アジアに起源があり、武器を持たない証として広まったとされています。
- 現代では感染症対策に配慮しつつも、ビジネスやスポーツで重要なマナーとして活用されています。
握手はシンプルながら奥深い文化的背景を持つ行為です。
歴史を紐解くと敵対心を解くサインから始まり、現在では信頼構築の礎として世界中で愛用されています。
読み方やマナーを正しく理解し、場面に応じた力加減やタイミングを意識することで、相手に温かい印象を与えられます。
「手を取り合う」という古来からの精神を大切にしながら、衛生面への配慮など現代的アレンジを加えていきましょう。