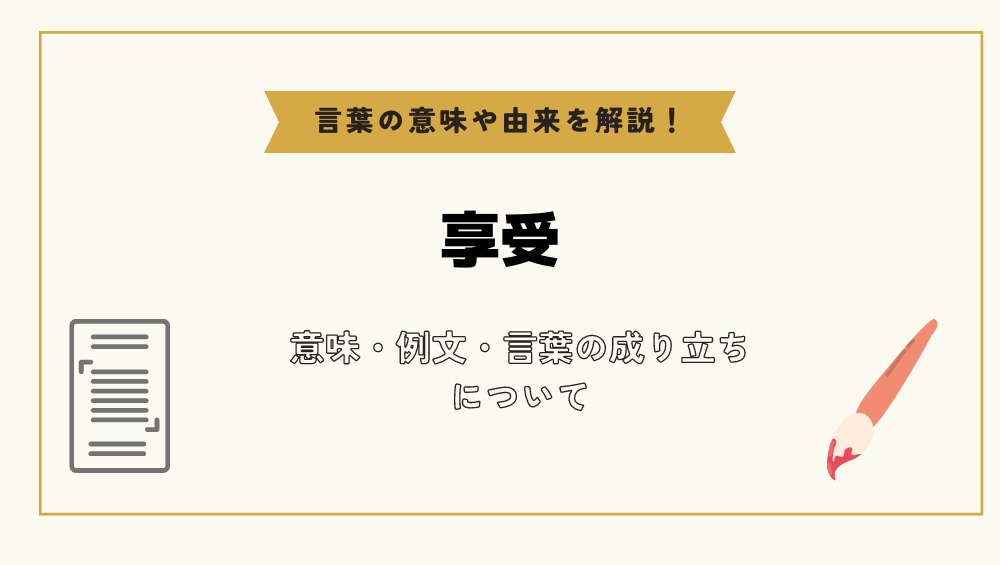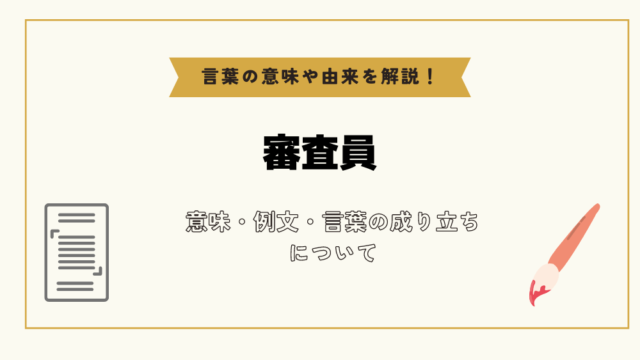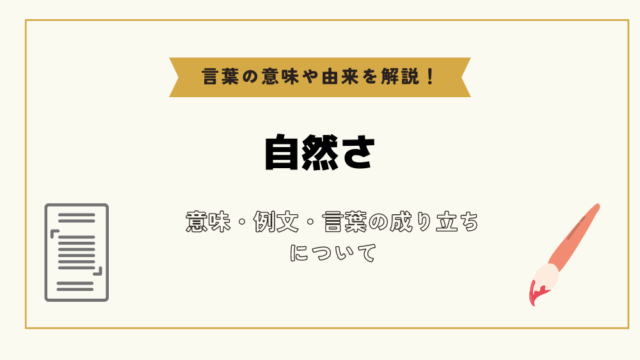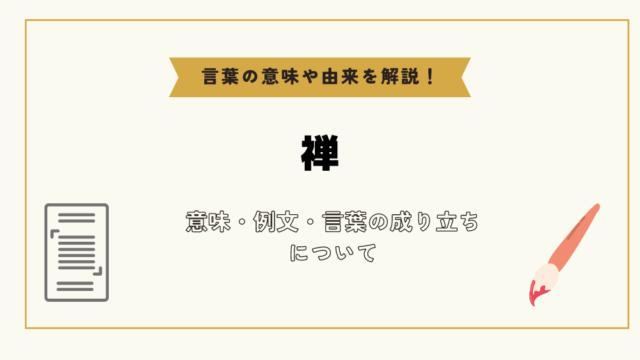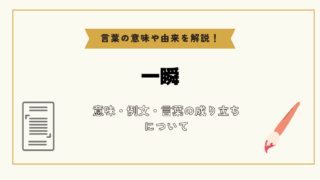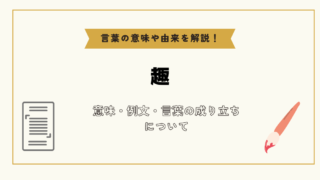「享受」という言葉の意味を解説!
「享受(きょうじゅ)」とは、ある物事や権利・利益を自分のものとして受け取り、おおいに味わい楽しむことを指します。具体的には「与えられた恩恵を受け取り、その価値を十分に堪能する」というニュアンスが含まれます。
法律分野では「権利を享受する」という表現が多く、権利を合法的に行使して利益を得る行為を示します。
日常会話では「休日を享受する」「音楽を享受する」のように、楽しみや喜びを積極的に味わう意味で広く使われています。
「享受」の読み方はなんと読む?
「享受」は音読みのみで「きょうじゅ」と読みます。訓読みや混同されがちな読み方(こうじゅ・きょうじゅう等)は誤りなので注意しましょう。
「享」の字は「うけたまわる」「うける」の意味を持ち、「受」は「受け取る」を表します。
携帯やパソコンの変換で素早く出てきますが、まれに「供授(きょうじゅ)」と誤変換されることがあるため、ビジネス文書では最終確認を怠らないことが大切です。
「享受」という言葉の使い方や例文を解説!
「享受」はフォーマルな場面だけでなくカジュアルな会話でも使えます。動詞的に「〜を享受する」というかたちで目的語を取る点がポイントです。
【例文1】自然豊かな環境を享受する。
【例文2】福祉サービスを享受できる社会を目指す。
例文のように抽象的な「環境」「サービス」や具体的な「休日」「音楽」など、幅広い名詞を目的語に取れるのが特徴です。
一方で、自分が不当に得た利益には「享受」を使わず「搾取」や「不当利得」と区別するのが一般的です。
「享受」という言葉の成り立ちや由来について解説
「享受」は中国古典由来の熟語で、「享」は「供える・受ける」、「受」は「受け取る」を示します。両字が連なることで「授けられたものを受け取り楽しむ」という意味が完成しました。
唐代の文献にはすでに「享受」の語が登場し、仏教経典の漢訳にも用例があります。
日本には平安期に仏典を通じて入り、当初は宗教的な「法悦を享受する」といった文脈で用いられていましたが、近世以降は世俗的意味合いが強まりました。
「享受」という言葉の歴史
奈良・平安時代には漢籍僧侶の間で限定的に使われ、鎌倉期の禅宗文献でも確認できます。
江戸時代になると朱子学や儒教書の普及で知識人層に浸透し、明治期には法典編纂の影響で法律用語として定着しました。特に1898年施行の旧民法では、「財産権の享受」という表現が公文書で初めて明確に採用されました。
現代では法律・経済・観光・ライフスタイルなど多岐にわたり使われ、SNSで「推し活を享受する」といったカジュアル表現も見られます。
「享受」の類語・同義語・言い換え表現
「享受」と似た意味を持つ語には「堪能」「満喫」「味わう」「享受する権利を行使する場合は『行使』『所持』」などが挙げられます。最も近いニュアンスを持つのは「満喫」で、喜びや楽しさを十分に感じる点が共通しています。
ただし「堪能」は高度な技能を持つ場合にも使われるため、文脈によっては置き換えが難しい場合があります。
ビジネス文書では「受益」「利得」といった漢語を使うとやや硬い印象を与え、「享受」より限定的な意味になることもあります。
「享受」の対義語・反対語
対義語として代表的なのは「喪失」「剥奪」「不享」などです。「権利を享受する」の反対は「権利を喪失する」や「権利を剥奪される」と表現できます。
日常場面では「楽しみを享受する」の反対として「楽しみを奪われる」「我慢する」が使われることもあります。
対義語を理解しておくと文章の対比構造が明確になり、説得力が高まります。
「享受」についてよくある誤解と正しい理解
「享受」は「教授(きょうじゅ)」と音が似ているため、読み間違いや誤入力の指摘が多い語です。
また、「享受」はあくまで「与えられたものを受けて味わう」意味であり、「自力で獲得する」ニュアンスは含みません。自分で生み出した成果を楽しむ場合は「達成感を味わう」「成果を享受する」のように補足語を入れると誤解を防げます。
さらに、マイナス要素(損害・苦痛)には通常「享受」を用いないため、「痛みを享受する」という表現は一般には不自然です。
「享受」という言葉についてまとめ
- 「享受」とは、与えられた恩恵や権利を受け取り、十分に味わい楽しむこと。
- 読み方は音読みのみで「きょうじゅ」と読む。
- 中国古典由来で、日本では平安期に導入され、明治期に法律用語として定着。
- 権利やサービスなどフォーマルな文脈から日常的な楽しみまで幅広く使えるが、読み間違いと誤用に注意。
「享受」は古典的な背景を持ちながらも、現代では日常語としても法律用語としても活躍する便利な言葉です。
読みやすさと正確さを意識しつつ、権利や楽しみを表現する際に上手に取り入れてみてください。