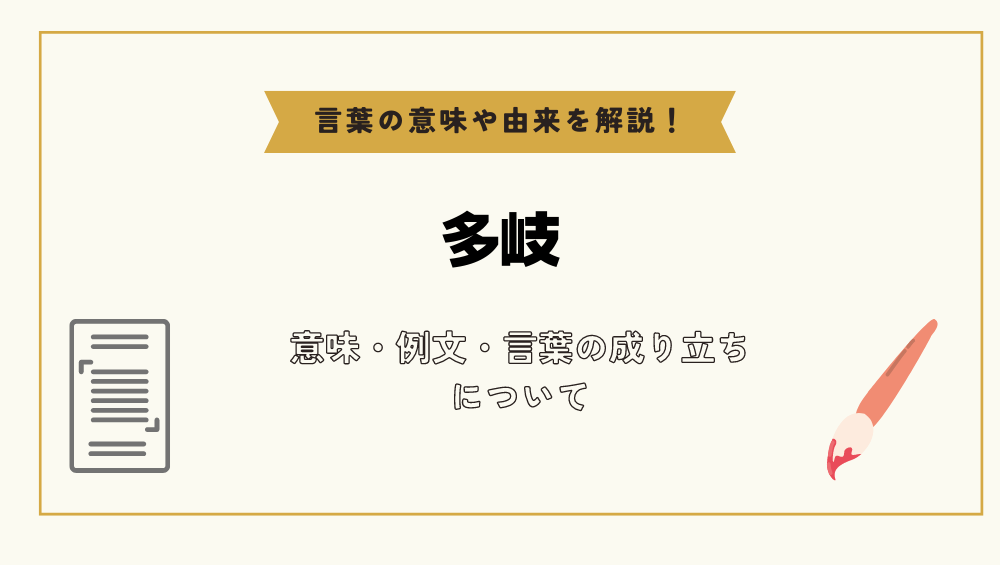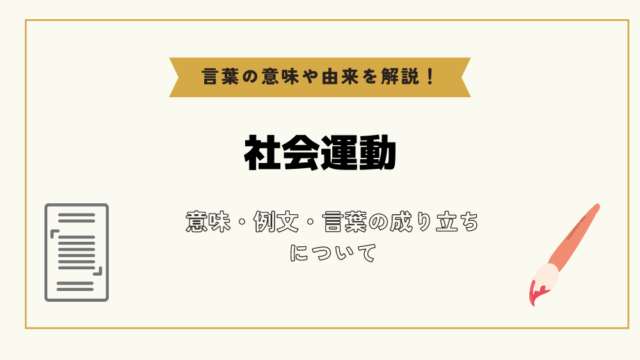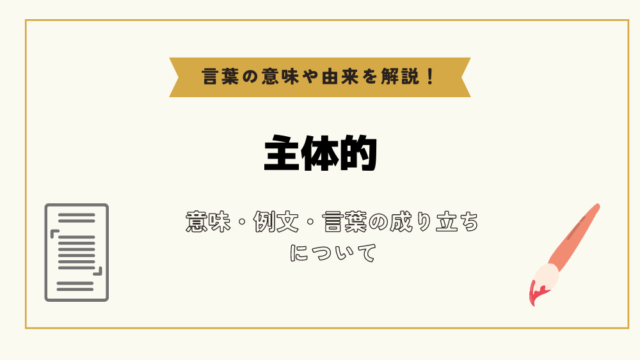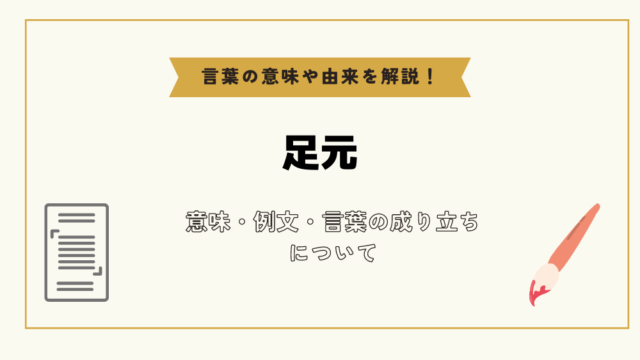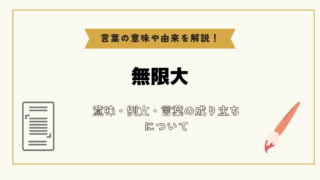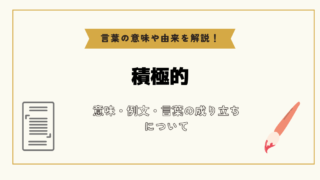「多岐」という言葉の意味を解説!
「多岐(たき)」とは、物事や話題が一つの流れから枝分かれし、いくつもの方向へ広がっている状態を指す言葉です。日常では「多岐にわたる」「多岐に及ぶ」という形で用いられ、範囲が広大であることを強調します。\n\n端的にいえば「多岐」は“さまざまな方向へ分かれている”ことを示す日本語です。ビジネスの会議資料で「検討事項が多岐にわたる」と書けば、課題が分野横断的であると伝えられます。\n\n語義のニュアンスは「数が多い」だけでなく「分散している」点にあります。したがって項目数が多くても一列に並ぶだけでは「多岐」とは呼びません。\n\n古典文学から行政文書まで幅広く使われるため、堅い文章にも柔らかい文章にも順応できる便利な表現です。\n\nビジネス・学術・日常会話のいずれでも違和感なく使える汎用性の高さが、「多岐」という語の大きな特徴です。\n\n【例文1】今回のプロジェクトは担当分野が多岐にわたる\n\n【例文2】彼の興味は歴史から科学まで多岐に及ぶ\n\n。
「多岐」の読み方はなんと読む?
「多岐」は常用漢字表に掲載されており、音読みで「たき」と読みます。訓読みはほとんど存在せず、辞書でも専ら音読みが示されています。\n\n誤って「おおまた」や「たぎ」と読まれることがありますが、正式には“たき”と覚えましょう。新聞や書籍ではルビを振らない場合が多いため、読み誤りを防ぐには慣れが必要です。\n\n二文字とも小学4年生レベルの漢字でありながら、組み合わせ語としては中学以降に学習するケースが大半です。意外と口語より書き言葉で目にする機会が多いため、読みに迷いやすい言葉といえます。\n\nまた「岐」は「分かれる」を意味する部首「山偏の支」で、音読みは「キ」です。「多」は「数が多い」ことを示すため、両者が合わさることで語感のイメージもつかみやすくなります。\n\n読み方を確実に覚えるコツは「多岐にわたる」をセットで暗記することです。\n\n【例文1】この議題は多岐にわたるため、順番に整理しましょう\n\n。
「多岐」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方の基本形は「多岐にわたる」「多岐に及ぶ」という連語です。文中の主語はテーマや項目など広がりを示す名詞が好相性です。\n\n「多岐」を単独名詞として使うことはまれで、ほとんどが複合動詞・複合述語の一部として登場します。文章を引き締めつつ情報の幅広さを示せるため、報告書や研究要旨で頻繁に用いられます。\n\n誤用として多いのは「多岐が広い」「多岐が多い」といった表現です。そもそも「多岐」自体に広さや多さが含まれるため重複表現になります。\n\n以下に実際の使用例を挙げます。\n\n【例文1】当社のサービスは医療・教育・観光と多岐にわたり、地域社会に貢献しています\n\n【例文2】研究対象が多岐に及ぶため、分科ごとに専門家を配置した\n\n【例文3】多岐にわたる情報を俯瞰し、優先順位を定めることが要となる\n\n【例文4】多岐にわたる趣味を持つことで、新しい人間関係が広がった\n\nポイントは「範囲」や「領域」の幅広さを明示した後に「多岐」を置くと、文章が自然になることです。\n\n。
「多岐」という言葉の成り立ちや由来について解説
「多岐」は中国古典に源流を持つとされ、『礼記』や『荘子』の中で「多くの岐路」という意味合いで登場します。日本には奈良時代に漢文と共に伝来し、平安期の文献では既に確認できます。\n\n語源的には「多」が“たくさん”、“岐”が“分かれ道”を示し、合わせて“分かれ道の多い場所”を象徴しました。古代中国の交通や軍事で岐路の多さが戦略上重要だったことに由来する説もあります。\n\n和語には同義語がなかったため、そのまま音読み熟語として定着しました。日本語の感覚では「枝分かれ」や「雑多」と似た意味を補完する語が必要だったため、平安貴族の漢詩文に重宝されたと考えられます。\n\n江戸時代の戯作や蘭学書にも散見され、特に儒学者の注釈書では研究分野の広さを示す定型表現として用いられました。\n\nこうした経緯から「多岐」は“知の広がり”を示す言葉として、学問分野で長く愛用されてきたのです。\n\n。
「多岐」という言葉の歴史
古代中国の辞書『説文解字』には「岐」を「分かれ道」と定義する記述があります。そこに「多」を冠した熟語「多岐」は戦国〜前漢期の竹簡に見いだされ、思想家たちが多面的な議論を語る際に使用しました。\n\n日本では『日本書紀』や『続日本紀』の漢文訓読文中には現れませんが、平安時代の学者が漢詩を収めた『和漢朗詠集』で確認できます。その後、室町期の漢学隆盛により民衆の学問熱が高まると、読み下し文にも広まりました。\n\n明治以降、西洋学術の翻訳が進むなかで「多岐」は「diverse」「various」「multifaceted」などの語の置き換えとして再評価されました。新聞記事や官報に登場する頻度が大幅に増えたのもこの時期です。\n\n戦後は高度経済成長とともに情報量が爆発的に増え、行政文書や学術論文で「多岐にわたる」という表現が標準句となりました。現代ではインターネットで検索すれば数百万件ヒットするほど一般化しています。\n\nこのように「多岐」は時代の知識・情報の増大と歩調を合わせながら、使用領域を拡大してきた歴史を持ちます。\n\n。
「多岐」の類語・同義語・言い換え表現
「多岐」に近い意味を持つ日本語には「多方面」「多様」「多角的」「多種多様」「多元的」などがあります。\n\n言い換える際は「分散」のニュアンスが必要か「種類の豊富さ」を重視するかで語を選ぶと効果的です。たとえば「多角的視点」は視点の角度が多いことを示し、「多方面の知識」は領域の広さを表します。\n\nそれぞれの語感を比較すると、「多元的」は要素が独立して存在するイメージが強く、「多様」は単純に種類が多いことを示します。「多岐」はそれらの両方を内包しつつ枝分かれという比喩性を持つ点が特徴です。\n\n【例文1】課題を多角的に検証する\n\n【例文2】多方面の分野で活躍する研究者\n\n【例文3】社会問題は多元的な視点で分析すべきだ\n\n文章のトーンに合わせて「多岐」を他の語と置き換えれば、表現の幅が広がります。\n\n。
「多岐」の対義語・反対語
「多岐」の対義語として最も適切なのは「一途(いちず)」や「一筋(ひとすじ)」です。どちらも方向が一つに定まることを示し、「枝分かれ」とは正反対のイメージを与えます。\n\n文章上でコントラストをつけたい場合、「多岐にわたる」⇔「一途に向かう」という対比が効果的です。概念的には「単一」「一本道」「集中」なども反意表現として用いられます。\n\n使用例を示します。\n\n【例文1】多岐にわたる議論の末、最終的には一途な結論に至った\n\n【例文2】彼は多岐に興味を持つ弟とは対照的に、一筋に音楽だけを追求した\n\n反対語を理解することで「多岐」が持つ分散・多面的という特性をより鮮明に把握できます。\n\n文章表現では「多岐」を使いすぎると散漫になるため、対義語を織り交ぜて流れを締める工夫が有効です。\n\n。
「多岐」を日常生活で活用する方法
日常会話では「興味が多岐にわたるね」と褒め言葉として使えます。相手の幅広い趣味や知識を尊重するニュアンスが伝わります。\n\n家計や時間の管理でも「多岐にわたる支出をカテゴリ別に整理する」と応用すれば、可視化と優先順位づけに役立ちます。また、読書記録や学習計画を立てる際に「テーマが多岐にわたるため月ごとに集中領域を決める」と書き込むと整理効果が高まります。\n\nビジネスでは週報・月報で「リスク要因が多岐に及ぶ」と述べたうえで、リスクマトリクスを提示すると説得力が増します。プレゼン資料の冒頭で使えば、聴衆に全体像の複雑さを予告できます。\n\n【例文1】今年は多岐にわたる目標を掲げず、優先事項を三つに絞ろう\n\n【例文2】多岐にわたるタスクを一元管理できるアプリを導入した\n\n使いどころの鍵は「幅の広さ」を示したあとに整理策や重点化策を続けることです。\n\n。
「多岐」についてよくある誤解と正しい理解
「多岐=大量」と誤解されがちですが、量が多くても一本線上に並んでいるだけなら「多岐」とは呼びません。分岐・散在が欠かせない要素です。\n\nもう一つの誤解は「難しい言葉なので日常会話では不自然」というものですが、実際にはシンプルな音読みで耳障りが柔らかく、会話に溶け込みやすい語です。\n\nまた「多岐に渡る」と「渡る」を「わたる」と漢字表記する誤用が見られます。正しくは「わたる」で平仮名表記が慣例化しており、公用文でも平仮名が推奨されています。\n\n【例文1】× 多岐に渡る課題 → ○ 多岐にわたる課題\n\n【例文2】× 興味が多岐だ → ○ 興味が多岐にわたる\n\n誤用に気づいたら早めに修正することで、文章全体の信頼性が向上します。\n\nポイントは「多岐」と「わたる」をセットにし、平仮名表記を守ることです。\n\n。
「多岐」という言葉についてまとめ
- 「多岐」は物事が枝分かれして多方向に広がる状態を示す熟語です。
- 読みは「たき」で、表記は「多岐にわたる」とセットで使うと覚えやすいです。
- 古代中国由来で、日本では平安期から知識の広がりを表す語として定着しました。
- 現代ではビジネス・学術・日常会話を問わず使われるが、「わたる」は平仮名にする点に注意が必要です。
ここまで見てきたように「多岐」は単に数が多いことではなく、複数の方向へ分かれている状態を強調する語です。読み方や成り立ちを押さえておけば、文章だけでなく会話でも自然に使いこなせます。\n\n類語・対義語を理解し、誤用を避けながら適切な位置に配置することで、情報の広がりや複雑性をスマートに表現できます。多面的な社会で生きる私たちにとって、「多岐」はまさに言葉の万能ツールといえるでしょう。