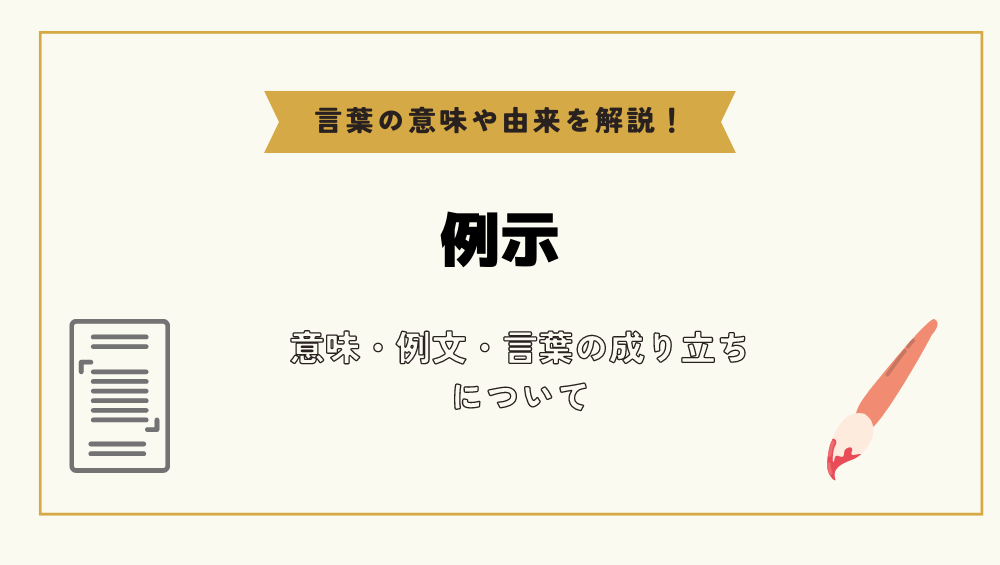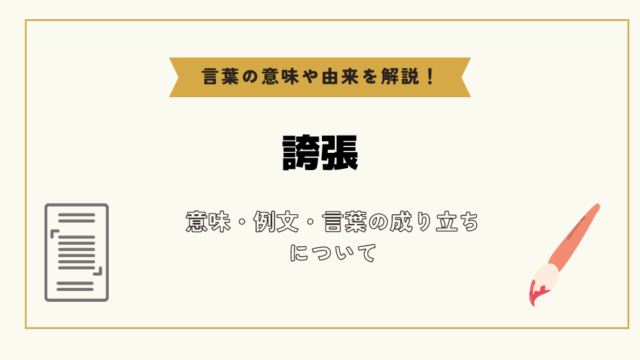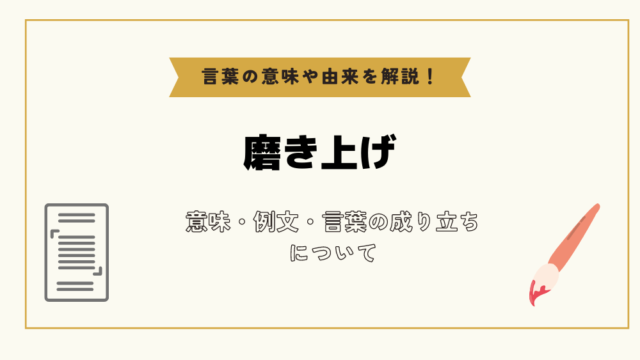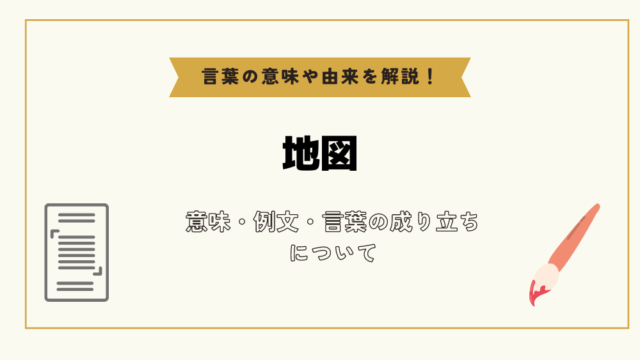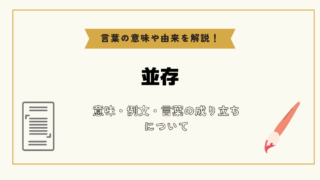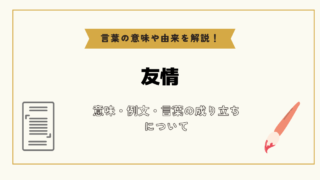「例示」という言葉の意味を解説!
「例示」とは、ある概念や主張を分かりやすくするために具体的な事例を挙げて示すことを意味します。言葉や文章で抽象的な内容を語る際、そのままではイメージしにくい場合があります。そこで代表的なケースや身近な出来事を挙げることで、読み手や聞き手が理解しやすくなる仕組みが「例示」です。例示はプレゼンテーションや授業、報道などあらゆる場面で活躍し、情報伝達の質を高めます。
例示の目的は二つあります。一つは内容を具体化し、誤解を防ぐこと。もう一つは共感や納得を引き出し、説得力を強化することです。「これが典型的な例です」と示されると、抽象論だけではぼんやりとしていた輪郭がはっきり見えてきます。母語話者の直感にも合致するため、記憶への定着を助ける効果も期待できます。\\n。
要するに、例示は「分かりやすさ」と「説得力」を支える実務的なテクニックであると言えます。人間は具体例を通して情報を整理する傾向があるため、例示を上手に盛り込むことでコミュニケーション全体が円滑になります。\\n。
「例示」の読み方はなんと読む?
「例示」の読み方は「れいじ」です。漢字の読み分けとして、「例」は“れい”と読む常用的読み方で、「示」は訓読みだと“しめす”ですが、この語では音読みで“じ”と読まれます。よって二文字合わせて四音、「レイジ」と発音します。
アクセントは平板型が一般的で、語尾を上げ下げしない滑らかな発音が標準語では自然です。一方、地域によっては「レ↗イジ↘」のようにやや抑揚を付けるケースも見られますが、共通語としては平板で問題ありません。
ビジネスの場でも雑談でも、「例示します」「一例を示します」のように動詞化して使われることが多いです。「れいし」や「れいひょう」と読み間違えないよう注意しましょう。\\n。
「例示」という言葉の使い方や例文を解説!
例示は名詞・動詞句の両面で使えます。文中では「~を例示する」「~として例示できる」のように他動詞的に用いる形が一般的です。抽象概念の説明、統計データの補足、法律条文の具体化など幅広い目的にフィットします。
論文や報告書では、例示によって前提を明確化し、読み手の誤解を抑制します。同じ文章量でも例示の有無で理解速度が大きく変わるため、情報を正確に届けたい場面ほど重要度が高まります。
【例文1】新制度の効果を例示するため、導入企業A社の売上推移を提示します。
【例文2】「過失」の範囲を例示すると、自動車のブレーキ整備を怠ったケースが典型です\\n。
例示と混同されやすい言葉に「列挙」「具体化」がありますが、列挙は単に複数項目を並べる行為であり、例示のように代表例を選んで示すニュアンスとは異なります。また具体化は抽象→具体という広い概念変換を指すため、例示はその一手法と捉えると整理しやすいです。\\n。
「例示」という言葉の成り立ちや由来について解説
「例」は“手本”や“前例”を指し、「示」は“見せる”や“示す”を表します。古代中国の漢籍では「示」は神意を天意として表す語でしたが、後に「見せる」意味へ拡大しました。この二文字を組み合わせた「例示」は、前例を示し理解を助けるという概念が凝縮されています。
日本語としての定着は明治初期、西洋法律書や学術書を翻訳する際に作られた言葉群の一つと考えられています。翻訳家たちはラテン語 exemplum や英語 example の訳語を模索し、「例示」を術語として採用しました。特に法学・教育学の文脈で早期から使われたため、専門家を介して一般社会へ広がりました。
この過程で「例解」「例証」など近縁語も生まれましたが、使われる領域によって徐々に意味が分化しました。「例示」が抽象的説明の補助を意味する一方、「例証」は証拠性を重視する点が違いです。\\n。
「例示」という言葉の歴史
古典文学には「例示」という表記はほぼ登場しません。漢文訓読や和歌の世界では、個別具体の描写で代用していたためです。しかし明治期以降、近代学問の流入と共に論理的説明を求められる機会が増え、「例示」という概念語が必要とされました。
明治23年公布の旧民法草案注釈書には既に「例示的に列挙する」という表現が確認でき、法令分野で早くから定着していたことが分かります。大正期に入ると教育現場で「例示教授法」が研究され、児童に具体例を示して理解を深める指導法として注目されました。
戦後はマスメディアの発展により、新聞やテレビ番組が統計グラフとともに具体事例を示すスタイルを採用し、一般層にも浸透します。21世紀に入ってからはインターネット上の解説記事や動画教材で頻繁に見られ、検索キーワードとしての需要も高まっています。\\n。
「例示」の類語・同義語・言い換え表現
「例示」の近い意味を持つ語として「例証」「具体例」「事例提示」「サンプル提示」「実例紹介」などが挙げられます。微妙にニュアンスが異なるため、文脈に合わせて使い分けると表現の幅が広がります。
たとえば論文では説得力を伴う証拠性を示すため「例証」が好まれ、商品紹介の場面では親しみやすさを前面に出す「実例紹介」が向いています。また英語に置き換えるなら example、illustration、instance などが機能的に相当しますが、日本語の語感とは完全に一致しないため注意が必要です。
さらに「列挙」「提示」「具体化」は部分的に重なりますが、列挙は数量の多さ、提示は示す行為そのもの、具体化は抽象→具体の変換を主眼に置いており、焦点が異なると覚えておくと便利です。\\n。
「例示」を日常生活で活用する方法
日常会話でも例示を意識的に取り入れると、伝えたい内容をスムーズに共有できます。たとえば「最近のスマホは高いね」と言うだけでは漠然としていますが、「最新モデルだと10万円以上するよ」と例示すると、価格帯が具体的に伝わります。
プレゼン資料ではスライド一枚につき一つの例示を入れるだけで、聴衆の記憶定着率が向上するという調査結果もあります。家族との会話でも「健康にいい食生活」と言う代わりに「例えば野菜中心で、朝にトマトジュースを飲む」と示せば具体像が浮かびます。
読書や勉強の際には、抽象的な概念が出てきたら自分で例示を考えてみるのがおすすめです。これにより理解が深まり、説明する場面でもスムーズにアウトプットできます。\\n。
「例示」についてよくある誤解と正しい理解
「例示=全てのケースを網羅している」という誤解が見られます。例示はあくまで代表的なサンプルを挙げているに過ぎず、絶対的な範囲指定ではありません。法律条文などでも「その他これに類するものを含む」と補足されることが多いのは、その性質に由来します。
もう一つの誤解は、例示を多用すれば説得力が無限に高まるというものですが、過剰な例示はかえって論旨を散漫にします。重要なのは目的に合った数と質を選ぶことです。論点が一つならば一例で十分に伝わる場合もあります。
また「例示=列挙」と短絡的に捉えると、必要以上の情報を詰め込みがちです。列挙は情報の広がり、例示は理解の深さを狙うと覚えておくとバランスよく使えます。\\n。
「例示」という言葉についてまとめ
- 「例示」は概念を具体的な事例で示し、理解と説得力を高める手法を指す言葉。
- 読み方は「れいじ」で、平板型の発音が標準とされる。
- 明治期の翻訳語として誕生し、法学や教育分野から一般に広がった歴史を持つ。
- 代表例を示すだけで全体を網羅しない点に注意し、目的に応じて適量を活用することが大切。
例示は抽象概念を生き生きとした情報に変換し、相手の腑に落ちる瞬間を生み出す力強いツールです。読み方や成り立ちを知れば誤用を防ぎ、歴史を学べばその意義が一層鮮明になります。\\n。
日常会話から専門的なレポートまで、例示はあらゆる場面で頼れる相棒です。ただし例が多過ぎると本筋がぼやけるため、代表的でインパクトのある事例を厳選しましょう。例示を上手に操り、伝えたいことをよりクリアに届けてください。