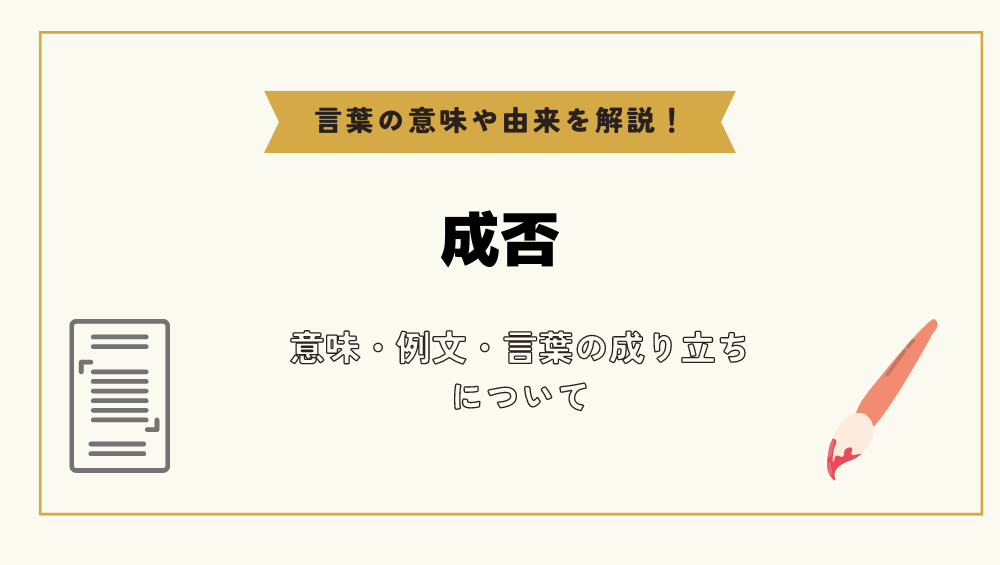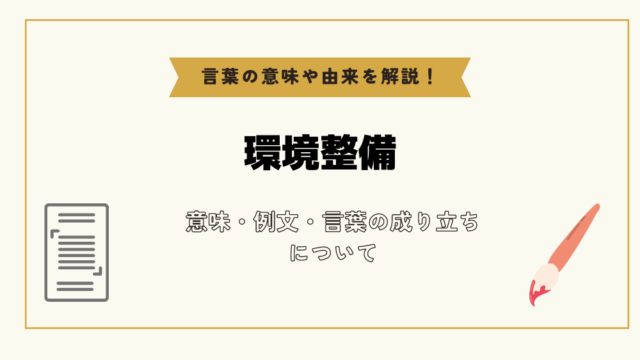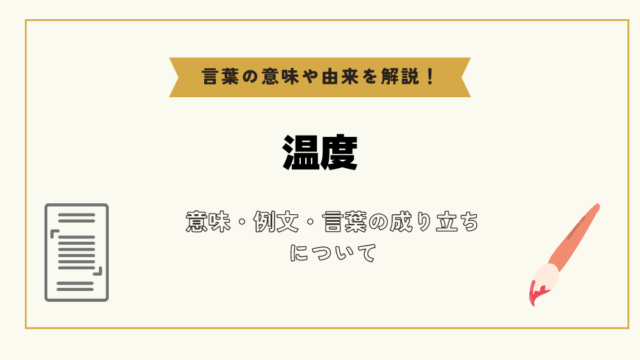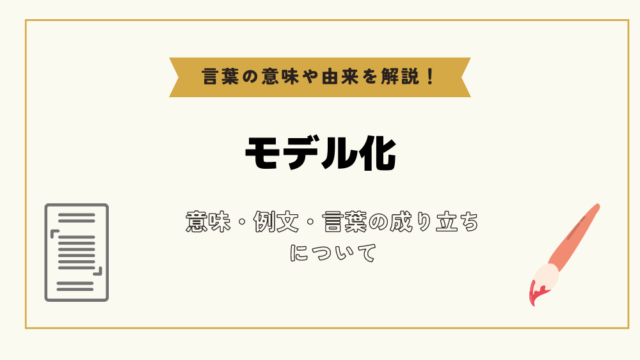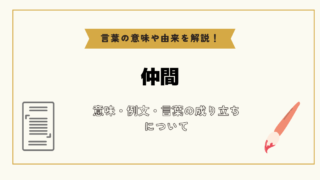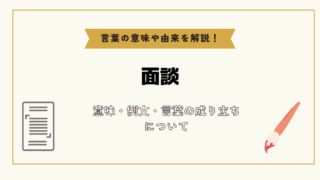「成否」という言葉の意味を解説!
「成否」とは、物事が成功するか失敗するかという結果の二極を示す名詞です。この言葉は単に「うまくいったかどうか」を評価するだけでなく、計画・方針・判断など一連のプロセス全体を含む結果の総括を指します。したがって、数字や成果が明確に出るビジネス現場だけでなく、日常会話でも使われやすい便利な語です。
多くの場合、「企画の成否」「手術の成否」というように、具体的な対象と結び付けて用います。ここでの「成」は成功・成立、「否」は失敗・不成立という意味をそれぞれ担っており、二つを対置させて一語化している点が特徴です。
判断がつかない場合は「成否を見極める」「成否が不明」といった形で、結果が確定していない過程を示すこともできます。これにより、進行中の案件や研究など状況が流動的な事柄に対しても柔軟に用いられます。
また、日本語では珍しく、肯定と否定を同時に示す造語であるため、両極端な結果を含んだ中立的なニュアンスをもつ点も押さえておきましょう。
「成否」の読み方はなんと読む?
「成否」の読み方は「せいひ」です。「成」は音読みで「セイ」または「ジョウ」、「否」は音読みで「ヒ」と読みますが、この語では両方とも音読みを採用し「せいひ」と続けて発音します。
日常会話では「せいひ」とはっきり二拍で区切ると発音が硬く聞こえるため、実際には「セイヒィ」のように軽くつながります。ビジネスシーンで文書を読み上げる場合でも「成否(せいひ)」とフリガナを添えると誤読を防げて便利です。
誤って「しょうひ」や「じょうひ」と読まれることがあるため、会議や発表の場では先に読みを提示するのが無難です。こうした注意を怠ると、専門性を問われる場面で齟齬が生じるため気をつけましょう。
「成否」という言葉の使い方や例文を解説!
実際の会話や文章での使用方法を確認すると、語感が把握しやすくなります。ここでは典型的な用例を示し、ニュアンスの違いにも触れていきます。
ポイントは「結果」だけでなく「結果がまだ出ていない状態」を示す場面でも活躍することです。
【例文1】この提案の成否は、消費者がどう受け取るかにかかっている。
【例文2】ワクチン開発の成否が、世界経済の行方を左右する。
上記のように、主語になる対象と「~の成否」という所有格の形で結び付けるのが一般的です。また、「成否を分ける要因」「成否に影響を与える」といった形で結果を左右する条件を述べる場合にも多用されます。
判断が遅れる場面では「成否を見極める」「成否を判断する」と動詞とセットで用い、過程を強調します。これにより、現在は不確定であることを読み手に伝えられます。
「成否」という言葉の成り立ちや由来について解説
「成否」は「成る(なる)」と「否(いな)」という漢語由来の語根を組み合わせた複合語です。「成」は中国古典で「完成・成立」を意味し、「否」は「否定・拒絶」を意味します。
古代中国語では「成敗」や「可否」といった対語が多く見られ、日本語もその構造を踏襲して「成否」という語を生み出しました。もともと「成否」は漢籍の中で「物事の成功と失敗」を並べて論じる際に現れ、日本に輸入される過程で音読みが定着します。
中世の文献ではまだ「成否」はまれで、「成敗」や「可否」の方が一般的でした。近世になると学問・医学・商業の発展とともに「成功/失敗」を一語で表したい需要が高まり、行政文書や商取引書面で「成否」が使われ始めます。
日本国内で完全に一般語化したのは明治以降で、公的文書や新聞記事に頻出するようになったことで広く定着しました。こうして、現代ではビジネス・学術・日常会話へと用途が拡大しています。
「成否」という言葉の歴史
「成否」の歴史をたどると、まず中国唐代の法律文書に同形の語が記録されています。当時は科挙試験の合否を示す語としても使われており、合格・不合格を端的に表す便利な術語でした。
日本での最古の確認例は江戸前期の儒学者の著書で、国政における政策の「成否」を論じています。このころは学者や武士階級の筆談に限られていましたが、幕末には商人の往来文書にも登場し始め、経済活動の成績評価に活用されました。
明治政府の近代化政策により、西洋の「success or failure」という概念を翻訳する際、「成否」という語が公式に採用されたことで急速に普及しました。新聞・雑誌が一般家庭へ浸透する過程で日常語化し、戦後の高度成長期には企業の経営判断を表現するキーワードとして欠かせない存在となります。
現在はIT業界や医療分野など、専門領域でもそのまま使用されるほど汎用性が高く、歴史的な重みと現代的な実用性を兼ね備えた語となっています。
「成否」の類語・同義語・言い換え表現
「成否」と同じように結果の良し悪しを示す語として、「成敗」「可否」「合否」「功罪」などがあります。それぞれ微妙にニュアンスが異なるため、シーンに応じた使い分けが重要です。
たとえば「合否」は試験や審査など合格・不合格が明確な場面で使われ、「可否」は計画を実行するか否かという可決・否決に焦点を当てます。「功罪」は功績と罪過の両面を評価する言葉で、対象が人物や制度の場合に向いています。
【例文1】新製品の発表は市場調査の可否を確認してから決めよう。
【例文2】改革の功罪を検証し、次のステップを議論する。
「結果」という語で置き換え可能な場合もありますが、「成否」のように成功・失敗の対立を前提としないため、慎重に選択しましょう。
言い換えの際は、評価基準が定量的か定性的か、また判定が二者択一か連続的かを見極めることがコツです。
「成否」の対義語・反対語
「成否」自体が成功と失敗の両極を包含する語なので、完全な対義語は存在しません。しかし、あえて対立概念を探すなら「途中経過」や「未定」といった結果に至っていない状態を示す表現が該当します。
具体的には「検討中」「試行段階」「進捗」といった語が、成否が定まる前のフェーズを指すため、用途によっては機能的な反意表現となります。
【例文1】この案件はまだ途中経過であり、成否は決まっていない。
【例文2】進捗を共有したが、成否については次回会議で判断する。
「成功」単独の対義語は「失敗」ですが、「成否」は両方を含むため、文脈に応じて言い換えず、そのまま用いるほうが理解がスムーズな場合が多いです。
反対語探しにこだわるよりも、「成否が未確定」である事実を丁寧に伝える方が実務的には有益です。
「成否」を日常生活で活用する方法
ビジネス文書以外でも、「成否」という語を使うと説明が簡潔になり、会話が引き締まります。たとえば家庭内のイベントや趣味の計画にも応用可能です。
【例文1】ダイエットの成否は食事管理にかかっている。
【例文2】家庭菜園の成否を分けるのは水やりのタイミングだ。
ポイントは「◯◯の成否は△△に左右される」という形を覚えることです。これで原因と結果をセットで伝えられるため、聞き手がイメージしやすくなります。また、報告書や日記に書く際、冗長な説明を避けられるのも利点です。
ただし、結果が確定していない場面で多用すると、責任を曖昧にする印象を与える恐れがあるので注意しましょう。「責任の所在を明確にする」ために、誰が判断を下すのかを添えるなど、補足表現を足すと丁寧です。
「成否」についてよくある誤解と正しい理解
「成否=成功」と誤解している人が少なからずいますが、実際は成功と失敗の両方を含む言葉です。失敗の可能性を無視したポジティブなニュアンスだけで取られると、議論に齟齬が生まれます。
もう一つの誤解は「成否=合否」で、試験の合格・不合格に限定されると思われがちですが、対象は企画・交渉・手術など多岐にわたります。
【例文1】この薬の効果の成否がわからない(誤:効果がある前提で使うのは不適切)
【例文2】実験の成否は条件設定に左右される(正:成功するか失敗するかどちらも視野に入れている)
「成否」を用いるときは、必ず二つの結果が想定されていることを示し、どちらか一方の結果のみを暗示しない言い回しを心がけましょう。これにより、コミュニケーションの齟齬を回避できます。
「成否」という言葉についてまとめ
- 「成否」とは成功と失敗のいずれかという結果全体を示す語である。
- 読み方は「せいひ」で、音読みを連続させるのが正しい。
- 漢籍由来で明治期に一般語化し、ビジネスや日常へ普及した。
- 使用時は二つの結果を同時に想定し、未確定の過程にも用いられる点に注意する。
「成否」は成功か失敗かという二極の結果をまとめて示す便利な語で、企画・研究・日常の計画など幅広い場面で活用できます。読み方は「せいひ」と覚えておき、誤読や「成功=成否」の勘違いを避けましょう。
歴史的には中国古典に端を発し、明治期に日本で定着しました。現在ではビジネスレポートから家族のイベントまで幅広く使われ、「◯◯の成否を分ける」という定型句が定着しています。
使う際は、結果が両方あり得る状況であることを意識し、責任の所在や判断基準を補足すると、より誤解のないコミュニケーションが実現します。今後も言葉の機能を理解し、的確な表現として「成否」を使いこなしてみてください。