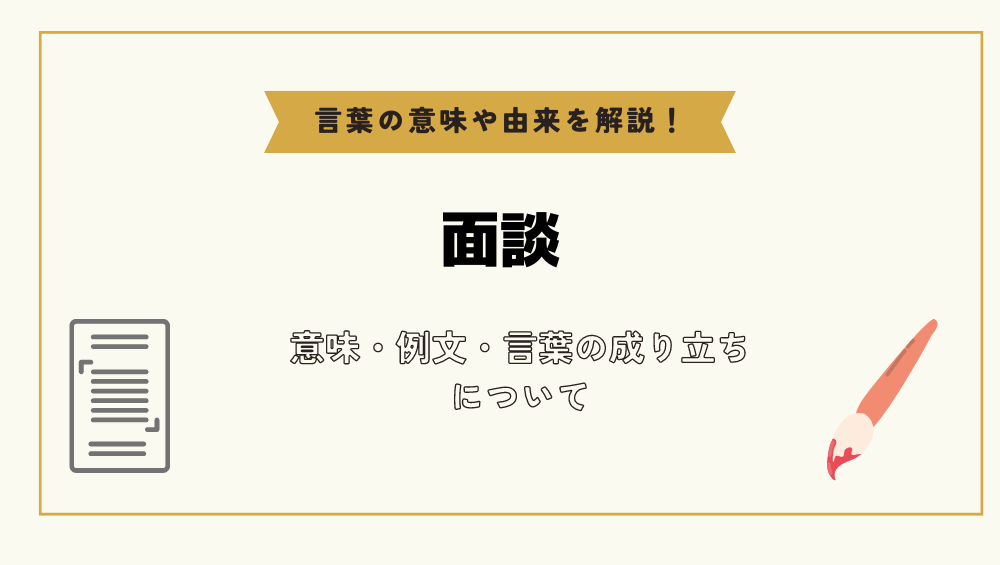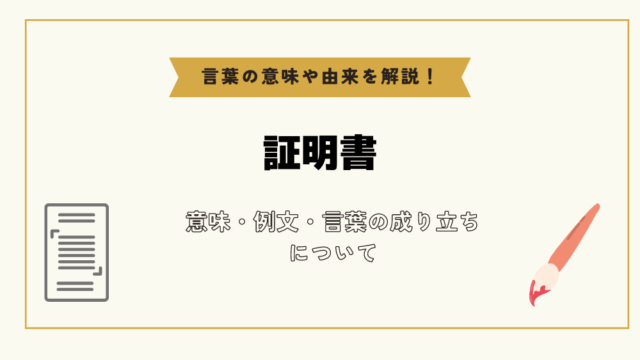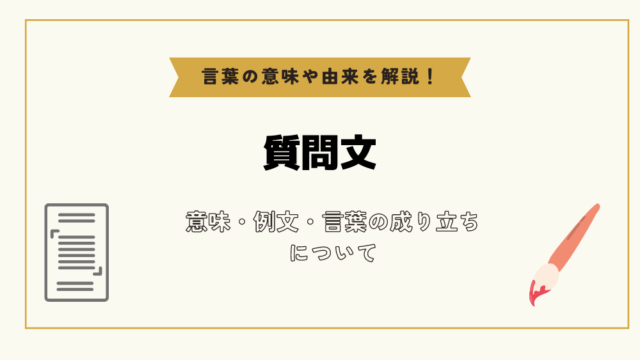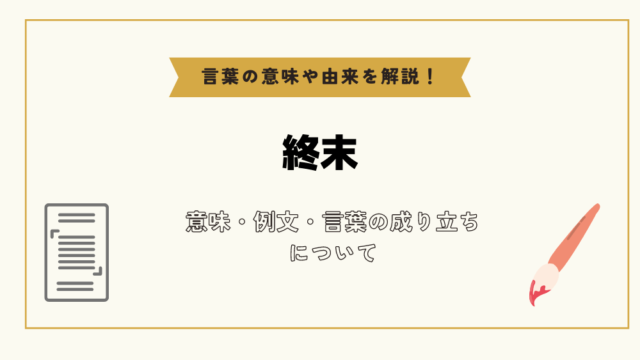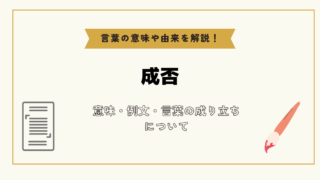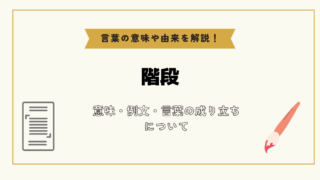「面談」という言葉の意味を解説!
「面談」とは、二人以上の当事者が対面し、相手の表情や声色を確かめながら情報交換や意思確認を行うコミュニケーション行為を指します。
最も一般的には、上司と部下、教員と学生、採用担当者と応募者など、一方が評価・助言を行い、もう一方が説明・相談を行う場面で用いられます。
電話やメールでは捉えきれないニュアンスを汲み取れることが大きな特徴です。
面談は「議論」よりも柔らかな響きがあり、「相談」よりも形式的な場面で使われる傾向があります。
対等な立場で話し合う場合もありますが、組織内では評価や査定を伴うことが多く、準備不足が不利に働くこともあります。
だからこそ面談は、事前目的の共有と、双方が納得できるゴール設定が欠かせないのです。
また、面談は「対面」を前提とする言葉ですが、オンライン会議システムが普及した現代では、画面越しであっても「顔を合わせる」ことが担保されれば面談と呼ばれるケースが増えています。
この意味変化は、言葉が時代の技術や社会背景によって拡張される好例といえるでしょう。
最後に、面談は「聞くこと」と「語ること」が半々になる場が理想です。
一方的に話す、あるいは黙り込む状態は面談の価値を著しく下げるため、意識的に質問と応答を交互に繰り返す姿勢が望まれます。
「面談」の読み方はなんと読む?
「面談」は音読みで「めんだん」と読みます。
漢字「面」は「顔」「つら」を意味し、「談」は「はなす」「ことばを交わす」を意味します。
そのため“顔を合わせて話し合う”という字面通りの意味合いをもつ言葉です。
混同されやすい読み方に「めんたん」や「めんさつ」がありますが、いずれも誤読です。
特に「面接(めんせつ)」と混同すると印象が変わるため、ビジネスシーンでは注意が必要です。
アナウンスや議事録で読みを誤ると、フォーマルな場ほど信頼性に影響しますので、音読確認を習慣化してください。
さらに、音読時のアクセントは「メ↘ンダン」とやや前半で下がるのが標準的です。
地域によっては平板に読む例もありますが、共通語ではこの抑揚が用いられます。
「面談」という言葉の使い方や例文を解説!
面談はフォーマルとインフォーマルの中間に位置する語感をもち、ビジネス・教育・医療など幅広い分野で活躍します。
口語だけでなく文書でも自然に置き換え可能な汎用性がある点が魅力です。
以下に典型的な使い方を示します。
【例文1】来週、上司との人事評価面談が予定されています。
【例文2】担当医と治療方針について面談したいと申し出た。
【例文3】進路指導の面談で、大学受験の希望を伝えた。
【例文4】採用面談では会社のビジョンについて逆質問ができた。
例文から分かるように、「面談後」「面談時」「面談資料」など名詞修飾での活用が多く、動詞化せずとも文章が成立します。
動詞形を選ぶ場合は「面談する」「面談を行う」が一般的です。
「面談」という言葉の成り立ちや由来について解説
「面」は漢籍の『論語』や『孟子』などで「顔を合わせる」という意味で用いられ、日本にも奈良時代に伝来しました。
「談」は平安期に漢文訓読のなかで「ことばを交わす」語として定着し、江戸時代には「談義」「世間話」の語が広まりました。
この二字が複合して「面談」という語形が見られるのは明治中期の新聞記事が最古級の資料とされています。
西洋近代化の過程で「インタビュー」や「ディスカッション」など外来概念が入る中、日本語として対面相談を表すピンポイントな言葉として定着しました。
明治政府の官報や兵役法令にも登場し、公的手続き用語として一気に広がったことが確認できます。
「面談」という言葉の歴史
明治期は役所での取調べ・税務相談に「面談」という語が使用され、硬質な印象がありました。
大正から昭和初期にかけて人事考課制度が導入され、企業の定期面談が根づきます。
戦後の高度経済成長期には就職・転職活動の語として一般化し、1980年代には高校の三者面談という学習指導要領が制定されました。
2000年代以降、IT業界を中心に1on1ミーティングが普及し、面談は「よりフラットな対話」のイメージへと拡張しています。
オンライン化が進んでも「顔を映す」ことが必須条件として残り、言葉の核心は変わっていません。
「面談」の類語・同義語・言い換え表現
面談と近い意味をもつ語には「面接」「個別面談」「相談」「対話」「ヒアリング」「1on1」などがあります。
ただし「面接」は評価・選抜色が強く、面談よりも上下関係が明確化されやすい点が大きな違いです。
「相談」はプライベート寄りの柔らかい語感で、正式な報告や人事評価を伴わない場合に選ばれやすいです。
言い換える際は目的に合わせて選択すると誤解が減ります。
たとえば「上長とのキャリア面談」は「1on1ミーティング」に置き換えても意味が保たれ、「医師との治療面談」は「インフォームド・コンセント」とほぼ同義に扱われます。
「面談」を日常生活で活用する方法
ビジネスだけでなく、家族間や地域活動でも「面談」の考え方を活かすと対話の質が上がります。
ポイントは、目的を共有した上で時間を区切り、互いの話す・聞く割合を50:50に保つことです。
子育てでは「親子面談」と称して学習計画や進路希望を確認できます。
自治会やPTAでは「個別面談」で要望を聞き、合意形成を進める方法が有効です。
面談シートを作成して議事を残すと、次回に繋がる具体策を立てやすくなります。
「面談」についてよくある誤解と正しい理解
「面談=評価される場」という先入観を持つ人が多いですが、必ずしも査定目的とは限りません。
正しくは、面談は“双方の情報を持ち寄り、今後の行動を合意形成する場”であり、一方的評価は面接と呼ぶほうが適切です。
また「面談は雑談してはいけない」という誤解もあります。
アイスブレイクや雑談によって相互理解が深まると、本題の合意形成が円滑に進むことが多いです。
逆に雑談に終始して目的が達成できないと本末転倒なので、雑談の時間を最初と最後に限定するテクニックが推奨されます。
「面談」という言葉についてまとめ
- 「面談」は顔を合わせて情報交換・意思確認を行う対話を指す言葉。
- 読み方は「めんだん」で、誤読の「めんたん」や「めんさつ」に注意。
- 明治期の公的文書で定着し、対面相談の日本語表現として発展した。
- 現代ではオンラインを含むが「顔を合わせる」点と目的共有が必須条件。
面談という言葉は、「面=顔を合わせる」「談=言葉を交わす」というシンプルな構成が示す通り、古今東西で重視されてきた対話の基本形です。
歴史的には明治の官公庁で法令用語として採用された後、企業や教育機関を経て、現在では医療・行政・家庭へと活躍の場を広げています。
一方で「面接」「相談」と混同されることも多く、目的や立場の対等性によって適切な言葉を選ぶことが重要です。
オンライン化が進んでも“顔を見ながら話す”というコア概念は守られており、ツールよりも目的意識と信頼関係の構築が成果を左右します。
今後も技術の進化で形態は変わるでしょうが、面談が果たす「相手の表情を見ながら本音を確かめ、合意を得る」という役割は変わらないでしょう。