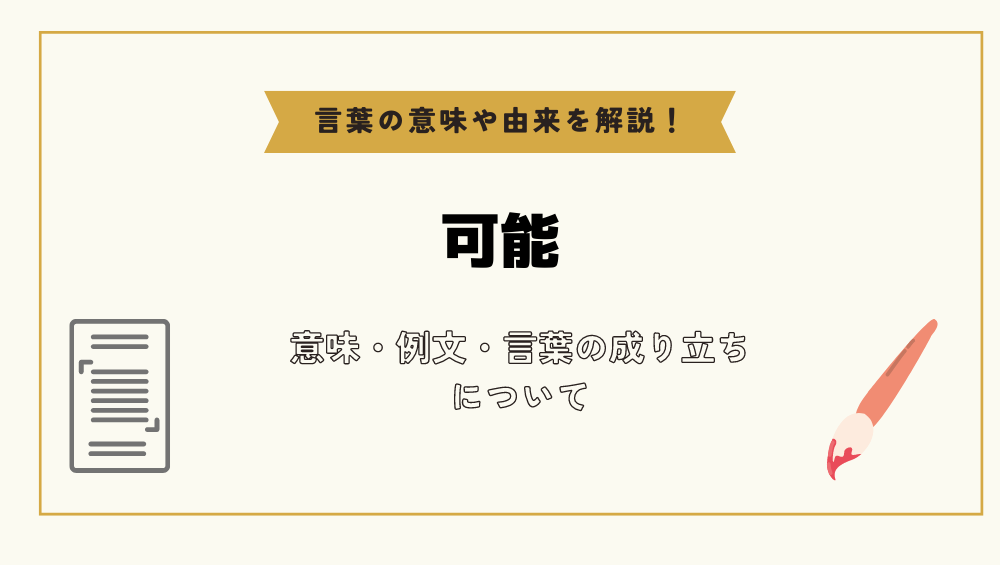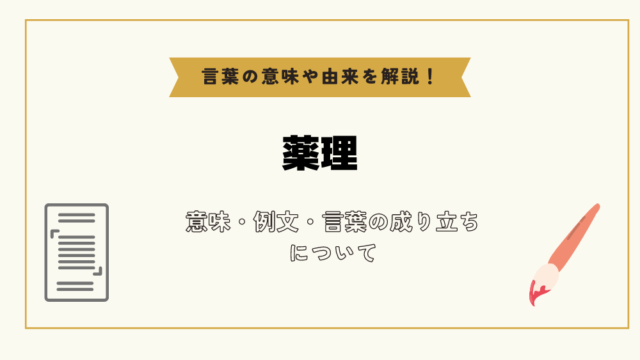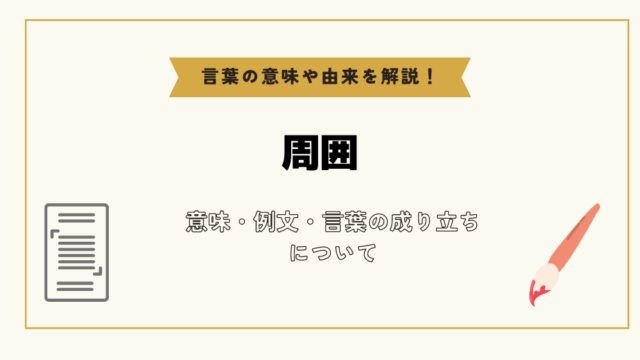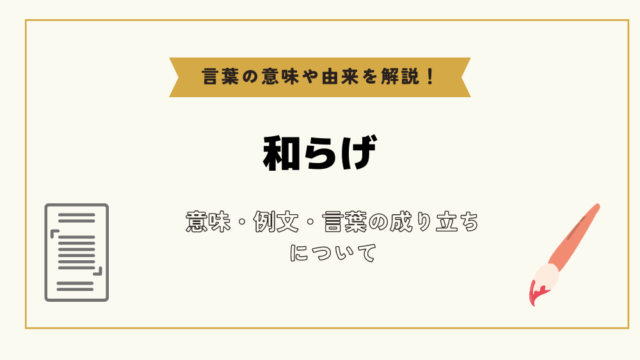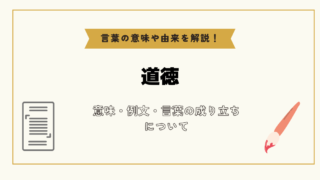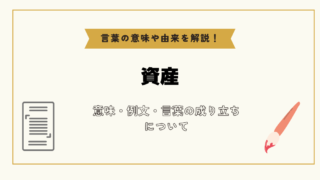「可能」という言葉の意味を解説!
「可能」とは「実現できる見込みがあること」「実行しうる状態にあること」を示す言葉です。この語が示すのは、現実に起こるかどうかよりも「起こり得る条件が整っているか」に重点があります。したがって、現行の状態を前提に「できるか」「できないか」を判断するときに便利な語です。
「可能」という語は抽象度が高いため、自然科学や法学、教育など幅広い場面で使われます。たとえば物理学では「実験的に可能」、法律では「法的に可能」など、後ろに分野名を付けることでニュアンスを限定できます。これにより誤解を減らし、具体的な可否を示すことができます。
同類語と混同されがちですが、「潜在的」「許容される」などとはニュアンスが異なります。「潜在的」は未だ顕在化していない力を意味し、「許容される」は外部からの承認を含みます。「可能」はあくまで条件が揃えば実施できるという自律的な可否を示します。
実用面では、「予定変更が可能」「支払いが可能」など具体的な条件とセットで用いると分かりやすいです。反対に「可能」とだけ言うと抽象度が高いため、相手に詳細を尋ねられる可能性があります。そこで時間や数量を補足すると、意思疎通が滑らかになります。
「可能」の読み方はなんと読む?
「可能」は一般的に「かのう」と読みます。音読みのみで構成され、訓読みは存在しません。両字とも常用漢字であり、学校教育では小学校で「可」、中学校で「能」を学習します。
「かのう」という読みは二音節で発音しやすく、ビジネスメールや公文書でも頻出します。ひらがな表記の「かのう」やカタカナ表記の「カノウ」は、デザイン上の視認性を高める目的で選択されることがあります。ただし公式文書では漢字表記が望ましいです。
さらに「可能性(かのうせい)」や「可能額(かのうがく)」など複合語でも読み方は変わりません。「可」は「許す」「よい」の意味を持ち、「能」は「よくする力」の意味を持つため、合わせて「できること」のニュアンスを形成します。
「可能」が名字や地名として使われることは稀ですが、発音上の誤読として「かの」や「かない」と読む例が国語辞典に指摘されています。ですが公的な標準読みは「かのう」ですので、公式な場では迷わず「かのう」と読みましょう。
「可能」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方の肝は「条件の提示」と「実行の見込み」を具体化することにあります。多くの場合、「~が可能だ」「~することが可能だ」の形で述語として機能し、動詞や名詞句を補います。
【例文1】現地に向かう前にオンライン打ち合わせを実施することが可能です。
【例文2】このアプリを使えば、複数通貨での支払いが可能になります。
上記のように主語を省略しても、「可能」という語が実行主体の能力を補うため、文意が通じます。反面、主語を明確にしないと責任の所在が曖昧になる場合があります。契約書など正式な文面では「当社は~が可能である」と主体を示すことが推奨されます。
「可能なら」「可能であれば」と仮定法的に用いると、柔らかな依頼表現になります。この方法はビジネスメールで多用され、相手の負担を考慮しつつ希望を伝えられるため便利です。たとえば「可能であれば来週中にご回答ください」のように活用できます。
一方で、「可能です」「不可能です」の二択だけで返答すると、具体的な障壁が不明瞭になりがちです。相手に改善策を提示するためにも、「現行プランでの実施は難しいですが、予算増であれば可能です」のように条件を添えましょう。
「可能」という言葉の成り立ちや由来について解説
「可能」は中国古典語の構成を踏襲し、「可」と「能」が組み合わさった合成語です。「可」は「認める・許す」の意を持ち、「能」は「技能・働き」を示します。この二文字が並ぶことで「許された働き=できること」という意味が自然に形成されました。
漢籍では『論語』や『孟子』に「可」「能」が独立して登場しますが、二字熟語としての「可能」は宋代以降の文献で確認されます。日本には奈良時代に漢籍が輸入された際、その語法が文人の間で取り入れられました。平安中期の漢詩集にも「可能」の用例が散見されます。
江戸時代には朱子学や蘭学の広がりによって、「可能」は学術用語として定着しました。蘭学者がオランダ語の “mogelijk” を訳す際にも「可能」が当てられ、意味の近い英単語 “possible” の訳語として明治期に一般化します。この頃には新聞や法令にも頻繁に登場しました。
近代以降は派生語として「可能性」「可能額」「可能力」などが生まれ、抽象概念の説明に欠かせない用語となります。特に科学技術の進展とともに「技術的に可能」「理論的に可能」といった言い回しが広まり、現代日本語に深く根付いています。
「可能」という言葉の歴史
日本語における「可能」は、学術輸入と近代化の流れの中で市民語へと転化しました。江戸後期の蘭学翻訳では“possible”の訳語として定着し、明治政府の法典編纂や教育制度で正式採用されます。
19世紀末の新聞では「開港が可能となりし」といった文語体で使用され、すぐに口語にも波及しました。大正期の文学では芥川龍之介が「可能な限り」という表現を用い、文学的ニュアンスを獲得します。昭和期の技術雑誌では「量産が可能」という工業用語として広まりました。
戦後の高度経済成長では「可能性調査」「実行可能性(フィージビリティ)」が行政文書で使用され、ビジネス用語へと発展します。1990年代にはIT業界が「リアルタイム更新が可能」と宣伝文句に取り込み、一般人にも馴染み深い語となりました。
21世紀に入ると、「サステナブルが可能か」「AIが可能にする未来」のように先端技術や社会課題と結びついて活用されています。現在ではあらゆる分野でポジティブな挑戦を促すキーワードとして浸透しています。
「可能」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「実現できる」「達成しうる」「ポテンシャルがある」などがあります。これらはいずれも「実行が見込める」という意味合いを共有しますが、ニュアンスに差異があります。
「実現できる」は計画や夢を現実化する際に、より確度の高い印象を与えます。「達成しうる」は目標に向けた努力が前提にあるため、スポーツや学習場面で好まれます。「ポテンシャルがある」は潜在能力を示す言葉で、今すぐではなく将来的な可否を強調します。
【例文1】十分な予算があれば、計画は実現できる。
【例文2】努力次第で優勝を達成しうる。
他にも「見込みがある」「可能性が高い」といった語も近い意味を持ちます。プレゼン資料などでは文言の重複を避けるため、状況に応じた言い換えで文章をテンポ良くすると読み手の集中力が維持できます。
ただし法律文書や契約書では、別語へ置き換えると解釈が変わる恐れがあるため注意が必要です。その場合は「可能」で統一し、補足説明を加えることで法的リスクを回避しましょう。
「可能」の対義語・反対語
もっとも一般的な対義語は「不可能(ふかのう)」です。「不」は打ち消しの接頭辞で、「不可能」は「実現できない状態」を示します。他にも「不能」「不可」「無理」などが対抗概念として用いられます。
「不能」は医学や法学で多用され、身体的・制度的制約を示す際に用います。「不可」は試験や審査での評価語として定着しており、「基準を満たさない」の意味が強いです。「無理」は口語で広く使われ、感情的ニュアンスを帯びる点が特徴です。
【例文1】時間的に不可能なスケジュールだ。
【例文2】彼は負傷により出場不能となった。
反対語を使う際は、相手に与える印象も考慮しましょう。「不可能です」と断定すると交渉が閉ざされる恐れがあります。「現状では困難ですが、条件変更で可能になります」と前向きな代替案を提示することで建設的な対話が生まれます。
ビジネス現場では「不可」と「不可能」を混同しないよう注意が必要です。「不可」は評価コード、「不可能」は状態や能力に関する判断を表すため、誤使用すると誤解が生じます。
「可能」を日常生活で活用する方法
日常会話で「可能」を使うコツは、お願いや提案を柔らかくすることです。たとえば「今週中の提出は可能でしょうか」と聞くと、直接的すぎない印象になります。相手が断る余地も残しつつ、希望を明確に伝えられます。
家計管理では、「月3万円の貯金が可能かどうか」を検討する表現が役立ちます。「可能」という語を使うと、具体的数字を掲げた計画が現実的に感じられ、実行意欲が高まります。
【例文1】車を使わずに通勤することは可能?。
【例文2】今日の夕食はテイクアウトで済ませることが可能だよ。
時間管理アプリでも「通知をオフにすることが可能」と設定項目に書かれています。このようにデバイス設定や取扱説明書では「…が可能」という説明が頻出し、ユーザーが機能を把握しやすくなっています。
子育てや介護の現場では、「在宅ワークが可能であれば支援体制が整う」といった使い方が見られます。この場合、「可能」がライフスタイルの柔軟性を示すキーワードとなり、家庭内の意思決定を助けてくれます。
「可能」についてよくある誤解と正しい理解
「可能」と言われても100%確実に実現するわけではないという点が最大の誤解です。「可能」はあくまで「やろうと思えばできる状態」を示し、実行するかどうかは別問題です。したがって契約やスケジュール調整では、具体的条件を再確認することが欠かせません。
「可能性」と同義だと誤認されがちですが、「可能」は形容動詞で状態を示し、「可能性」は名詞で度合いを示します。「可能です」と言うと可否が二分されますが、「可能性があります」と言うと確率の幅が残ります。この違いを理解しないと、ビジネスの説明責任で齟齬が生じます。
また「可能=簡単」と誤訳される例もあります。実際には高コストや長期間を伴う場合でも、「理論上可能」と表現されることがあります。そのため、「容易に」と言い換えると確実に誤情報になります。
【例文1】技術的に可能だがコスト面では非現実的。
【例文2】可能性があるだけで、必ず起こるわけではない。
最後に、法律文での「可能」は裁量権を示す場合があります。例えば「市長は必要があると認めるときは、助成することが可能である」と書かれている場合、必ず助成する義務は発生しません。文脈によって義務か権限かを読み解く力が求められます。
「可能」という言葉についてまとめ
- 「可能」は条件が整えば実現できる状態を示す言葉です。
- 読みは「かのう」で、公式文書では漢字表記が推奨されます。
- 中国由来の合成語で、明治期に学術・法令用語として定着しました。
- 具体的な条件や主体を示して使うと誤解が避けられます。
「可能」はシンプルながら、条件付きで実現が見込めるという前向きなニュアンスを含む便利な語です。読み方は「かのう」と覚えておけば、口頭でも文書でも迷うことはありません。
漢籍由来の歴史を経て、近代日本で学術・ビジネス用語として広まりました。現代では日常生活から専門分野まで幅広く用いられますが、使う際には「必ず実現する」わけではないことを意識し、条件や責任主体を明示することが大切です。