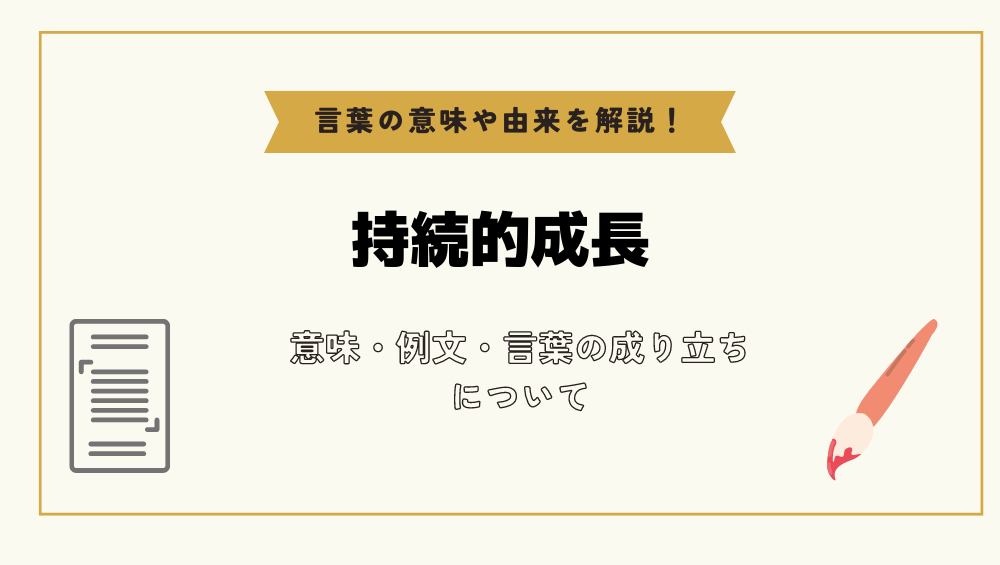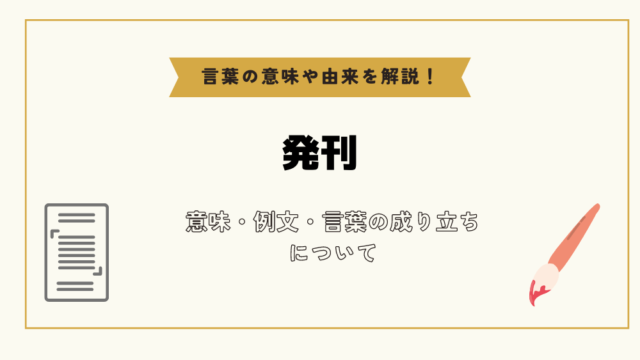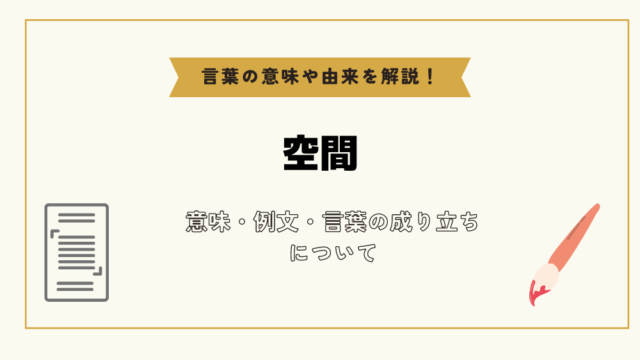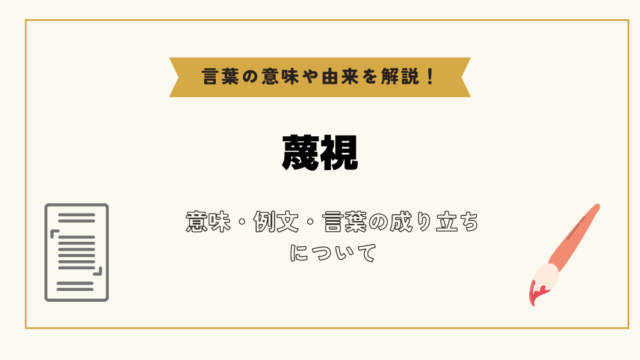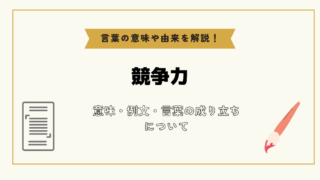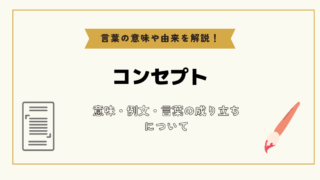「持続的成長」という言葉の意味を解説!
「持続的成長」とは、資源・環境・人材などの制約条件を踏まえながら、長期的に安定した発展を続けることを指す言葉です。経済学ではサステナブル・グロースと訳される場合もあり、単なる売上や規模の拡大だけでなく、社会的価値や環境負荷の最小化も含めた総合的な成長を意味します。企業経営や政策立案の現場では、短期的な利益追求に偏らない目標設定のキーワードとして広く使われています。
この言葉が注目される背景には、気候変動問題や少子高齢化、エネルギー制約など、従来型の成長モデルでは解決できない課題が山積していることがあります。また、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」が世界的な共通目標となったことで、企業・自治体・個人に至るまで「持続的成長」を意識した取り組みが浸透しました。
【例文1】企業は環境技術に投資し、持続的成長を実現したい。
【例文2】地方都市が持続的成長を目指すためには人材循環が不可欠。
「持続的成長」の読み方はなんと読む?
「持続的成長」は「じぞくてきせいちょう」と読みます。「持続(じぞく)」と「成長(せいちょう)」の間に「的(てき)」が入ることで、「持続する性質をもった成長」という形容修飾の関係になります。ビジネス会議や学会発表の場でも、平易な読み方であるため漢字のまま使われることが多いです。
口頭でのコミュニケーションでは、語勢が強い単語なので「持続的“な”成長」と「な」を付けて形容詞的に使うケースも見られます。英語では“Sustainable Growth”が一般的ですが、日本語で議論する際は原則としてカタカナ表記せず漢字表記が推奨されています。
【例文1】次世代エネルギーはじぞくてきせいちょうの鍵だ。
【例文2】じぞくてきせいちょう型の経営戦略を立てよう。
「持続的成長」という言葉の使い方や例文を解説!
現場での使い方のポイントは「時間軸」と「総合性」の二点を示すことです。短期的・部分的な拡大ではなく、長期的・多面的な発展を示したい場合に用いると意図が伝わりやすくなります。特にCSRレポートや統合報告書では、「持続的成長に資する投資」「持続的成長のための人材育成」など目的語を補うと説得力が高まります。
【例文1】環境対策と収益性を両立させることで持続的成長を図る。
【例文2】地域社会との共創が持続的成長の土台になる。
注意点としては、単に成長率を示す数値目標を掲げるだけでは「持続的」とは言い難いため、根拠となる仕組みやプロセスも合わせて言及することが大切です。
「持続的成長」という言葉の成り立ちや由来について解説
「持続」という漢語は江戸後期の学術書にも見られ、連続して保たれる意を表します。「成長」は明治期以降、近代経済学の翻訳語として定着しました。二語が結び付いた「持続的成長」という複合語は、1970年代のオイルショック以降、資源制約下での経済モデルを論じる中で使われ始めたとされています。
由来的には、ローマクラブの報告書『成長の限界』(1972)を受け、日本の経済学者が「サステイナブル・グロース」を訳する際に「持続的成長」という表現を採用したことが大きいとされています。これにより、環境保護と経済発展を両立させる概念として定着し、今日に至ります。
【例文1】持続的成長という概念は70年代の環境危機に端を発する。
【例文2】日本語訳では持続的成長がサステイナブル・グロースに相当する。
「持続的成長」という言葉の歴史
1970年代に研究者の間で使われ始めた後、1992年の地球サミットで採択された「アジェンダ21」をきっかけに国際的議論が活性化しました。2000年代にはESG投資の盛り上がりやISO14001の普及により、企業経営の中核概念へと進化しました。
2015年に国連でSDGsが採択されると、「持続可能」と並んで「持続的成長」も一般用語として浸透しました。近年は脱炭素社会の実現を巡る政策議論や、人的資本経営の重要性が高まったことで、持続的成長の射程は環境のみならず社会・ガバナンス領域にまで広がっています。
【例文1】SDGs時代における企業の使命は持続的成長だ。
【例文2】脱炭素経営こそ持続的成長の近道である。
「持続的成長」の類語・同義語・言い換え表現
類語としては「持続可能な成長」「サステナブル成長」「長期的成長」「安定成長」などが挙げられます。いずれも長い時間スパンを意識し、急拡大よりも安定を重視するニュアンスがあります。
ビジネス文章では、英語の“Sustainable Growth”をそのままカタカナ化した「サステイナブル・グロース」がよく用いられます。また、経営学では「長期価値創造」「恒常的発展」といった表現に置き換えることも可能です。
【例文1】サステイナブル・グロースを実現するR&D投資。
【例文2】長期価値創造の視点で持続的成長を捉える。
「持続的成長」の対義語・反対語
対義語として代表的なのは「短期的成長」「急成長」「バブル的成長」です。これらは短期間で急激に規模拡大を図る一方、資源や資本が枯渇しやすい点が特徴です。
「バブル的成長」は持続可能性の欠如を示すネガティブワードとして用いられ、持続的成長との対比でリスクを強調する際に便利です。経営戦略を語る際には、短期的利益の追求に偏る危険性を示すために対義語の概念を押さえることが役立ちます。
【例文1】短期的成長に偏るとバブル的成長に陥りやすい。
【例文2】急成長ではなく持続的成長を重視したい。
「持続的成長」と関連する言葉・専門用語
持続的成長を論じる際には、環境・社会・ガバナンスを示す「ESG」、国連が定めた「SDGs」、循環型経済を表す「サーキュラーエコノミー」などの概念が密接に関わります。また、企業価値を測る指標として「ROIC(投下資本利益率)」や「人的資本経営」が重視されるのも特徴です。
これらの用語はいずれも、経済成長と社会的課題の同時解決を図るフレームワークとして、持続的成長を支えるキーワードです。理解を深めるためには、各専門用語の定義と相互関係を押さえておくと議論に厚みが出ます。
【例文1】ESG投資は企業の持続的成長を後押しする。
【例文2】サーキュラーエコノミーの導入で持続的成長を加速する。
「持続的成長」という言葉についてまとめ
- 「持続的成長」は資源・環境・社会への配慮を含めた長期的な発展を示す概念。
- 読み方は「じぞくてきせいちょう」で、漢字表記が一般的。
- 1970年代の資源制約論から生まれ、SDGsの広がりで定着した。
- 使用時は時間軸と総合性を示し、短期的成長との区別を明確にすることが重要。
「持続的成長」は環境・社会・経済のバランスを取りながら、長期的に価値を創造し続ける姿勢を端的に表す言葉です。読み方や表記はシンプルですが、背後には資源制約や社会課題を乗り越えるための知恵と覚悟が込められています。
歴史的には1970年代の環境危機から生まれ、SDGsという世界共通目標を追い風に一般化しました。現代のビジネスや政策においては、単なる流行語ではなく、持続可能な社会を構築するための中核概念として機能しています。
実務で使う際は、短期的利益と長期的価値の両立を示す具体的施策とセットで語ることが肝要です。適切な場面で言葉を選び、真に持続性のある成長を実現していきましょう。