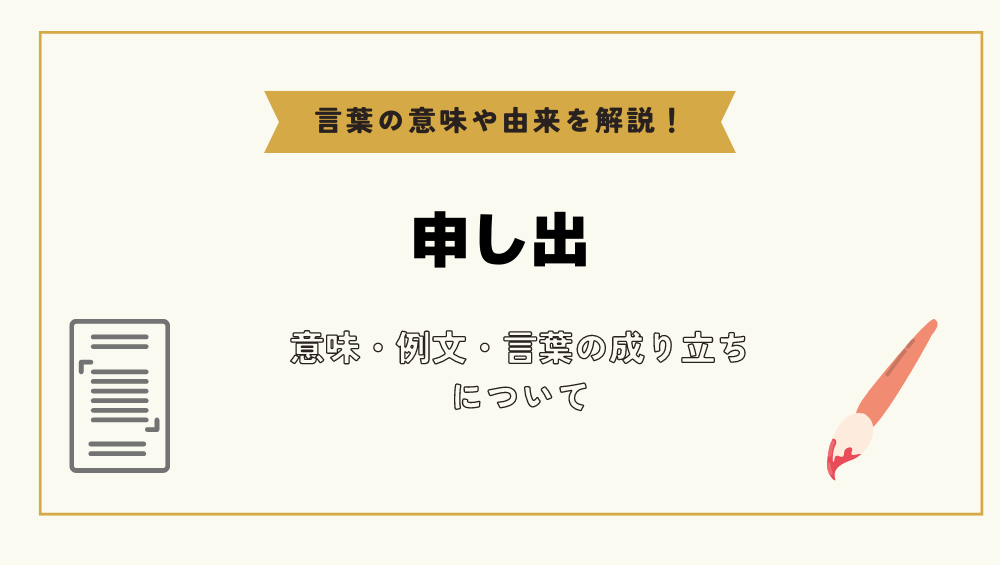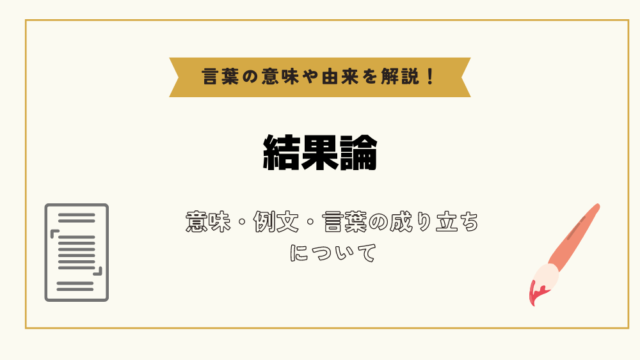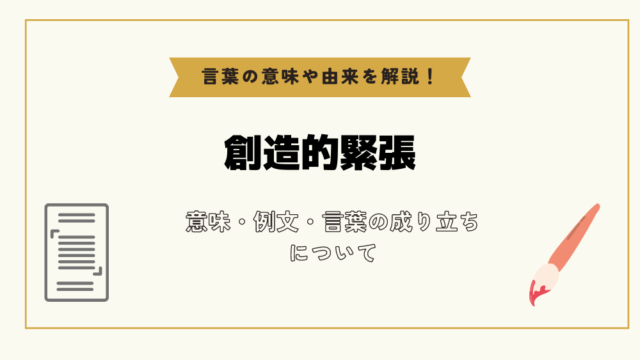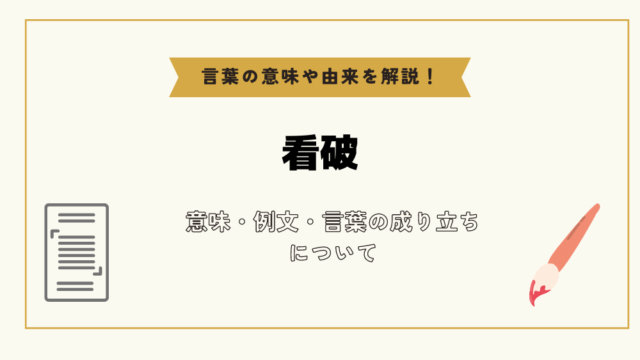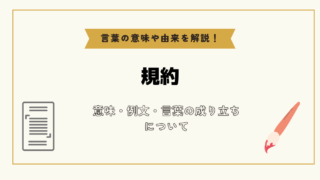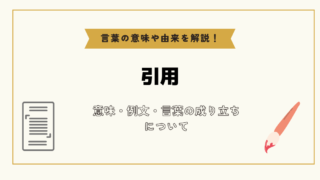「申し出」という言葉の意味を解説!
「申し出(もうしで)」とは、自分の意思や要求、提案、報告などを相手に向けて公式に伝える行為を指す日本語名詞です。行政手続きやビジネスシーンでは「提出」「届け出」とほぼ同義に扱われることもあります。日常会話では「親切な申し出」のように好意的な提案を示す場合も多く、文脈により「オファー」「申し込み」「自己申告」のニュアンスが入り混じります。
「申し出」の語感には相手を立てる敬意が含まれ、単なる提案よりも丁寧さが強調されます。そのため目上の人や公的機関に対して自分の希望を述べる際に最適な言葉といえるでしょう。
法令や規約の文言では「~の申し出を受けたときは」「~の申し出に基づき」といった形で頻出し、手続きの起点となる行為を明示します。書類上で使う場合は「申出」と送り仮名を省略することが一般的です。
要するに「申し出」は、相手に敬意を払いながら自分の意向を正式に表明する日本語の定番ワードだと覚えておくと便利です。
「申し出」の読み方はなんと読む?
「申し出」の読み方は平仮名で「もうしで」と読みます。「申し」は動詞「申す」(言うの謙譲語)に由来し、「出」は外に出すことを表します。音読み・訓読みが混ざる重箱読みの一種ですが、慣用読みとして完全に定着しているため迷うことはないでしょう。
送り仮名を付けない略式表記「申出」は、公的文書や契約書で採用されがちです。「もうしでる」と動詞形にすると書き言葉でも話し言葉でも違和感なく使用できます。
また「申し」の部分が敬語を含むため、相手を上位に置くニュアンスを付与します。社交辞令的に柔らかく聞こえるため、同じ内容でも「提案」より角が立ちにくいのが特徴です。
読み間違い例として「もうで」と省略するケースがありますが、正式には「もうしで」ですので注意しましょう。
「申し出」という言葉の使い方や例文を解説!
「申し出」は敬意を伴う名詞なので、謙譲語や尊敬語と組み合わせて丁寧な表現を作ると自然です。たとえば「ご提案」をさらにへりくだって示したいときに便利です。
【例文1】退職の意向を上司に申し出る。
【例文2】市役所へ住所変更の申し出を行う。
【例文3】善意の寄付を申し出てくださった。
【例文4】取引条件の見直しを申し出る。
上記の例のように、主語は個人にも法人にも置き換えられます。動詞形「申し出る」を使う場合、「AがBに~を申し出る」という三項構造を意識すると書きやすいです。
丁寧さをさらに高めるには「ご」や「お」を付け、「ご申し出」「お申し出」とすると失礼がありません。
「申し出」という言葉の成り立ちや由来について解説
「申し出」は動詞「申す」と「出る」が結合した「申し出る」の名詞形として生まれました。「申す」は平安時代に成立した謙譲語で、目上に向かって言葉を差し上げる意を示します。「出る」は奈良時代の『万葉集』にも見られる最古級の動詞で、内部から外側へ向かう動作を示します。
つまり「申し出」は“敬意をもって言葉を外へ出す”という意味合いを、語形そのものに内包しているのです。中世以降、公家社会や武家社会で口上を述べる行為が「申し出」と呼ばれ、やがて江戸期の公文書にも記載されるようになりました。
明治期の近代法体系整備に伴い、申告・届出・請願などと並ぶ行政用語として固定化。今日の法令データベースでも約2万件以上登場し、その重要性がうかがえます。
敬語文化と文書主義の歴史が、「申し出」を公式な手続き用語へと発展させた背景といえるでしょう。
「申し出」という言葉の歴史
古文献をたどると、鎌倉時代の『吾妻鏡』に「申し出でたる由候」との記載が確認できます。室町期には武将の起請文にも使用例が増え、口頭だけでなく書面にも進出しました。
江戸幕府の公事方書では「所持金申出候」というように記述され、庶民から武士まで幅広く浸透します。明治維新後は「太政官布告」や「内務省令」が相次いで発布され、その都度「申し出」が義務・権利の起点として明記されました。
戦後の日本国憲法下でも「国又は地方公共団体に対する損失の補償の申し出」のように条文で存続し、現代法体系に連綿と受け継がれています。昭和・平成期には企業コンプライアンスの文脈で「内部通報の申し出」が新たに注目されるなど、社会の変化に合わせて守備範囲を拡大しています。
近年ではデジタル庁が推進するオンライン行政手続きで「電子申出書」という新語も誕生し、「申し出」はアナログからデジタルへと舞台を広げつつあります。
「申し出」の類語・同義語・言い換え表現
同じような文脈で使える語として「提案」「申し込み」「届け出」「申告」「オファー」「申し入れ」などがあります。
ニュアンスの違いを理解すれば、文脈に最適な言葉を選択できるようになります。たとえば「申告」は税務や統計など数字を伴う報告色が強く、「届け出」は法的義務の履行を示す場合に適切です。「申し入れ」は相手に対し条件や要望を示す硬い語感があります。
【例文1】価格改定を提案する。
【例文2】退去届を届け出る。
【例文3】欠品の発生を申告する。
これらは「申し出」で言い換え可能ですが、敬意や手続きの厳格さが変化するため、置き換え時は注意が必要です。
「申し出」は敬意と公式性のバランスが取れた万能ワードとして位置づけられます。
「申し出」を日常生活で活用する方法
身近なシーンでも「申し出」を上手に使うと、コミュニケーションが円滑になります。たとえば交通機関で席を譲りたいときに「お席を代わりましょうかと申し出る」と言えば、相手へ配慮を示しつつ自分の意思を伝えられます。
家庭では「家事分担を申し出る」と言うと、単なる提案より協力姿勢が強調され、角が立ちません。学校では「補講の開催を申し出た」と記述すれば、自発的な学習意欲を表明できます。
ビジネスシーンでは「在宅勤務を申し出る」「企画案の修正を申し出る」などが一般的です。メール表現では「この度、お時間の変更をお願い申し上げたくご連絡申し上げます」と敬語を重ねて丁寧さを確保します。
ポイントは“相手の判断を尊重する姿勢”を込めることにあり、こうした配慮が円満な合意形成へとつながります。
「申し出」についてよくある誤解と正しい理解
「申し出る=要求が通る」と誤解されがちですが、実際は“意思表示”にすぎません。受け手側が承諾しなければ成立しない点を押さえましょう。
もう一つの誤解は「申し出=謝罪」と思い込むケースですが、謝罪文中で使われることが多いだけで、本来は中立的な単語です。むしろ謝罪の意思を丁寧に伝える効果があるため、謝罪文で頻繁に採用されています。
【例文1】返金を申し出たが、相手が不要と回答した。
【例文2】無償サポートの申し出を丁重にお断りする。
以上のように「申し出」は双方向の意思決定プロセスの第一歩であり、一方的な決定事項ではないという点を理解することが重要です。
誤解を防ぐには、申し出内容・目的・期限を具体的に明示し、相手が判断しやすい情報を添えることがカギとなります。
「申し出」という言葉についてまとめ
- 「申し出」とは、敬意をもって意思や提案を公式に伝える行為を指す言葉。
- 読み方は「もうしで」で、書類では「申出」とも表記される。
- 動詞「申す」と「出る」から成り、平安期の敬語文化とともに発展した。
- 現代では行政から日常会話まで幅広く用いられ、相手への配慮が欠かせない。
「申し出」は敬語文化の粋ともいえる日本語表現で、相手を立てながら自己の意思を示すための便利な語です。使い方を誤らなければ、ビジネスでも家庭でも良好な関係を築く強力なツールとなります。
現代社会ではオンラインフォームやメールなど媒体が多様化していますが、根底にある“丁寧に意思を外へ出す”という精神は不変です。状況や相手に応じて具体性と期限を示し、誤解のないコミュニケーションを心がけましょう。