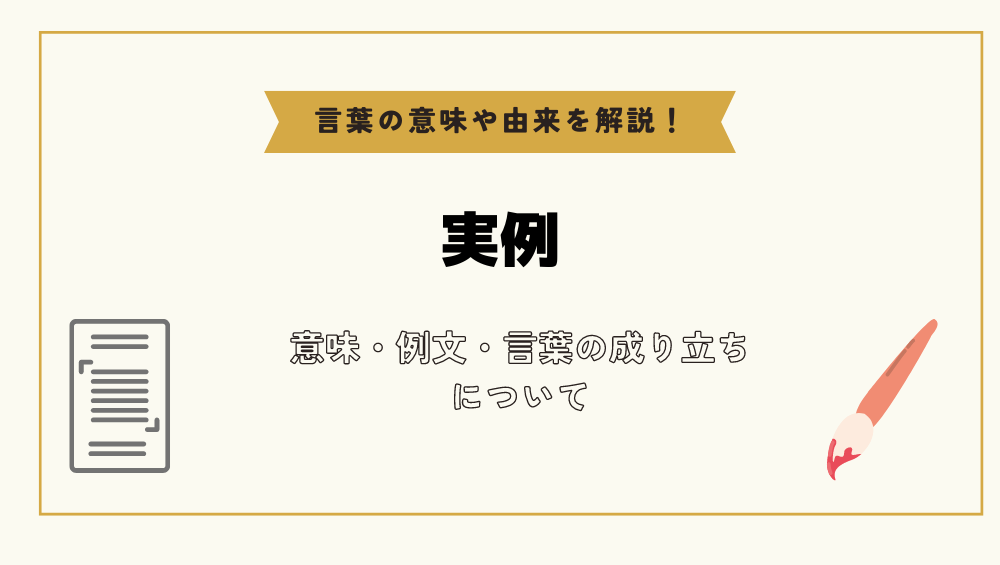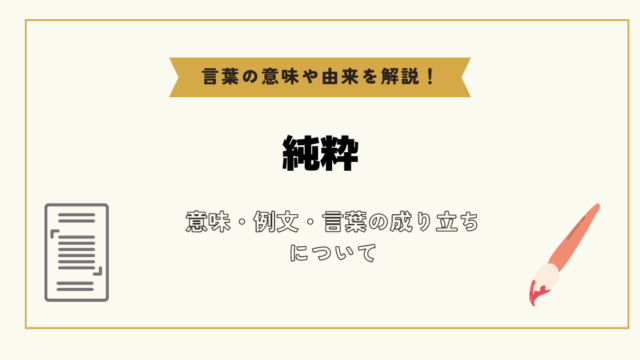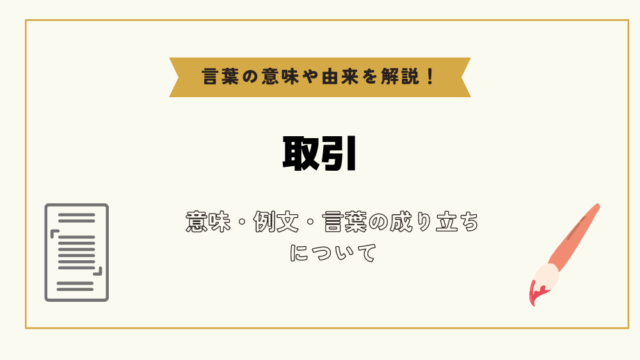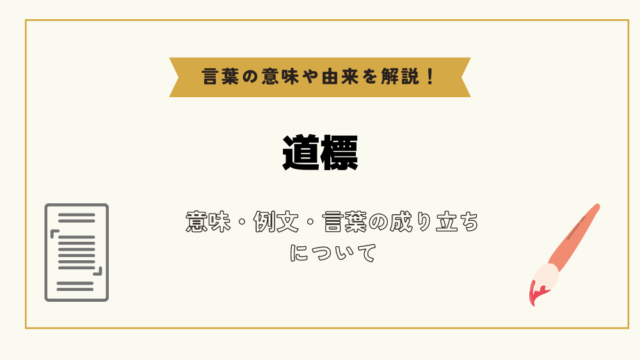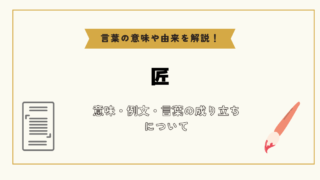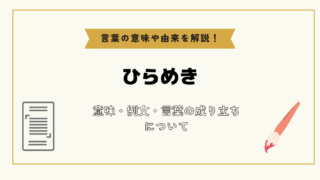「実例」という言葉の意味を解説!
「実例」とは、抽象的な概念を具体的に示すための既に存在する事柄や事象を指す言葉です。一般的には、説明や議論をわかりやすく補強する目的で提示されることが多く、ビジネス文書から学術論文、日常会話まで幅広い場面で用いられます。英語では“example”や“case”に相当し、実践的・具体的・客観的という三つの性質を併せ持つ点が特徴です。抽象度の高いテーマでも、実在する事実を挙げることで相手の理解を助け、納得感を生み出せるため、説得力を高める有用な方法といえます。
「データ」との違いはよく混同されますが、データが観測値や数値そのものを指すのに対し、実例はデータを含む具体的な事象全体を示します。「具体例」とはほぼ同義ですが、実例の方が“実際に起きた”ニュアンスが強い点で区別されます。
「実例」の読み方はなんと読む?
「実例」の読み方は「じつれい」で、ひらがな表記では“じつれい”、カタカナ表記はほとんど用いられません。読み間違いとして「じちれい」と発音してしまうケースが散見されますが、正しくは濁音の「つ」を用いる点に注意しましょう。漢字二文字のうち「例」は“ためし・たとえ”を含意するため、音読するときに“れい”と伸ばすのが自然です。
音便化しやすい単語ではないものの、議事録や速記で「実例を挙げる」と書く際に「実例を上げる」と誤変換されることがあります。「挙げる」は“あげる”ですが、文章で混乱を招くため正しい表記を意識すると読み手が混同せずに済みます。
「実例」という言葉の使い方や例文を解説!
実例は「抽象的な説明を補足する」「説得力をもたせる」「再現性を検証する」など、多岐にわたる用途で用いられます。とくにビジネスではプレゼン資料や報告書で、学術ではケーススタディや症例報告で重宝されます。
【例文1】新しいマーケティング戦略の実効性を示すために、昨年度の実例を提示した。
【例文2】医師は治療法を説明する際、似た症状の実例を出して患者を安心させた。
場面に合った語選びも重要です。会話では「具体例」がなじみやすいケースがありますが、文書で公的に示す際は「実例」の方が信頼感を与えやすい傾向があります。また、複数提示する場合には「複数の実例」「いくつかの実例」といった数量詞を添えると明快です。
「実例」という言葉の成り立ちや由来について解説
「実例」は、“実”と“例”の二字熟語で、中国古典に由来をもつ翻訳語ではなく、明治期以前から和文漢語として定着していました。“実”はリアリティや事実を示し、“例”は手本・試みを示すため、二字を合わせることで「事実に基づく手本」という意味が自然に構築されています。
奈良時代の文献には見当たりませんが、江戸期の和算書や儒教書には「実例ヲ見セテ教ヘル」といった表現が散発的に見られます。当時は“じつれい”という音読みのほか、“みのりためし”と訓読される場合もあったようです。明治期以降、実証主義的な学問の広がりとともに「具体例」「事例」と並んで学術用語として定着し、現在の多用途性につながりました。
「実例」という言葉の歴史
江戸中期から明治初期にかけて、「実例」は学問・武芸・技術書で頻出し、近代化の過程で教育現場にも広がりました。特に明治20年代の『尋常小学読本』には「算数の実例」「修身の実例」が掲載され、子どもが抽象概念を具体的に学ぶ方法として制度的に導入されています。
大正期には法律や裁判分野で「判例」と区別しつつ、実際の事案を要約した“実例集”が刊行されました。戦後の高度経済成長期には、経営学や工学分野でケーススタディの翻訳語として再評価され、英語の“case study”と対で用いられる場面が増えました。現代ではデジタル分野でも「UIデザインの実例」「セキュリティ事故の実例」といった形で使われ、時代とともに応用範囲が拡張していると言えます。
「実例」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「具体例」「事例」「ケース」「サンプル」「ケーススタディ」が挙げられます。「具体例」は日常で最も汎用的ですが、“実際に起きた”ニュアンスが薄い場合があります。「事例」は官公庁文書や論文でよく見られ、法律文脈では「判例」との混同に注意が必要です。「ケース」は外来語で、ITや医療分野で簡潔さを重視する際に選ばれます。
語感の違いを整理すると、客観性を重視するときは「事例」、再現性を検証するときは「ケーススタディ」、実践的アドバイスを示すときは「サンプル」が向いています。言い換えの際は対象読者と文脈に合わせて最適な語を選択しましょう。
「実例」の対義語・反対語
対義語としてまず挙げられるのが「抽象」です。「抽象」は具体的事実から離れて本質的・概念的側面を取り出す行為や思考を指し、実例が“具体”を示すのに対し真逆の位置にあります。さらに「仮説」「概念」「モデル」も状況によって対抗概念として用いられることがあります。
【例文1】この理論は抽象的すぎるので、実例を追加して理解を深めたい。
【例文2】仮説だけでは説得力が弱いので、検証された実例が必要だ。
一方で、「反証」や「例外」は“既存の実例を打ち消す存在”として反対の機能を持ちますが、語種としては対義語ではなく“対立概念”に近い位置づけです。言語的にペアで扱う場合は「実例と抽象」「具体と抽象」が最も一般的です。
「実例」を日常生活で活用する方法
身近な場面ほど実例を意識的に活用すると、コミュニケーションの誤解が減り、物事の合意形成がスムーズになります。たとえば家庭で新しい掃除ルールを決めるとき、抽象的に「きれいにしよう」ではなく「週末にリビングを10分ずつ掃除した実例」を示すと理解しやすくなります。
勉強では公式や定理を学ぶ際に、教科書の数値を自分の生活に置き換えた実例を作ると記憶の定着が促進されます。また、友人に料理を教える場合でも「分量は目安」と言うより「昨日作ったカレーを例に取ると…」と示す方が説得力が増します。
プレゼン練習では、相手の興味関心に合わせた実例を前もって準備すると質問対応が容易になります。ポイントは「相手が想像できる範囲の事実」「新規性があり過ぎない」「数字や固有名詞を明確にする」の三点です。
「実例」についてよくある誤解と正しい理解
「実例=一次情報」と誤解されることがありますが、必ずしも一次情報とは限らず、第三者の報告でも実際に起きた事実を示せば実例になり得ます。また、「実例が多いほど結論は正しい」との見方も危険です。多数の実例が偏っている場合、統計的な偏りやバイアスが発生するため、客観性の担保が不可欠です。
【例文1】成功例ばかりの実例集は参考になるが、失敗例も併記しないと再現できない。
【例文2】ネット上の実例を鵜呑みにせず、出典と検証手続きを確認するべきだ。
誤解を避けるコツは「出典の明示」「条件の説明」「反例の提示」の三点セットで示すことです。これにより読み手は同一条件で再現可能かどうかを判断できます。
「実例」という言葉についてまとめ
- 「実例」は抽象的な概念を具体的に示すための事実や事象を指す言葉。
- 読み方は「じつれい」で、“実”と“例”の二字熟語として表記する。
- 江戸期の技術書に起源が見られ、明治以降に学術・教育分野で定着した。
- 活用時は出典や条件を明示し、反例も含めることで信頼性が高まる。
実例は抽象的な説明を補強し、説得力や具体性を与えるための強力なツールです。読み手の理解を助けるだけでなく、情報の再現性や検証可能性を担保する役割も果たします。
一方で、多数の実例を示せば必ずしも結論が正しいわけではなく、データの偏りや誤解につながるリスクがあります。出典の明示と条件説明、反例の提示を通じて、公正かつ正確な情報提供を心がけましょう。