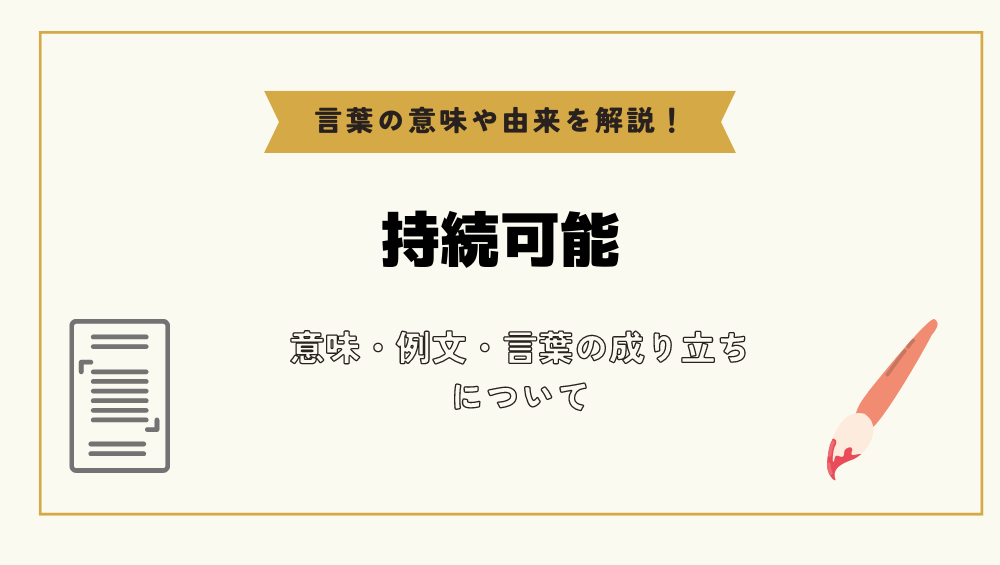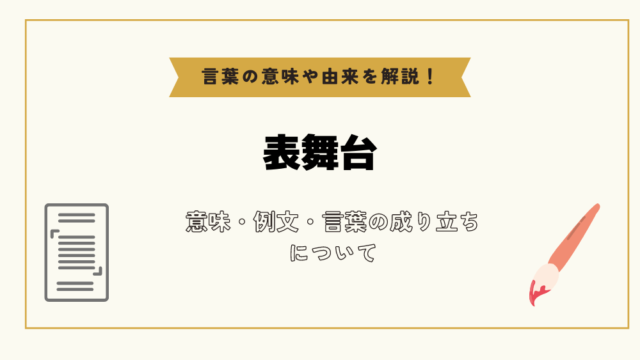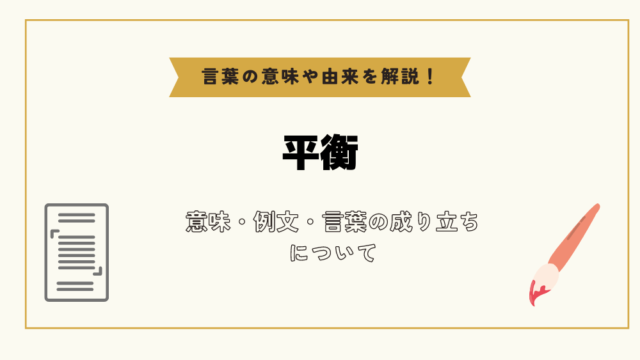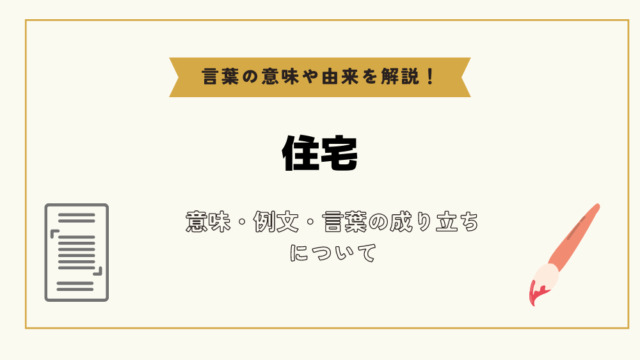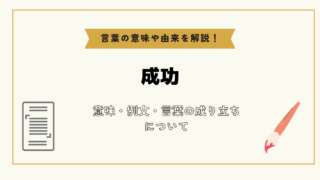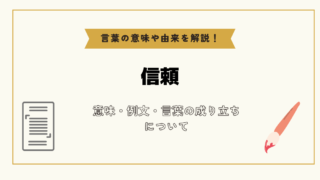「持続可能」という言葉の意味を解説!
「持続可能」とは、資源や環境、社会制度などを未来世代まで損なわずに保ち続けられる状態を指す言葉です。直訳すると「持ち続けることが可能」であり、単なる長期継続ではなく、関わるシステム全体が健全に循環し、負荷を回復可能な範囲に収める点が特徴です。暮らしやビジネスなど、あらゆる分野で「今の行動が将来にどんな影響を与えるか」を考える軸として用いられます。
もう少し踏み込むと、経済・環境・社会の三側面が調和しながら発展し続けることを意味します。この三側面は「サステナビリティの三本柱」と呼ばれ、どれか一つでも崩れると持続性は成立しません。たとえば経済的に成長しても、環境が壊れれば社会全体の基盤が失われ、結局は成長も頓挫してしまうという考え方です。
ビジネス領域では、企業が環境配慮や人権尊重を図りつつ利益を上げる経営方針を「持続可能な経営」と呼びます。行政では、地域の自然資源・文化資本を活用しながら住民の暮らしを守る政策を「持続可能なまちづくり」と表現します。つまり、具体的な対象は変わっても「未来世代にツケを回さない」という中核は同じです。
世界共通の課題認識として、国連が採択した「SDGs(持続可能な開発目標)」も、この概念を土台に設定されています。17のゴールは地球規模の問題を包括的に扱い、貧困や気候変動から教育まで幅広いテーマを網羅しています。SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念も、持続可能性の延長線上に位置づけられます。
最後に注意したいのは、「我慢して節約する」だけでは持続可能とは呼べないことです。負担を先送りしているだけではなく、システムが自律的に回復しながら発展できる仕組みを設計することが重要です。そのためには技術革新や制度改革、市民参加が欠かせません。
「持続可能」の読み方はなんと読む?
多くの人が迷いがちな読み方ですが、正式には「じぞくかのう」と読みます。漢字の構成を分解すると「持続(じぞく)」と「可能(かのう)」の二語から成り立ち、それぞれの読みをそのまま連結した形です。読み方が分かると、言葉のニュアンスが自然に頭に入りやすくなります。
英語では “sustainable” が最も一般的な訳語で、「サステナブル」や「サステイナブル」とカタカナ表記する場合もあります。カタカナ語の方が生活者に浸透している場面もあり、メディアでは「サステナブルファッション」「サステナブルツーリズム」などの用例が増えています。これにより「持続可能=サステナブル」という認識が広まりつつあります。
なお、専門家の間では「サステイナビリティ(sustainability)」という名詞形も広く使われます。この言葉を略して「サスティナビリティ」と表記されることもありますが、原語のつづりに忠実な「サステイナビリティ」を推奨する団体も見られます。公的文書では漢字表記とカタカナ表記を併記して読みやすさを確保するケースが多いです。
読み方を覚えるコツは「持つ」「続く」「可能」の三要素を頭の中で分けて確認し、ゆっくり音読することです。漢字が並ぶと難しそうに見えますが、実際の音は平易な日本語なので、口に出してみると意外とすぐに覚えられます。ビジネスのプレゼンやレポートで使うときは、落ち着いて発音することで説得力が高まります。
「持続可能」という言葉の使い方や例文を解説!
「持続可能」は形容動詞的に「〜が持続可能だ」または連体修飾として「持続可能な〜」と用います。基本的にフォーマルな場面で使用され、論文や政策文書、ビジネスレポートに頻出です。日常会話で使う場合は「長く続けられる~」と置き換えても意味が通じます。
使い方のポイントは、対象となる活動やシステムが長期的に維持できる根拠を合わせて示すことです。「持続可能な農業」と言うなら、具体的に化学肥料の削減や循環型の肥培管理を説明すると説得力が増します。抽象的に響きやすい言葉だからこそ、裏付けとなるデータや事例を添えると誤解が生じにくくなります。
【例文1】私たちの会社は再生可能エネルギーを導入し、事業全体を持続可能な形へ転換する計画を立てている。
【例文2】地域の森林資源を活用した持続可能な住宅建築が注目されている。
【例文3】持続可能な社会を実現するためには、個人のライフスタイルも見直す必要がある。
文章で使う際は「サステナブル」というカタカナ表現と混在させない方が読みやすくなります。学術論文や行政文書では漢字表記の「持続可能」を優先し、カタカナ語は脚注で補足する方法が一般的です。読み手の専門性に合わせて言い換えながら使うと良いでしょう。
会話で用いるときは「今のやり方だと持続可能じゃないよね」と否定形を添えると、改善の必要性を端的に示せます。このフレーズは職場の会議や家庭内での資源管理の話し合いなど、場面を問わず活用できます。言葉自体が問題提起のトーンを帯びているため、相手にも考えを促す効果があります。
「持続可能」という言葉の成り立ちや由来について解説
「持続可能」は、戦後の日本語学術訳語として登場しました。英語 “sustainable” を直訳する際に「持続」と「可能」を組み合わせた合成語です。当初は学術論文や政府の翻訳資料で限定的に使われていましたが、1990年代から環境政策のキーワードとして定着しました。
由来をたどると、1972年の「かけがえのない地球(UNEP設立宣言)」や、1987年の「ブルントラント委員会報告」が直接的な源流に位置づけられます。この報告書では “sustainable development” が「将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発」と定義され、世界的な概念として確立しました。日本の訳語はその文脈を受けて「持続可能な開発」とまとまりました。
漢字の選定には、「sustain=支える」「continue=続く」の両ニュアンスを兼ねる「持続」が採用されました。「可能」を付すことで「支えるだけでなく、実現できる」という動態的な意味合いを含ませています。その結果、単なる時間的継続ではなく、行為主体の努力と仕組みが伴う概念として機能しています。
現在では「持続可能」という語だけでも「サステナビリティ全般」を指す総称として浸透しており、訳語から独立した日本語として扱われる段階に入りました。新聞見出しや企業のキャッチコピーで単独使用される例も増え、日常語彙として根づきつつあります。言葉の成り立ちを知ることで、なぜ社会がこの言葉に注目するのかが理解しやすくなります。
「持続可能」という言葉の歴史
「持続可能」の歴史は、国際社会の環境問題への取り組みと並行しています。1970年代の公害問題を契機に、急速な経済成長の陰で生じる負荷が顕在化し、各国が環境保護策を強化しました。日本でも「環境基本法」などの成立により、行政用語として「持続可能な発展」が導入されました。
1992年の地球サミットで採択された「リオ宣言」と「アジェンダ21」が、持続可能の概念を世界全体に広げるターニングポイントになりました。この会議では「持続可能な開発」が国際的合意として位置づけられ、先進国・途上国双方が共有すべき原則とされました。以降、企業も社会的責任(CSR)の一環として持続可能性を評価されるようになります。
2000年代に入ると、気候変動への危機感が高まり、「低炭素社会」や「循環型社会」の実現が政策の柱となりました。2015年の国連サミットでSDGsが採択されると、持続可能はビジネス戦略や教育カリキュラムにも組み込まれ、一般市民の関心も急速に拡大しました。大学では「持続可能学」や「環境経営学」といった学際的な分野が整備されました。
近年はESG投資やカーボンニュートラル目標といった金融・技術面の動きが連携し、持続可能性が具体的な数値目標で測定される時代に入っています。評価指標が整備されたことで、企業は義務として持続可能性を説明する必要が生じ、消費者も製品やサービスの選択基準に組み込むようになりました。こうして「持続可能」は単なるスローガンから、具体的行動を促す実務用語へと発展しています。
「持続可能」の類語・同義語・言い換え表現
「持続可能」の近い意味を持つ日本語には「永続的」「長期的」「恒常的」「継続可能」などがあります。ただし、これらは時間的スパンを示す語であり、資源循環や社会的公正を含意しない点でニュアンスが異なります。「自立可能」や「自走可能」は、外部支援に頼らず続けられるという側面に焦点を当てた言い換えとして使われます。
英語圏の同義語では “viable”(実行可能)や “durable”(耐久性のある)などが挙げられますが、厳密には持続可能性=サステナビリティほどの広がりはありません。逆に専門家は “long-term sustainability” と強調表現を用いて、単なる長期性ではなく包括的な持続性を示します。日本語文章で英語を用いる際は、文脈に合わせてニュアンスを補足すると理解が深まります。
類語を使い分けるコツは、環境面を強調するなら「環境負荷の少ない」、社会面を強調するなら「包摂的な」など具体的形容詞を組み合わせることです。これにより、「持続可能」を連呼するだけの漠然とした表現を避けられます。たとえば「包摂的で環境負荷の少ない経済成長」と言えば、持続可能性の要件を具体化できます。
ビジネス文書では「長期的に維持可能」「再生可能エネルギー活用」といったフレーズが、同義語として実務的な印象を与えるため好まれます。言い換えを適切に行うことで、文章のリズムを保ちつつ、読み手に具体像を連想させる効果があります。
「持続可能」の対義語・反対語
「持続可能」の明確な対義語は日本語で定まっていませんが、意味の対立軸として「不可持続」「短命」「一過性」「枯渇的」「破壊的」などが挙げられます。これらの語は、資源やシステムが将来にわたって維持できない状態を表します。
英語では “unsustainable” が直接的な反意語で、「持続不可能な」と翻訳されます。たとえば “unsustainable consumption” は「持続不可能な消費形態」、 “unsustainable growth” は「持続不可能な成長」と訳出されます。政策提言では「現状の経済成長はunsustainableだ」と否定形で課題を示すことが一般的です。
対義語を使う際は、システムの寿命を縮める要因を具体的に示すと説得力が増します。「化石燃料依存は持続不可能である」という文は、温室効果ガス排出や枯渇リスクを示す根拠を伴って初めて意味を持ちます。「一過性」は「バブル的」と併用すると金融や流行の文脈でニュアンスが伝わりやすくなります。
反対語を理解することは、持続可能性の要件を反証的に確認する重要な手段です。自らの計画が「短命」に陥っていないか、「破壊的」な要素がないかをチェックすることで、より堅牢な戦略を構築できます。
「持続可能」と関連する言葉・専門用語
持続可能性を語る際によく登場するのが「SDGs」「ESG」「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」などの専門用語です。SDGsは17の国際目標を通じて、貧困・ジェンダー・環境などの課題を包括的に解決しようとする枠組みです。
ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字で、企業価値を測る新しい投資指標として重要視されています。カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出と吸収を差し引きゼロにする概念で、2050年を目標年とする国や企業が増えています。サーキュラーエコノミーは、廃棄物を資源として循環させる経済モデルを指します。
他に「ライフサイクルアセスメント(LCA)」は製品の原料採取から廃棄までの環境負荷を評価する手法で、持続可能な設計を支えるデータ基盤となります。「ネイチャーポジティブ」は自然環境の損失を止め、回復へ向かわせる考え方として注目されています。
これらの専門用語を正しく理解することで、「持続可能」という言葉を単なるスローガンから実践的な指標へと昇華できます。ビジネスや研究で扱う際は、用語間の関係性を整理し、適切に使い分けることが成果につながります。
「持続可能」を日常生活で活用する方法
「持続可能」という概念は、日常の小さな選択にも応用できます。たとえば食品ロスを減らすために冷蔵庫の在庫を把握し、買い物リストを作るだけでも資源の無駄遣いを抑えられます。使い捨て製品の代わりにリユース可能なアイテムを選ぶことも、有効なアクションです。
エネルギー面では再生可能エネルギーの電力プランに切り替える、家電を省エネ性能の高いものへ更新するといった手段があります。交通では短距離移動を自転車や徒歩に切り替えることで、健康促進とCO₂削減を同時に実現できます。衣類の購入時に「エシカルファッション」ブランドを選べば、労働環境改善にも貢献できます。
【例文1】私はマイボトルを持ち歩き、ペットボトルの使用を減らすことで持続可能なライフスタイルを意識している。
【例文2】地域の農家から旬の野菜を買うことで、地産地消を通じた持続可能な食文化を支えている。
習慣化するコツは「小さな成功体験を積むこと」です。まずは月一回のリサイクルデーに参加するなどハードルの低い行動から始めると、実感を伴って継続しやすくなります。行動を記録し可視化すると、家族や友人とも成果を共有できてモチベーションが高まります。
日常行動と持続可能性を紐づけることで、抽象的だった概念が自分ごとになり、社会全体の変化を後押しできます。無理なく楽しみながら続けることこそ、持続可能性を体現する最良の方法です。
「持続可能」という言葉についてまとめ
- 持続可能とは、資源や社会を未来世代まで傷付けずに保ちながら発展させる概念。
- 読み方は「じぞくかのう」で、英語では “sustainable” が対応語。
- 1970年代の環境問題を契機に国際的に普及し、日本では「持続可能な開発」と訳された歴史を持つ。
- 使用時には具体的根拠や行動を添え、日常生活でも小さな選択から実践できる点に留意する。
持続可能という言葉は、単なる長期継続を超え、経済・環境・社会の三側面を調和させながら未来へ責任を果たすという価値観を示しています。読み方や由来、歴史を理解すると、なぜ現代社会がこの概念を重視するのかがクリアになります。
また、類語・対義語・関連用語を把握することで文章表現の幅が広がり、ビジネスでも学術でも説得力を高められます。日常生活での実践は小さな行動から始まり、個人の選択が社会全体の変革へとつながることを意識しましょう。