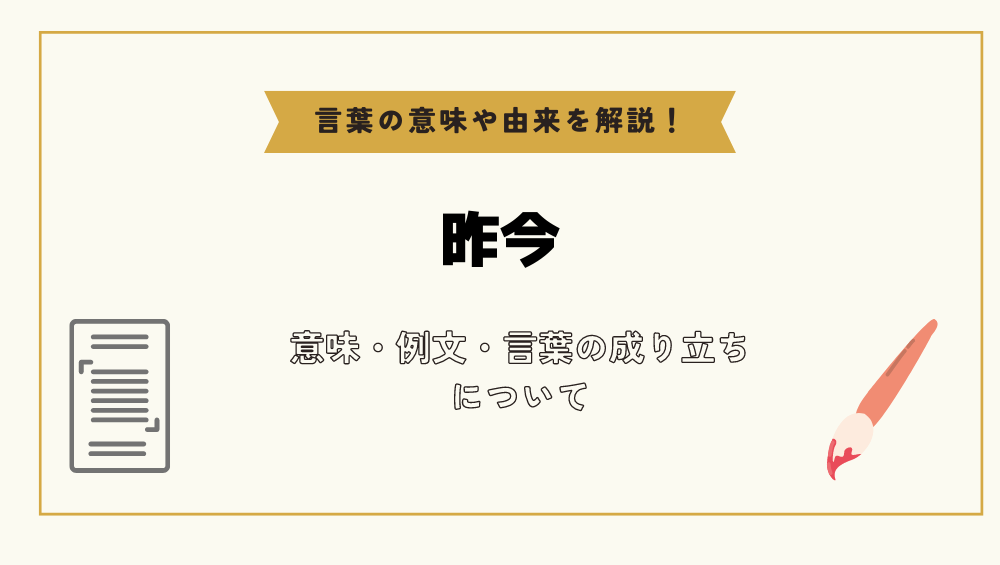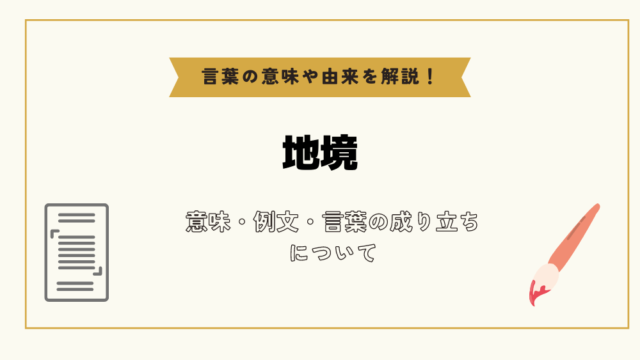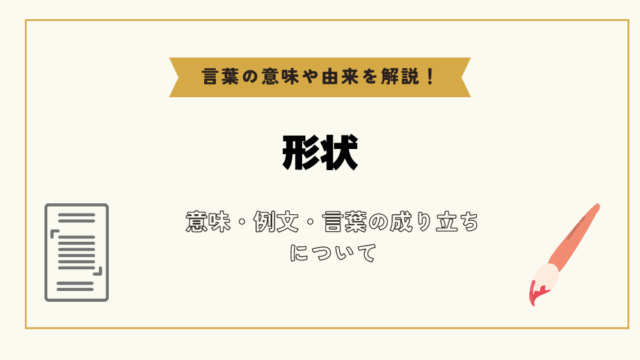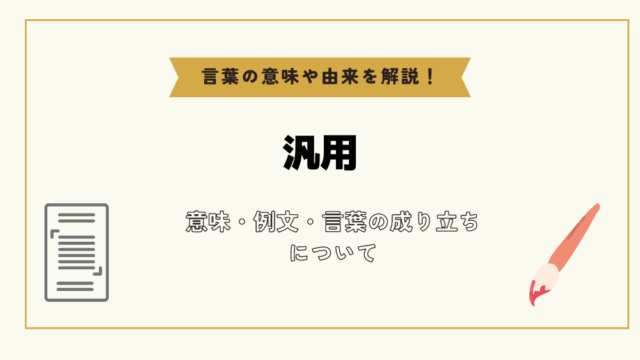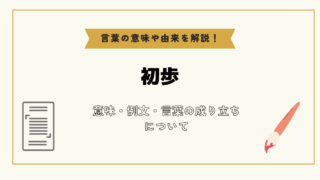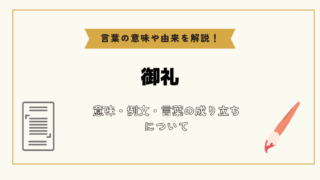「昨今」という言葉の意味を解説!
「昨今」は「ここ最近」「近ごろ」といった、ごく短い過去から現在に至る時期を示す副詞的名詞です。現代ではニュースやビジネス文書、評論などで頻繁に用いられ、「最近」とほぼ同義でありながら、やや硬い語感を伴います。口語よりも文語的なニュアンスが強いため、文章の調子を落ち着かせたい場面で重宝される語と言えます。期間的には数か月から数年程度を柔軟に指し、明確な日数や年数を限定しない点が特徴です。
「近年」との違いは「近年」が複数年のスパンを指す傾向が強いのに対し、「昨今」はより短いスパンを想起させる点にあります。
特定の年度や時代を明示せずとも、読者に「今この瞬間に関わる最近の動向」を端的に伝えられる便利な言葉です。対面の会話ではやや堅苦しく映ることもあるため、使う場面を選ぶと良いでしょう。
「昨今」の読み方はなんと読む?
「昨今」は「さっこん」と読みます。いずれの漢字も小学4年生で習う常用漢字ですが、熟語としての出現頻度がさほど高くないため、大人でも読み方に迷うことがあります。「昨」は「さく」と訓読みし、「昨日(さくじつ)」や「昨夜(さくや)」でおなじみの漢字です。「今」は「こん」と音読みするほか、「いま」と訓読みします。
読み誤りとして多いのが「さくこん」や「きのこん」です。意味を考えると「さく」と「こん」が結びついた読み方が自然ですが、音読みの連声変化で「く」が促音化し「さっこん」と発音する点がポイントです。
ビジネスシーンで誤読すると信頼性を損ねかねないため、メールやプレゼンの前に必ず「さっこん」と声に出して確認しておくと安心です。
「昨今」という言葉の使い方や例文を解説!
「昨今」は主に文頭や文中で副詞的に用い、「昨今、〜」「〜は昨今の課題だ」の形を取ります。内容としては社会的課題、経済状況、技術革新などのトピックを導入し、論旨を最近の流れと結びつける役割を果たします。
文章を引き締めつつ時事性を示せるため、レポートやニュース記事で非常に重宝されます。カジュアルな日常会話では「最近」に置き換える方が自然ですが、少しかしこまった席では「昨今」を使うと語調が整います。
【例文1】昨今、リモートワークの導入が急速に進んでいる。
【例文2】エネルギー価格の高騰は昨今の最重要テーマだ。
文末に「です・ます」をつける場合は「昨今では〜です」と接続すると滑らかに収まります。また、文中で名詞的に扱う際は「昨今の○○」「昨今における○○」の形が一般的です。
時期をぼかしつつ「いま話題の」というニュアンスを一言で示せる点こそ、「昨今」の最大の使いどころです。
「昨今」という言葉の成り立ちや由来について解説
「昨」には「きのう」「過ぎ去った日」の意があり、「今」は「現在」を指します。二字を合わせることで「過ぎ去ったばかりの時」と「いまこの時」を連結し、「直近の時期」を示す熟語が成立しました。
過去と現在が隣接している状態を一語で表した巧みな構成が「昨今」の語源的特徴です。中国古典には同一表記が見当たらず、日本で独自に成立した国字的熟語と考えられています。江戸期の文献にはまだ用例が少なく、明治期の新聞・雑誌の興隆とともに定着しました。
公文書や新聞記事では「最近」よりも客観性の高い語として選択され、時勢を論じる評論の定番語になりました。由来が比較的新しいため、古語辞典には掲載がない場合もありますが、国語辞典では「近い過去」「近年」と同義と説明されています。
国字として生み出された背景には、急激な文明開化の中で「過去と現在が地続きである状況」を手短に示したいニーズがあったと推測されます。
「昨今」という言葉の歴史
「昨今」が活字に初めて現れるのは明治10年代の新聞記事とされています。時事新報や朝日新聞の論説で「昨今、欧州の政情は混迷を極め」といった使い方が確認できます。
大正期には評論家・芥川龍之介など文学作品にも登場し、知識層の語彙として普及しました。戦後はマスメディアの発達に伴い、政治・経済の時評記事で定番表現になり現在に至ります。
昭和40年代以降の国語辞典ではほぼ全てに見出し語として掲載され、「昨今=最近」を示す標準語として定着しました。インターネット黎明期の1990年代後半にはオンラインニュースでも常用され、デジタル時代にも生き残った語です。
近年のコーパス調査では新聞・雑誌における頻度が依然高い一方、SNSでは「最近」が主流で「昨今」はややフォーマル寄りに位置付けられています。
150年足らずの歴史ながら、公的文書や専門誌に不可欠なワードとして独自の存在感を保ち続けています。
「昨今」の類語・同義語・言い換え表現
「昨今」と近い意味を持つ語には「最近」「近頃」「近年」「目下」「当今」などがあります。ニュアンスの違いを把握すれば文章の幅が広がります。
「最近」は口語でも文語でも万能に使える最も一般的な類語で、「昨今」よりも柔らかい印象があります。「近頃」はやや口語的で親しみやすく、会話やエッセーで好まれます。「近年」は5〜10年程度の比較的長いスパンを示し、統計や研究など長期的なデータを扱う場合に相性が良い表現です。
「目下(もっか)」は「今まさに」という切迫感を帯び、報告書やビジネスメールで「目下検討中」といった形で使われます。「当今(とうこん)」は古風な語で、伝統芸能や歴史書などで見かけます。
【例文1】近頃、気候変動の影響が身近に感じられる。
【例文2】目下、プロジェクトは最終段階に入っている。
文章のトーンに合わせて「昨今」「最近」「近年」を使い分けると、読者に与える印象が大きく変わります。
「昨今」の対義語・反対語
「昨今」は「直近の時期」を示すため、対義語は「過去の遠い時期」あるいは「未来の時期」を指す語になります。具体的には「往時(おうじ)」「往年」「昔日(せきじつ)」「将来」「未来」などが挙げられます。
「往時」「往年」は過ぎ去った時代を懐かしむニュアンスが強く、「昨今」と対照的に用いると時間的なコントラストを鮮明にできます。「将来」や「未来」は時間軸の前方を示し、社会課題を議論する際に「昨今の課題と将来の展望」などの対比がよく見られます。
【例文1】往年のスターも昨今はメディア出演が減った。
【例文2】昨今の技術革新を踏まえ、将来の働き方を考える。
反対語を意識して配置すると文章が立体的になり、論旨が明快になります。
「昨今」と「往時」「将来」をセットで使うことで、時間軸全体を俯瞰した説得力の高い文章が完成します。
「昨今」についてよくある誤解と正しい理解
「昨今=昨日と今日」という誤解がありますが、実際には数か月〜数年程度の幅広い期間を指します。日付が限定されていないため、「昨晩」「昨年」と混同しないよう注意しましょう。
また、「昨今」を多用すると古臭いという声もありますが、フォーマル文書ではむしろ適切な語として評価されています。口語での多用は堅苦しく感じられる場合がありますが、書き言葉では時事性を示す最適語です。
別の誤解として「昨今=現代全体」と解されることがありますが、歴史的な長期スパンでは「現代」「当代」が適切です。「昨今」はあくまでも短期的な最近を示します。
【例文1】昨今は江戸時代全体を指すわけではない。
【例文2】昨今というだけで昨日と今日だけを示すわけでもない。
正しくは「昨今=ごく近い過去から現在にかけて」の意味であり、期間の長短よりも「時事的な話題」を示唆する語として理解することが重要です。
「昨今」を日常生活で活用する方法
ビジネスメールでは冒頭の挨拶として「昨今、業界を取り巻く環境は大きく変化しております」という一文を入れると、課題提起がスムーズに行えます。
プレゼン資料では章タイトルやスライド見出しに「昨今の市場動向」と入れるだけで、聴衆に「最新情報が語られる」期待を抱かせられます。パーティーやスピーチでも「昨今の○○事情」というフレーズは硬すぎず、適度に改まった印象を与えられます。
ライフログや日記では「最近」を使う場面が多いものの、「昨今」をあえて用いることで文体にバリエーションが生まれます。
【例文1】昨今、子どもの読書離れが問題視されている。
【例文2】昨今の円安傾向を踏まえ、海外旅行の計画を見直した。
「昨今」は少量の堅さを文章に加え、説得力を高めるスパイスのような存在として活用できます。
「昨今」という言葉についてまとめ
- 「昨今」は「ごく近い過去から現在にかけて」を示す副詞的名詞。
- 読み方は「さっこん」で、促音化に注意。
- 明治期に登場し、公文書や報道で定着した国字的熟語。
- フォーマルな文章で「最近」を置き換える際に便利だが、口語では堅く映る点に注意。
「昨今」は短いフレーズで時事性を伝えられる便利な語であり、硬すぎず柔らかすぎない絶妙な立ち位置が魅力です。読み方の「さっこん」を押さえ、類語や対義語とのニュアンス差を理解すれば、ビジネス文書からブログ記事まで幅広く応用できます。
明治以降の日本語における歴史は比較的浅いものの、新聞・雑誌・行政文書で培われた信頼感は揺るぎません。適切な場面で使いこなすことで、文章全体に落ち着きと説得力を与えられるでしょう。