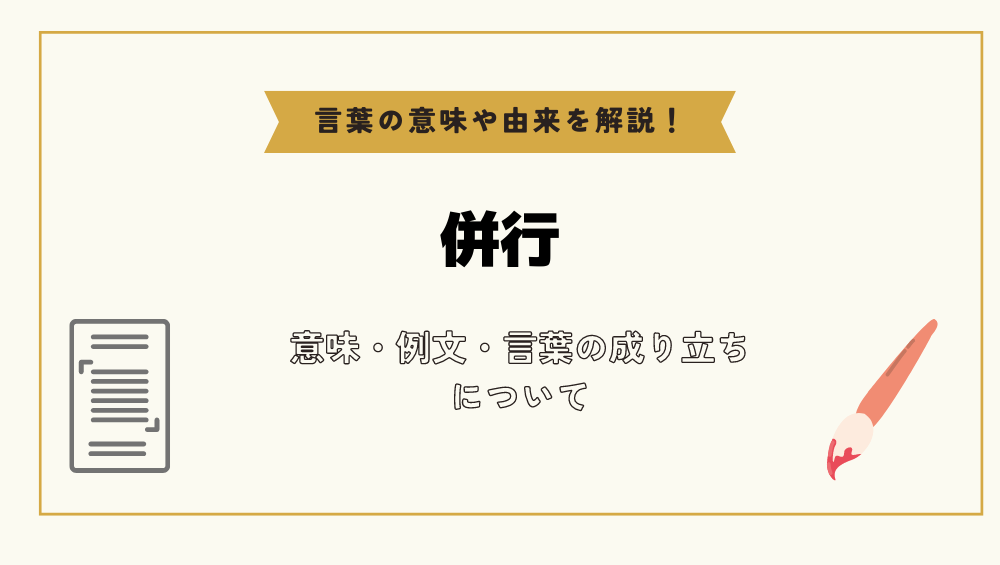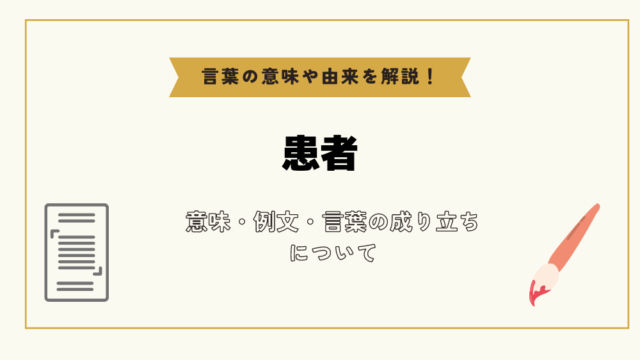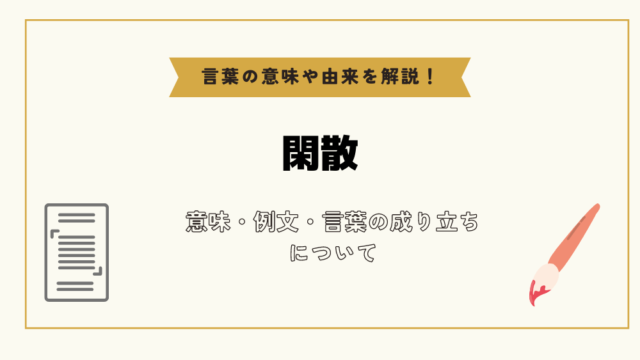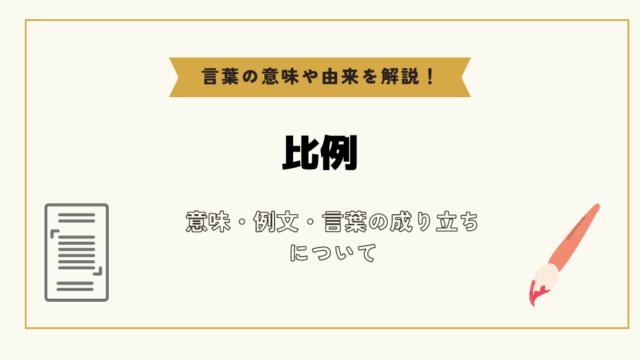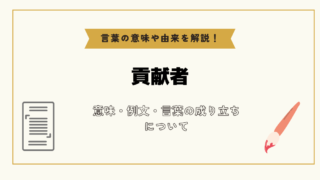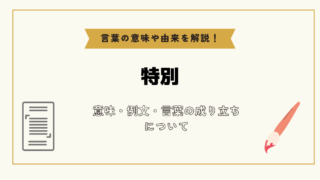「併行」という言葉の意味を解説!
「併行」とは、二つ以上の物事を同時進行させたり、同じ方向に並んで進ませたりする状態を指す言葉です。
日常的には「複数の作業を併行して進める」「二つの道路が併行して走る」といった使い方が見られます。
「併行」の対象は作業・計画・道路・工程など幅広く、物理的な並びだけでなく、抽象的なプロジェクトの同時進行も含みます。
「併行」は「並行」と混同されがちですが、意味の焦点が異なります。
「並行」は文字どおり平行線のように同じ方向に進むイメージが強く、空間的な並びを示すことが多いです。
一方、「併行」は“合わせて行う”ニュアンスが濃く、時間的な同時進行にも広く使われます。
法律文書や行政文書では「併行」の方が採用されるケースがあり、「並行」よりも行為性を伴う言葉として扱われています。
そのため、企画書や報告書で時間軸上の同時性を強調したい場合は「併行」を選ぶと意図が伝わりやすいです。
「併行」の読み方はなんと読む?
「併行」は一般に「へいこう」と読みます。
漢字の構成は「併(あわ)せる」「行(こう)」で、合わせて行うイメージがそのまま発音に現れています。
「併」を単独で読む場合には「へい」「あわ(せる)」など複数の音訓がありますが、「併行」においては音読みの「へい」で固定です。
同音異義語としては「並行(へいこう)」「平衡(へいこう)」「閉口(へいこう)」などが存在するため、文脈で判別する必要があります。
音声入力や読み上げソフトでは同音語を誤変換しやすいので、「併行作業」と入力する際は確認を怠らないのがコツです。
話し言葉での誤解を防ぐには「併せて進めるの併行です」と補足すると、意味が伝わりやすくなります。
「併行」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方のポイントは「同時進行」または「並んで進む」二つのニュアンスを場面に応じて選ぶことです。
仕事ではタスク管理、学習では複数科目の勉強、生活面では家事と育児など、同時に動く要素がある場面で頻繁に用いられます。
【例文1】新規開発と保守作業を併行して進める。
【例文2】高速道路と旧道が川沿いに併行している。
専門書や業務マニュアルで「併行して実施」と書かれている場合、優先順位を示すものではなく「同じタイミングで行う」指示です。
計画表に併行工程をリストアップする際は、作業者の負荷やリソースの重複に注意すると効率的です。
誤用として「併行を立てる」「併行性が高い」など形容詞的に使う例がありますが、正しくは「併行して〜する」「併行して〜が存在する」と動詞や動作に寄せて使います。
「併行」という言葉の成り立ちや由来について解説
「併」と「行」という二文字の組み合わせが、「共に」「進む」を示して結合した熟語が「併行」です。
「併」は古代中国の漢籍で「合わせる」「同時に成す」を意味し、「行」は「進む」「実行する」を示す基本漢字です。
六朝時代の法律文書や兵法書には「併行」の原形とみられる用例があり、軍隊の戦線を同時に展開する意味で使われました。
日本へは奈良時代に漢籍とともに伝わり、律令制度下の行政用語として「二事併行」などの形で見られるようになります。
江戸期の藩政資料では工事や年貢集計を「併行」させる記述が散見され、近代以降の官庁文書でも継承されました。
由来を知ることで、現代のビジネスシーンにおいても“複数施策を並列で動かす”という語感が歴史的に裏付けられているとわかります。
「併行」という言葉の歴史
「併行」は律令期から現代へ至るまで、法制・行政・軍事の分野で連綿と使われ続けてきた歴史があります。
平安期の『延喜式』には、祭礼準備と政務を「併行して務む」との記述が存在します。
戦国時代の軍記物にも「兵糧輸送を軍勢と併行して急がしむ」と見られ、戦術的同時性を示していました。
明治維新後、西欧の“parallel”や“simultaneous”の訳語として再評価され、法律・鉄道・土木の専門用語に定着しました。
昭和期には製造業の工程管理で「併行工程」という語がマニュアルに記載され、高度経済成長とともに一般企業でも普及します。
現代ではIT分野で「併行処理」や「併行開発」という形でさらに派生し、システム開発手法やプログラム実行モデルなどに応用されています。
このように歴史をたどると、「併行」は常に時代の先端技術や組織運営とともに発展してきた用語であることがわかります。
「併行」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「並行」「同時進行」「平行移動」「パラレル」などが挙げられます。
「並行」は空間的な平行線を基点とした言葉で、抽象度が近いが物理的ニュアンスがやや強めです。
「同時進行」は時間的同一性をストレートに示し、工程管理や放送業界でよく用いられます。
【例文1】設計と試作を同時進行でこなす。
【例文2】二社をパラレルで比較検討する。
IT分野では英語の「parallel」をそのままカタカナで用いることが多く、学術論文では「並列(へいれつ)」と訳される場合もあります。
文脈によっては「協調」「複合」「同時」も類語として使えますが、対象の動きが別々の軸上で進んでいるかを意識して選びましょう。
「併行」の対義語・反対語
明確な対義語は「順次」や「直列」など、物事を一つずつ行う状態を示す言葉です。
「順次」は手順どおりに次々と進める様子、「直列」は電気回路由来で“線上に一列”の概念を持ち、いずれも同時進行とは対極に位置します。
【例文1】工程を直列に組むことで品質を安定させる。
【例文2】順次対応では納期に間に合わない。
IT業界では「シリアル(serial)」が並列処理(parallel processing)の対義語となり、コンピュータのアーキテクチャ文脈で使われます。
教育現場では複数の科目を「併行して学ぶ」か「順次学ぶ」かでカリキュラム設計が変わるため、両者の違いは極めて実用的です。
「併行」についてよくある誤解と正しい理解
最も多い誤解は「併行」と「並行」が完全に同義だと思われている点です。
確かに意味は近いものの、漢字が示すニュアンスの差異を意識すると文章表現がぐっと精密になります。
誤解①:「併行」は道路など空間的並びにしか使えない。
→「併行処理」「併行学習」など時間軸を含む場面でも正しく使えます。
誤解②:「併行」は古語で現代では使わない。
→現在も法令集や業務マニュアルに頻出し、むしろビジネス用語として現役です。
【例文1】プロジェクトAとBを併行して進めます。
【例文2】複数の検査工程を併行化し、リードタイムを短縮する。
正しい理解には、文章中で同時性と協調性を示すかどうかで判断するクセをつけると誤用を防げます。
「併行」という言葉についてまとめ
- 「併行」は複数の物事を同時に進めたり、並んで進ませたりする状態を示す語。
- 読み方は「へいこう」で、「併」「行」の組み合わせが意味を支える表記が基本。
- 律令期から行政・軍事で用いられ、近代以降は工程管理やIT分野へ拡大した歴史を持つ。
- 「併行」と「並行」のニュアンス差に注意し、同時性を強調したい場面で使うと効果的。
併行という言葉は、同時進行と並列性の両面をバランス良く表現できる便利な日本語です。
読み方は「へいこう」で固定され、文章表現では「併行して〜する」という形で活用すると意味が明確になります。
歴史的には律令期から連綿と使われ、現代ではITや製造業の「併行開発」「併行処理」など、より専門的な領域にまで広がっています。
「並行」との意味差を意識しながら使い分けることで、レポートや企画書の精度が高まり、読み手へ伝えたいニュアンスが過不足なく届きます。