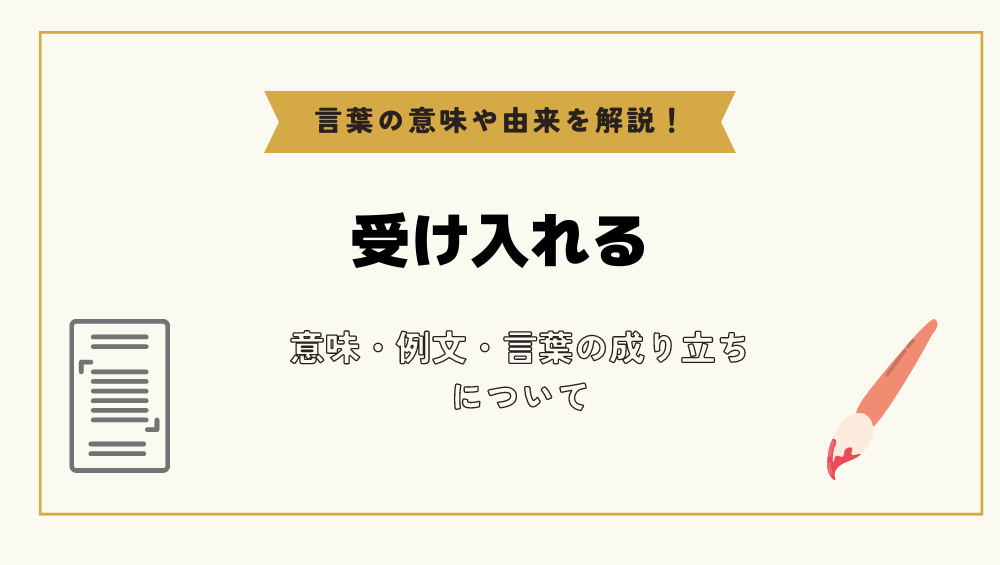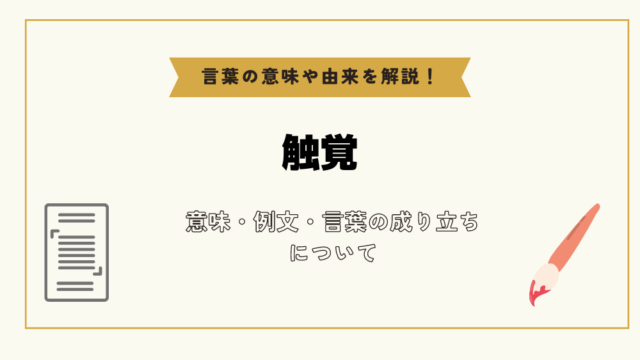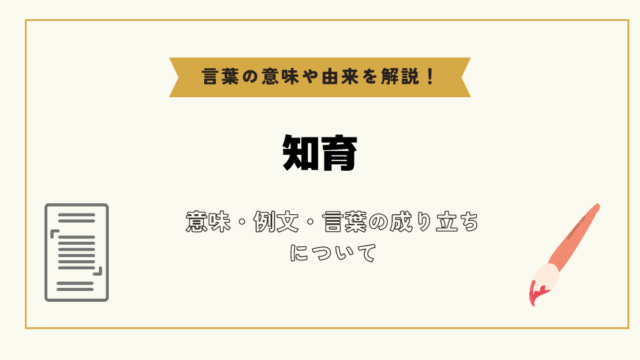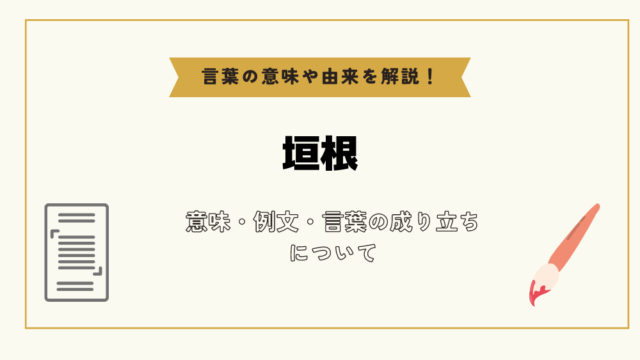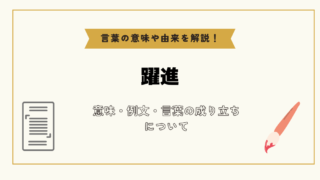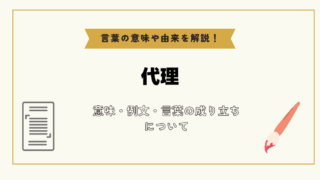「受け入れる」という言葉の意味を解説!
「受け入れる」とは、相手から差し出された物事・意見・状況などを拒まずに自分のものとして取り込む行為を指します。この語は「受ける」と「入れる」の二語が結合しており、まず相手の働きかけを「受け」、さらに自分の内部や領域に「入れる」という二段階のニュアンスが込められています。物理的な品物だけでなく、提案・感情・文化など無形のものにも幅広く使えるのが特徴です。ビジネス文書から日常会話まで用途が広く、柔軟さや寛容さを表す言葉として定着しています。
多くの場合、「受け入れる」はポジティブな協調姿勢を示しますが、単に従うのではなく「理解し納得したうえで取り込む」点が重要です。そのため、自己責任や主体性と結び付くケースも少なくありません。「受け入れる姿勢が成長を促す」「現状を受け入れることで次の一歩を踏み出す」など、心理学や自己啓発の文脈でも頻出する語です。
反面、安易な妥協と混同される場合があるため注意が必要です。「受け入れる」ことは相手に合わせて自己を消すことではありません。あくまでも情報を吟味し、必要に応じて選択・採用するプロセスを含みます。
最後に、社会的な場面では「キャパシティ(容量)」のニュアンスも帯び、「収容人数を受け入れる」「移転を受け入れる自治体」など数量・規模を受動的に示す使い方も広がっています。
要するに「受け入れる」は、主体的に納得しつつ外部要素を自分の内部へ取り込むという、能動と受動が同居した奥深い日本語です。
「受け入れる」の読み方はなんと読む?
「受け入れる」の正しい読み方は「うけいれる」です。全てひらがなで書く場合は「うけいれる」、漢字かな混じりなら「受け入れる」と表記します。
読みのポイントは「け」と「いえ」の母音連続部分で、口を開けっぱなしにせず軽く区切ると自然な発音になります。音声学的には五拍「ウ・ケ・イ・レ・ル」と分けて発声すると滑らかです。
ビジネスや公的文書では漢字表記が一般的ですが、子ども向け教材や口語的な文章ではひらがな表記もよく使われます。送り仮名の「れる」は下一段活用の未然形で、尊敬や受身の助動詞ではなく動詞本体の一部です。
誤読として「うけいられる」が挙がりますが、「いられる」は可能や受身の助動詞を連想させるため別語になります。辞書を引く際は「うけいれる(受け入れる)」の一語で収録されていることを確認すると良いでしょう。
日本語学習者に教える場合、ひらがなと漢字の対応関係を示しながら拍数で示すと習得がスムーズになります。
「受け入れる」という言葉の使い方や例文を解説!
「受け入れる」は〈物・情報・感情・人〉を主語が取り込むときに使用します。主に「Aを受け入れる」という形で目的語を前に置き、動詞自体が他動詞である点がポイントです。
【例文1】新しいアイデアを柔軟に受け入れる。
【例文2】転校生を温かく受け入れる。
これらの例文は対象が有形・無形を問わない汎用性を示しています。
文脈に応じて「受け入れられる」「受け入れてもらう」など受身・使役形に活用でき、自他の立場を切り替えやすい利点があります。敬語表現としては「受け入れてくださる」「お受け入れいただく」のように丁重語や謙譲語を組み合わせます。
注意点として、単なる「受ける」や「許可する」と混同しやすい場面があります。たとえば「申請を受け入れる」は「内容を認め採択する」意味になり、「申請を受け付ける」(書類を受領する)とは異なります。意図を明確にするため、後続語句で結果を補足すると誤解を防げます。
さらに心理的文脈では「自分の弱さを受け入れる」「現実を受け入れる」のように、自己対象に使うと内省を促す効果があります。
「受け入れる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「受け入れる」は古くからある和語「受く」と「入る」の複合から派生しました。「受く」は奈良時代の『万葉集』でも確認できる語で、「授かる・引き取る」の意がありました。一方「入る」は空間的移動を示す基本動詞です。
平安期には二語を連続させた形「受け入れ」が文献に見られ、のちに動詞活用部分が付加されて「受け入る → 受け入れる」へ変化したと考えられています。室町・江戸期の書簡や日記では、物資や使者を迎え入れる意味で頻出しました。
当初は主に物理的な「搬入・収容」を表す語でしたが、明治以降の近代化に伴い「思想・制度を受け入れる」といった抽象的用法が急増します。西洋文化の導入期に、翻訳語として「accept」の訳に当てられたことが拡大の契機です。
漢字表記の定着は大正期の国定教科書による影響が大きく、以降は現代まで「受け入れる」の三字を基本形として使われています。発音や活用の変化はほとんどなく、安定した語形を保っている点が興味深いところです。
「受け入れる」という言葉の歴史
古代:『万葉集』では「受く」と「入る」が独立して登場し、接続的に連ねて使われていましたが、複合語としては確認されていません。
中世:鎌倉後期の『徒然草』や室町期の「連歌」資料に「受け入れ」形で出現します。これは武家社会で客人や人材を迎え入れる実務用語として普及したと考えられます。
近世:江戸時代には大名家が参勤交代で「人馬を受け入れる」など宿泊・物資調達の文脈で多用され、行政用語へも定着しました。町年寄の記録には「米穀を受入れ候」などの記述があります。
近代:文明開化に伴い、大量の外来語・制度を「受け入れる」必要が生じました。新聞や官報に「外債を受け入れる」「法律を受け入れる」が頻発し、抽象概念を取り込む語として拡張しました。
現代:情報化・国際化が進む中で、ダイバーシティやインクルージョンを示すキーワードとしても注目されています。企業の人材方針や自治体の移住促進など、共生社会を語る際の重要語となりました。
「受け入れる」の類語・同義語・言い換え表現
「受け入れる」と似た意味を持つ語には「受諾する」「了承する」「引き受ける」「承認する」「容認する」「採用する」などがあります。
ニュアンスの違いを把握すると、場面に応じた言い換えがスムーズになります。たとえば「受諾する」は公的・正式な提案に同意する丁重な言い回しで、契約書や通知文に適します。「了承する」は内容を理解し問題ないと認める意味合いが強く、ビジネスメールでよく使われます。
「引き受ける」は責任を伴って仕事などを担当する意味が中心です。「承認する」は上位者が正式に認める意味、「容認する」は本意ではないが許容するニュアンスを帯びます。「採用する」は複数案から選び取る選択性が際立ちます。
類語を用いた言い換えは文体の硬さや距離感を調整できる便利なテクニックです。場面のフォーマリティや主語の立場を考慮して選ぶと文章の説得力が増します。
「受け入れる」の対義語・反対語
「受け入れる」の対義語は「拒む」「拒否する」「拒絶する」「排除する」「突っぱねる」などです。
ポイントは、外部からの働きかけを自分の領域に入れない姿勢を示す言葉である点です。たとえば「要求を拒否する」は提案を断る強い意思を表し、「排除する」は物理的・社会的に遠ざけるニュアンスを含みます。
ビジネスでは「不採用」「辞退」「保留」などが機能的な反対語として挙がりますが、情緒的な距離感を示すなら「心を閉ざす」「受け止めない」など表現が広がります。
文章で使い分ける際は、否定の強さや相手への配慮を鑑みて選択することが大切です。強い拒絶は対立を深める恐れがあるため、目的に応じて程度を調整しましょう。
「受け入れる」を日常生活で活用する方法
日常生活では、家族や友人の意見を「受け入れる」ことでコミュニケーションが円滑になります。相手の言葉を最後まで聞き、自分の価値観と照らし合わせて咀嚼する姿勢がポイントです。
心理学では「自己受容(セルフアクセプタンス)」が精神的健康に直結するとされ、まず自分自身を受け入れることが人間関係の土台になると説かれています。ネガティブな感情を否定せず、「今そう感じている自分」を認めるだけでもストレスが減少するという研究結果があります。
また、異文化交流の場面では、習慣や食文化を受け入れることで理解が深まり、トラブルを未然に防げます。例えば海外旅行で現地ルールに合わせる姿勢は安全面でも重要です。
ビジネスシーンでは、部下からの提案を受け入れる「ボトムアップ型マネジメント」が注目されています。組織の多様な視点を取り込むことでイノベーションが促進されるためです。
生活全般で「受け入れる力」を高めるには、①相手の立場を想像する②判断を急がず事実を集める③感情と言動を切り分ける、などのステップを意識すると効果的です。
「受け入れる」についてよくある誤解と正しい理解
誤解1:「受け入れる=従う」と思われがちですが、実際は主体的な選択行為です。納得せずに従う場合は「従属」「服従」に近く、本来の意味とは異なります。
誤解2:「受け入れると自分の意見を失う」という懸念がありますが、相手を理解したうえで自分の考えを保持することは可能です。
正しい理解では、受け入れる行為は対話を通じて視野を広げ、自他の立場を尊重するプロセスとされます。自らの軸がないと流されやすい点も事実なので、自己理解とセットで行うとバランスが取れます。
誤解3:「何でも受け入れると損をする」という声もありますが、境界線を設定すればリスクは減らせます。自分の価値観を明確にし、同意できない点は率直に伝えることで健全な関係を維持できます。
心理的安全性の観点では、組織内で多様な意見を受け入れる文化がイノベーションを生みやすいと実証されています。つまり、適切な「受け入れ」は個人と組織の双方に利益をもたらします。
「受け入れる」という言葉についてまとめ
- 「受け入れる」は外部の物事を主体的に取り込み、納得のうえで承認する行為を示す語。
- 読み方は「うけいれる」で、漢字かな混じり表記が一般的。
- 奈良期の「受く」と「入る」から派生し、近代に抽象的用法が拡大した歴史を持つ。
- 使い方の幅が広く、自己受容からビジネス交渉まで現代生活で重要なキーワードとなる。
「受け入れる」は、相手や状況を尊重しながら自分の内側に取り込む柔軟な姿勢を表す言葉です。読み方は「うけいれる」で統一されており、文章では漢字表記が推奨されます。
歴史的には物理的搬入を示す語から始まり、外来文化や思想を取り込む過程で意味が拡張しました。現代ではダイバーシティや自己受容を語る際の中心語となり、多分野で欠かせない存在です。
使い方のコツは「安易な妥協」との線引きを明確にし、納得のプロセスを経て決断することです。これにより、対人関係の信頼構築や自己成長の礎として機能します。
今後も社会の多様化が進むにつれ、「受け入れる」という行為とその言葉はより一層重要度を増すでしょう。