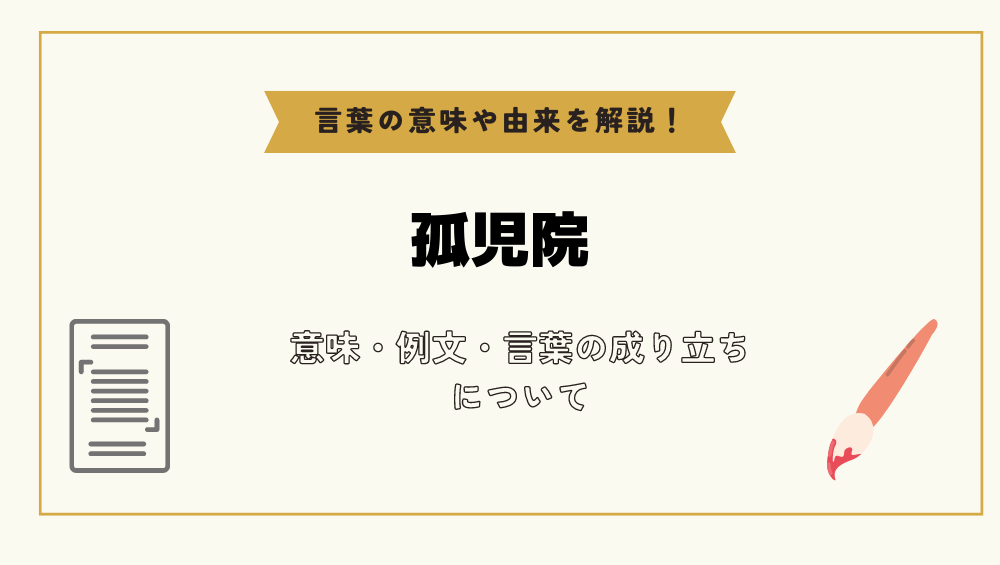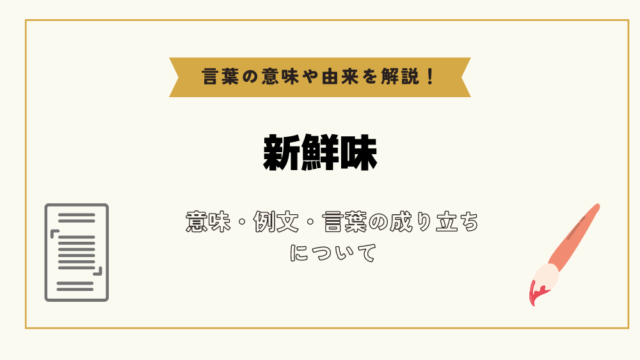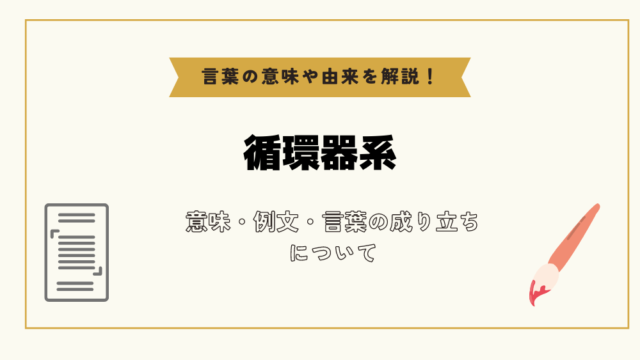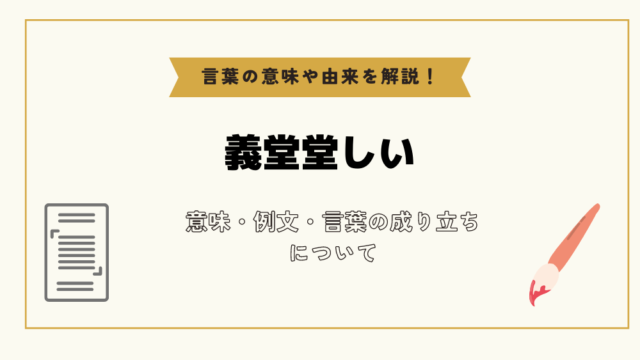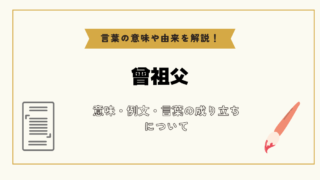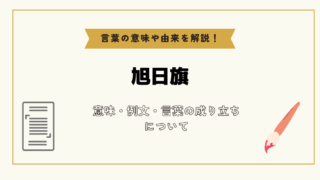Contents
「孤児院」という言葉の意味を解説!
「孤児院」とは、親との別れや失踪、または親の死などによって親の愛情や保護を受けられなくなった子供たちが、居場所やケアを提供される施設のことを指します。
孤児院では、食事や寝床、学習環境の提供だけでなく、心のケアや社会生活の指導なども行われています。
その目的は、子供たちが健やかに成長し、幸せな未来を迎えるための基盤を作ることです。
「孤児院」という言葉の読み方はなんと読む?
「孤児院」という言葉は、「こじいん」と読みます。
日本語の発音ルールに基づいて読むと、「こしいん」となる可能性もありますが、一般的には「こじいん」と読まれることが多いです。
「孤児院」という言葉の使い方や例文を解説!
「孤児院」という言葉は、子供たちが安心して生活できるような環境を提供する施設を指す言葉です。
例えば、「この地域では孤児院が数多く運営されています」というように使われます。
また、「私は孤児院でのボランティア活動をしている」というように、孤児院に関連する活動や事柄を説明する際にも使います。
「孤児院」という言葉の成り立ちや由来について解説
「孤児院」という言葉は、日本語の漢字で構成されています。
「孤」という字は、親と離れてひとりぼっちであることを表し、「児」という字は子供を指しています。
「院」は施設の意味です。
こうした漢字の組み合わせによって、親の愛情や保護を失った子供たちが集まる施設であることが表現されています。
「孤児院」という言葉の歴史
「孤児院」という施設は、江戸時代から存在していましたが、それほど広く知られているものではありませんでした。
明治時代になり、社会の変化や産業化の進展によって、孤児や貧困に苦しむ子供たちの問題が深刻化しました。
この時期になって孤児院の必要性が再評価され、私設や宗教団体などによって孤児院が設立されるようになりました。
「孤児院」という言葉についてまとめ
「孤児院」という言葉は、親の愛情や保護を失った子供たちが居場所やケアを受ける施設を指します。
日本語の読み方は「こじいん」と読まれることが一般的です。
この言葉は、子供たちが安心して生活できるような環境を提供する施設や関連する活動を表現する際に使用されます。
成り立ちや歴史についても知ることで、孤児院の存在と役割について理解を深めることができます。