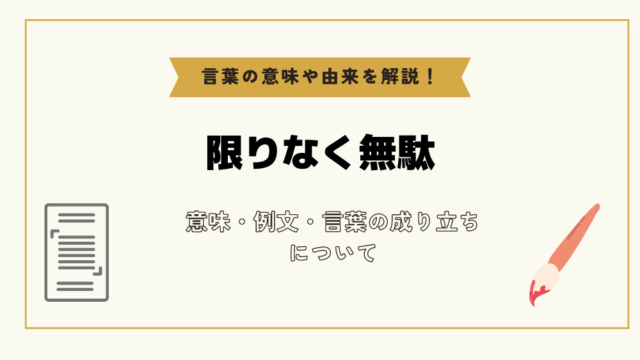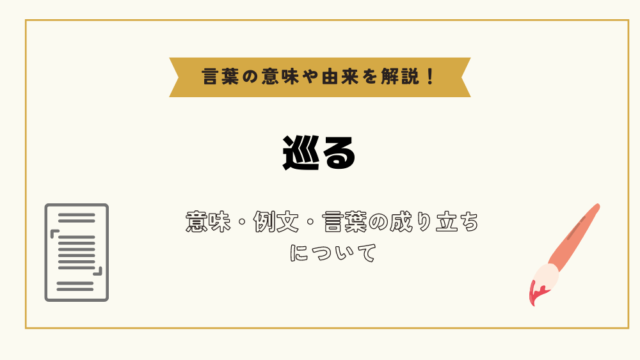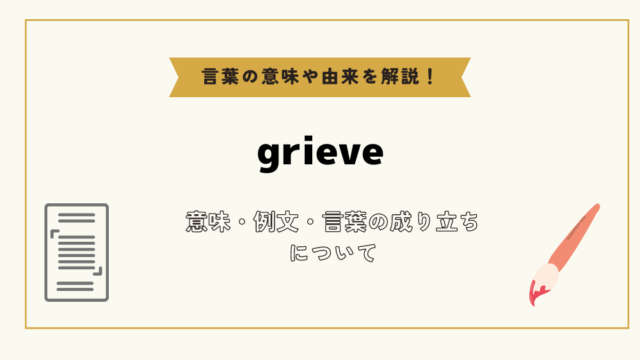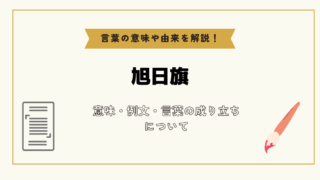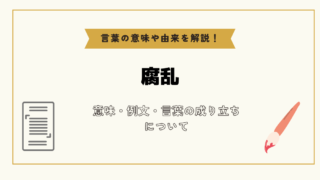Contents
「舞妓」という言葉の意味を解説!
「舞妓」という言葉は、日本の伝統的な芸者の一種を指す言葉です。
舞妓は、京都を中心に活動しており、日本の文化を代表する存在として知られています。
彼女たちは、舞踊や音楽、茶道などの伝統的な芸術の修行をし、美しい芸を披露することが役割です。
「舞妓」の読み方はなんと読む?
「舞妓」は、「まいこ」と読みます。
日本語の読み方では、「舞」は「まい」と読み、「妓」は「こ」と読みます。
この読み方には、舞妓の華やかな踊りや美しさが表現されています。
「舞妓」という言葉の使い方や例文を解説!
「舞妓」という言葉は、一般的にそのまま使われることが多く、特別な言い回しや例文はありません。
例えば、「彼女は舞妓になる夢を持っています」といった形で使われます。
「舞妓」という言葉の成り立ちや由来について解説
「舞妓」という言葉は、江戸時代の中期ごろから使われ始めた言葉です。
当時、舞妓は遊女や芸娼妓とは異なり、芸事を専門に行う存在でした。
舞妓は、身体を使った美しい舞踊や音楽の演奏によって、人々に楽しみと感動を与えていました。
「舞妓」という言葉の歴史
「舞妓」という言葉の歴史は古く、平安時代以前から存在していました。
当時は貴族の間で遊興の一環として舞妓が活躍しており、社交の場で優雅な舞を披露していました。
その後、江戸時代になると、舞妓は庶民の間でも人気となり、現在の舞妓の基盤が築かれていきました。
「舞妓」という言葉についてまとめ
「舞妓」という言葉は、古くから日本の伝統芸能として継承されてきました。
彼女たちは華やかな衣装を身にまとい、美しい舞踊や音楽の演奏を通じて、人々に楽しみを提供してきました。
今でも京都では多くの舞妓が活動しており、伝統と新しい文化の融合が進んでいます。