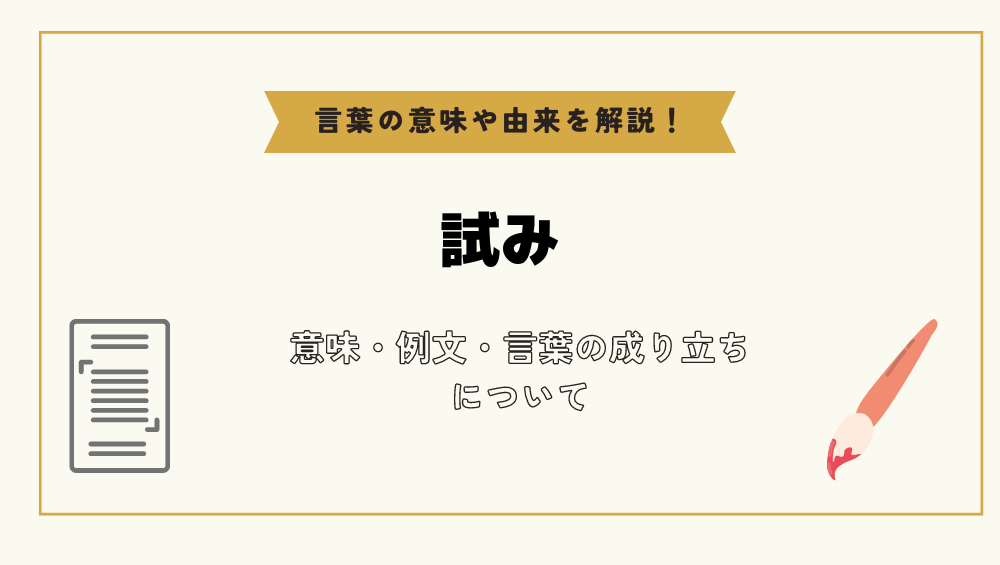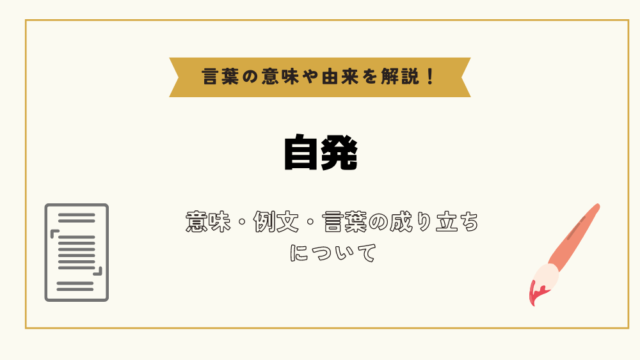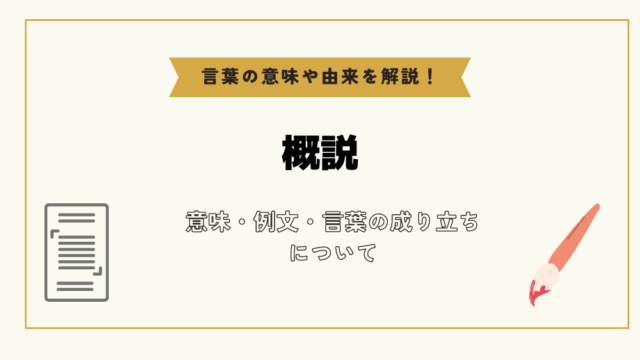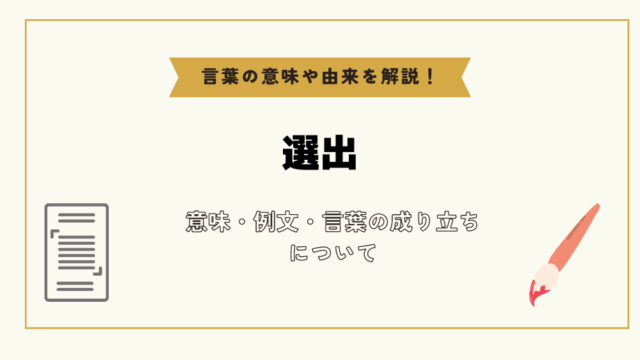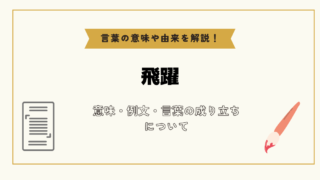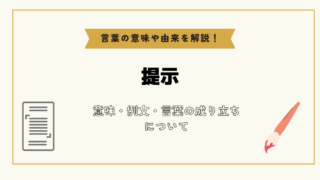「試み」という言葉の意味を解説!
「試み」とは、ある目的を達成するために方法や行動を実際に行ってみること、またはその行動自体を指す言葉です。結果が未確定である点が特徴で、成功しても失敗しても「試み」に含まれます。ビジネスシーンでは「新規事業の試み」、日常生活では「早起きの試み」のように幅広く使われます。
多くの場合、未知の領域への挑戦や改善の意図をはらみます。「テスト」「チャレンジ」と訳されることもありますが、ニュアンスとしては「目的達成のための具体的行動」に軸足を置いている点が異なります。
また、「試み」には評価や結論を急がず、まずは動いて確かめる態度が内包されています。このため、教育や研究、芸術など探索的な分野で重視される概念といえます。
「試み」の読み方はなんと読む?
「試み」は一般に「こころみ」と読みます。他の読み方はなく、音読み・訓読みの混合語でもありません。
「試」は「こころ‐みる」と訓読みする漢字で、動詞形「試みる(こころみる)」も日常的に用いられます。「試み」を「ためし」と誤読するケースがありますが、この場合は「試し」という別語なので注意が必要です。
送り仮名を省いた名詞形が「試み」、送り仮名を付けた動詞形が「試みる」である点を覚えておくと混乱しにくいです。
「試み」という言葉の使い方や例文を解説!
「試み」は名詞としても動詞としても活用できます。名詞の場合は「~の試み」「試みとして」と後ろに助詞や体言が続きやすいです。動詞の場合は「試みる」「試みれば」など活用形が豊富で、文章の主語や時制に合わせて変化させられます。
結果よりも行動自体に重心があるため、成功が前提の文脈とは相性が良くない場合があります。たとえば「確実に成功する試み」と書くとやや矛盾した響きになります。
【例文1】新しい配送ルートを導入する試みが始まった。
【例文2】休日に早起きを試みたが、結局二度寝してしまった。
【注意点】名詞「試み」を動詞化したい場合は「試みる」と送り仮名を付ける。
「試み」という言葉の成り立ちや由来について解説
「試」という漢字は「言」と「式」に由来し、もともと「祈祷の言葉を唱えて結果を占う」ことを指していました。そこから「試す」「ためす」の意味が派生し、平安時代には「こころみ」という訓読みが一般化しました。
「試み」は、結果を占う宗教行為から「結果を待つ行動」へと意味が広がった代表例です。この変遷により、現代では宗教的ニュアンスが薄れ、学問・産業・日常生活へと用途が拡大しました。
「み」は名詞化接尾辞で、「こころみる」という動詞の語幹「こころみ」に対応する形で定着しました。文献上では『枕草子』や『徒然草』など古典作品にも出現し、長い歴史を持つ語彙です。
「試み」という言葉の歴史
古代日本では「占い」や「験(しるし)」としての試みが主流でしたが、鎌倉以降の武士社会で軍事的な「戦の試み」が登場します。室町期には芸能や茶道で「新たな手前(てまえ)の試み」が記録され、文化面でも重要語になりました。
近代以降、科学実験や産業革命の波とともに「試み」は「実験」や「プロトタイプ」の意味合いを帯び、技術革新のキーワードとして定着しました。戦後の高度経済成長期には企業の開発部門で日常的に用いられるようになり、現在ではIT分野の「PoC(概念実証)」とほぼ同義に扱われることもあります。
このように「試み」の歴史は、社会の変化とともに対象領域が拡大し続けてきた歩みそのものです。
「試み」の類語・同義語・言い換え表現
「試み」と近い意味を持つ日本語には「挑戦」「実験」「試行」「トライ」「挑戦」「取り組み」などがあります。「試行錯誤」という熟語は、複数の「試み」を重ねる過程を示す代表例です。
ただし「挑戦」は闘志や困難さを強調し、「実験」は科学的手続きを示す点で微妙にニュアンスが異なります。言い換えを行う際は、目的や文脈に最も合致する語を選ぶことが大切です。
英語では「attempt」「trial」「experiment」などが対応しますが、ニュアンスの幅は日本語と同様に多彩です。
「試み」を日常生活で活用する方法
家計の見直し、健康管理、学習計画など身近なテーマで「試み」を取り入れると、目標達成までのプロセスを柔軟に調整できます。
ポイントは「結果を急がず小さく始める」ことです。たとえば毎日5分だけストレッチを試み、継続できたら10分に延ばすなど段階的に設定すると成功体験を積みやすくなります。
【例文1】朝のSNS閲覧をやめる試みとして、目覚ましを別室に置いた。
【例文2】週1回の菜食デーを家族で試みて、食費と健康状態を比較した。
注意点は、結果が芳しくない場合でも「失敗」と断定せず、データとして次の行動に活かす姿勢を保つことです。
「試み」についてよくある誤解と正しい理解
「試み=成功しなければ意味がない」と考える人がいますが、これは誤解です。試みの本質は「動いて確かめる」ことにあります。失敗しても経験値やデータが残れば、それ自体が成果といえます。
また、「試みれば必ずしも改善するわけではない」という現実も見落とされがちです。不適切な方法を続ければ逆効果になる可能性もあります。
【注意点】強制された試みはモチベーションが下がり、結果の解釈も歪みやすい。主体性を保つことが成功率を高める鍵です。
「試み」という言葉についてまとめ
- 「試み」とは、目的達成のために実際に行動して結果を確かめることを指す言葉。
- 読み方は「こころみ」で、動詞形は「試みる」。
- 古代の占い行為から派生し、近代以降は科学・産業分野へ意味が拡大した。
- 結果より過程を重視するため、失敗も価値あるデータとして評価する姿勢が重要。
「試み」は未知への第一歩を象徴する語であり、成功・失敗を問わず行動そのものに価値があります。歴史的にも宗教行為から科学・ビジネスへと用途が広がり続けてきました。
現代ではPDCAサイクルやアジャイル開発など、反復的に改善する手法と相性が良い概念です。成果を急がず、小さく始めて学びを蓄積する──そのマインドセットこそ「試み」の真髄といえるでしょう。