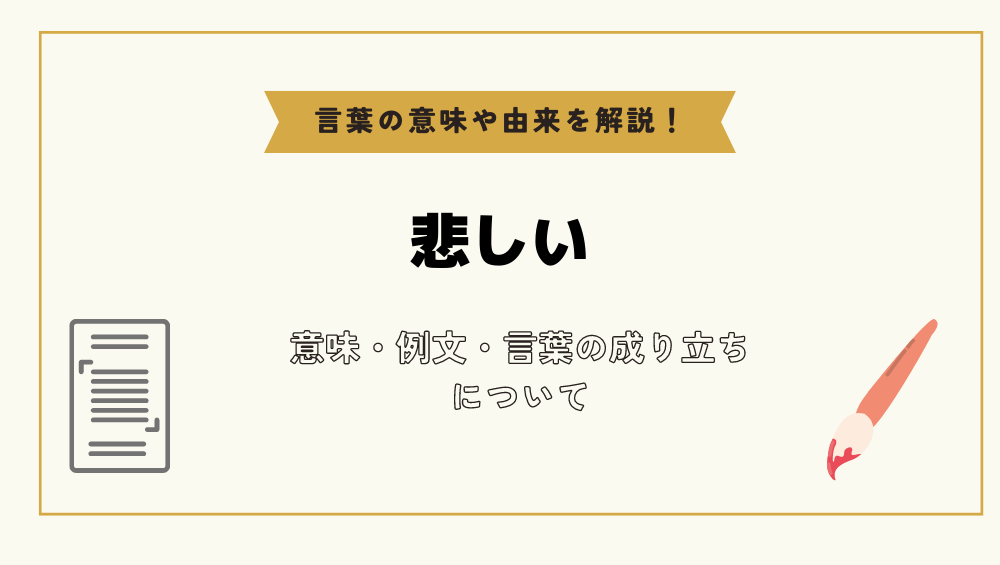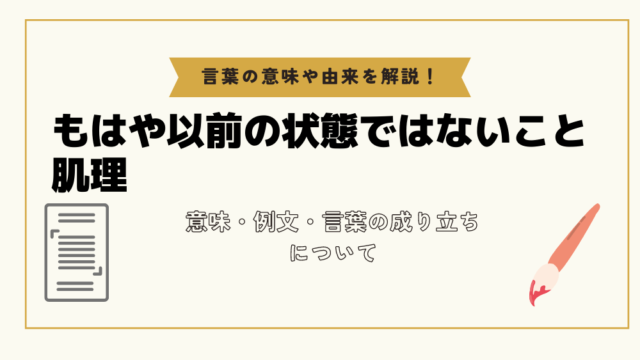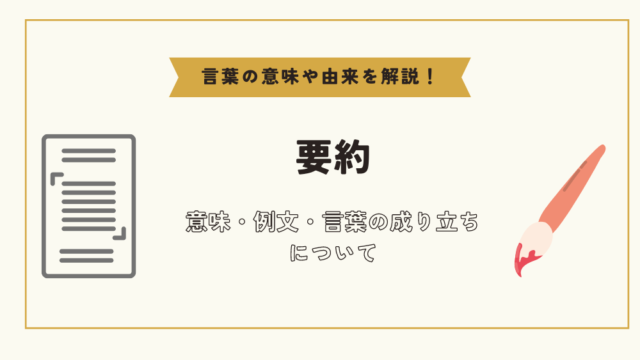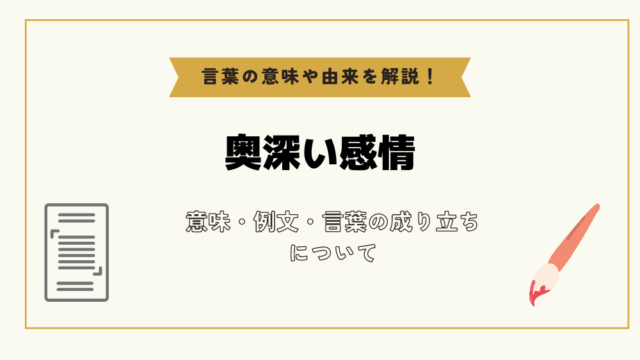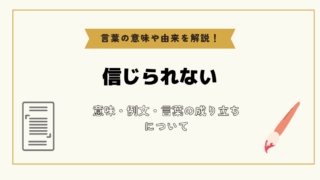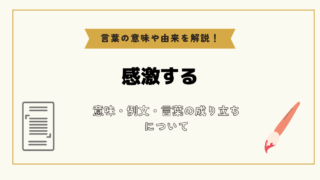Contents
「悲しい」という言葉の意味を解説!
「悲しい」とは、心が嘆きや憂いで満たされている状態を表す言葉です。
何かが予想外の結果や状況になったとき、または大切な人やものを失ったときに、私たちは悲しさを感じるのです。
悲しい気持ちは涙や重い心に表れることがあり、その心の痛みを和らげるために、人々はさまざまな方法を試みることがあります。
「悲しい」の読み方はなんと読む?
「悲しい」は、「かなしい」と読みます。
この言葉の読み方は一般的で広く使用されています。
日本語には漢字が多くありますが、この言葉においては、そのままの読み方をすることで、感情の深さや切実さを表現していると言えます。
「悲しい」という言葉の使い方や例文を解説!
「悲しい」は、さまざまな場面で使用されます。
例えば、友人が大学を卒業することになり、別れを惜しんで「君とはお別れできることが悲しいよ」と言うことがあります。
また、映画や小説などの感動的な場面で「このシーンは本当に悲しい」と表現することもあります。
思いがけない不幸な出来事に遭ったときにも、「悲しい出来事が起こってしまった」という風に使用されます。
「悲しい」という言葉の成り立ちや由来について解説
「悲しい」という言葉の成り立ちは、仏教由来であるといわれています。
仏教では、人間が感じるさまざまな感情や苦しみについて研究されており、その中でも心の深い悲しみを表す言葉として「悲しい」が生まれました。
また、言葉の由来に関しては、古代の日本語において「悲」という漢字が意味を持っていたことから派生したともいわれています。
「悲しい」という言葉の歴史
「悲しい」という言葉は、日本の古典文学や歌などにも多く使われてきました。
例えば、源氏物語や万葉集には、時の移り変わりや人々の切ない思いが「悲しい」と表現されています。
さらに、現代でも、「悲しい恋」といった表現が映画や音楽などでよく見られることからも、この言葉の長い歴史と広がりがうかがえます。
「悲しい」という言葉についてまとめ
「悲しい」という言葉には、心の嘆きや憂いを表現する力があります。
人々はさまざまなシーンでこの言葉を使って感情を伝えてきました。
また、仏教の思想や古代の文学にもこの言葉がよく使われ、日本の言葉としての歴史を刻んでいます。
悲しみは人間らしさの一つであり、その感情に寄り添いながら生きていくことが大切です。