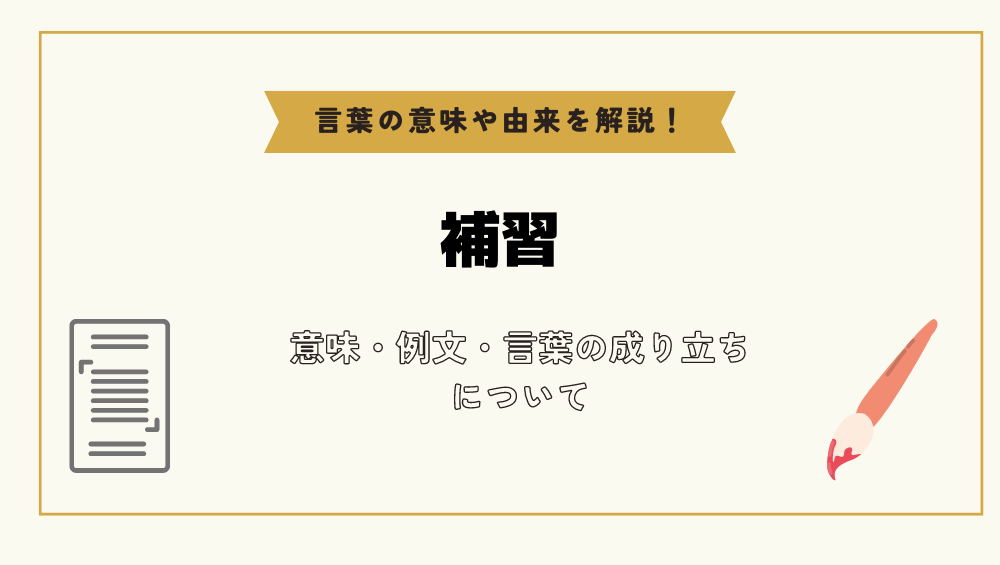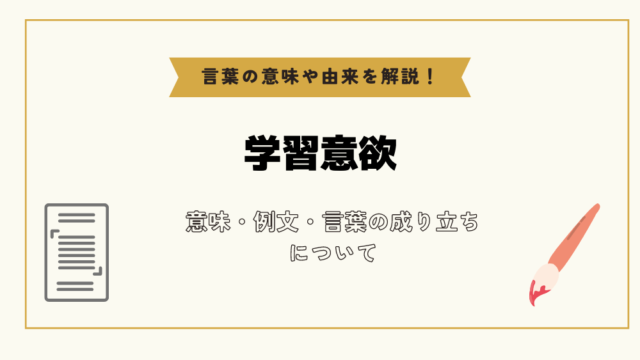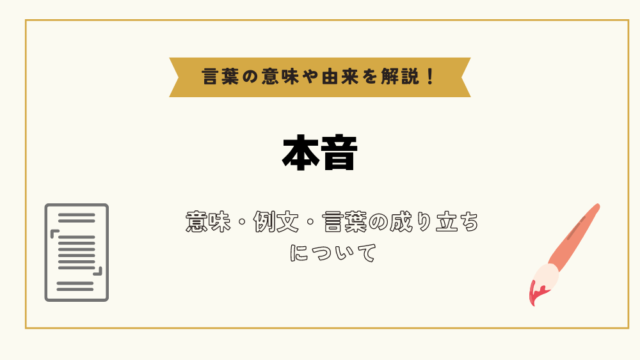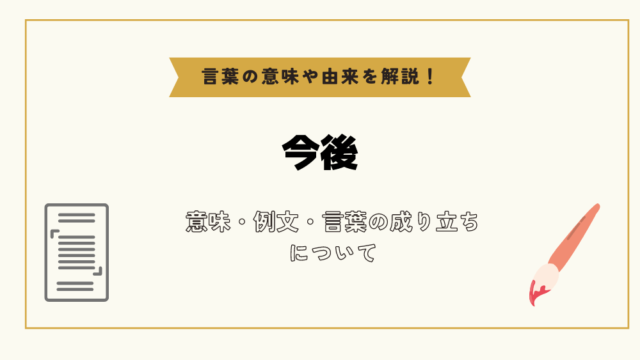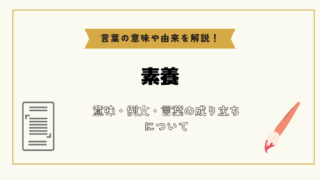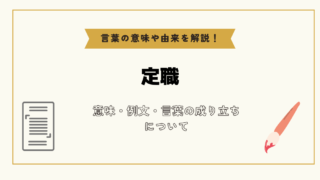「補習」という言葉の意味を解説!
「補習(ほしゅう)」とは、通常の授業や講義で理解が不十分だった内容を補い、学習の定着を図るために行われる追加学習を指す言葉です。この語は小学校から大学、さらには社会人研修まで幅広い場面で用いられ、学びの遅れを取り戻すだけでなく、理解を深める機会としても重宝されています。
補習はあくまで「補い習う」行為であり、学力が低い人のためだけのものではありません。テスト前の確認や難関資格試験に向けた強化学習など、目的意識の高い学習者にも選択されています。
「追いつくための時間」という側面が強調される一方で、授業で扱えなかった応用問題や実験を行うなど、発展的な内容を扱うケースもあります。補習の設計者が学習目標を再確認し、ニーズに沿ったプログラムを組むことが成果を左右します。
最近ではオンライン教材や双方向型のライブ授業を組み合わせたハイブリッド型補習も普及し、時間や場所の制約が大きく緩和されています。これにより、働きながら学び直しをしたい社会人や、遠隔地に住む学生でも効率よく学べる環境が整いつつあります。
補習は「学習者の自己肯定感を高めるサポート機能」という役割も担います。理解できない部分を放置せず、早期にフォローすることで学びの連鎖を途切れさせずに済むため、結果として主体的な学習姿勢を引き出しやすくなります。
「補習」の読み方はなんと読む?
「補習」はひらがなで「ほしゅう」と読み、漢字の音読み同士が結び付いた熟語です。中学国語の範囲に含まれる基本熟語ですが、正しいアクセントが曖昧になりやすい語でもあります。共通語(東京式アクセント)では「ホ↗シュウ↘」と後ろ上がりになるのが一般的です。
「補」は「おぎな(う)」とも読み、欠けた部分を足す意味合いを持ちます。一方「習」は「なら(う)」で、学びを示す漢字です。二字が組み合わさることで、欠けている学習を補うニュアンスが直感的に伝わります。
日本語では「保守(ほしゅ)」と音が似ているため聞き間違いが頻発します。授業中の連絡や掲示物では、ふりがなを添える・文脈を明示するなどして誤解を避ける工夫が求められます。
英語では remedial lesson や supplementary class と訳されることが多く、海外の教育現場でも同様の概念が存在します。ただし国や地域によって目的や実施形態は若干異なるため、言語と文化の両面を確認することが大切です。
「補習」という言葉の使い方や例文を解説!
教師や指導員だけでなく、学習者自身も日常的に用いる単語です。ここでは代表的なコロケーションや文脈を整理し、表現の幅を広げるヒントを紹介します。
使い方のポイントは「どの内容を・どの範囲で補うのか」を具体的に示すことです。曖昧なままでは学習者が目的を見失い、モチベーション低下につながります。
【例文1】昨日の数学の補習では二次関数の応用問題を重点的に解いた。
【例文2】資格試験直前の補習のおかげで苦手分野を克服できた。
「補習を受ける」「補習に参加する」などは学習者目線の表現で、「補習を実施する」「補習を組む」は教員側の語選びです。ビジネス研修では「補習プログラム」「補習セッション」といったカタカナ語と併用されることもあります。
なお、部活動や委員会の都合で出席できない学生には「オンライン補習」や「オンデマンド補習動画」を提供する事例が増えています。対面でのフォローが難しい場合でも、情報通信技術を活用すれば理解度の底上げが可能です。
「補習」という言葉の成り立ちや由来について解説
「補」という漢字は古代中国の甲骨文に源流があり、裂け目を布で継ぎ合わせる象形から派生しました。「習」は羽根を持つ鳥が繰り返し飛ぶ姿を表し、反復学習の意が付加されています。
二字を組み合わせた「補習」は、欠落した知を繰り返し埋める行為を端的に言い表した言葉として、江戸後期の寺小屋文献に既に見られます。当時は「補稽(ほけい)」や「補業(ほぎょう)」と書かれるケースもありましたが、明治の学制発布以降「補習」に統一されました。
由来の背景には「入学年齢や進級基準が揃っていない生徒を同じ教室で教える」という近代初期の課題があります。学力ギャップを埋める上で、放課後や休日を活用した追加授業が不可欠だったため、新たな教育用語として定着しました。
今日では義務教育だけでなく、民間塾や企業研修でも使われる汎用語ですが、語源をたどると「公教育の布石」として誕生した歴史的側面が浮かび上がります。
「補習」という言葉の歴史
明治5年(1872年)の学制発布後、全国で異年齢学級が混在し、教師が共通の授業を行うのが困難でした。この状況で「遅れた部分を埋める特別授業」として補習が導入されました。
大正期になると、中等教育機関で試験後の成績不良者を対象に「補習授業」を行う制度が整備されます。昭和30年代の高度経済成長期には高校進学率の上昇に伴い、大学受験対策として放課後補習や長期休暇中の特別補習が一般化しました。
1980年代以降、学習塾や予備校が台頭すると、学校側は「基礎学力の底上げ」を目的に無料補習を拡充して対抗しました。ゆとり教育期(2002〜2011年)には授業時間削減の影響で補習依存度が高まり、土曜補習や夏期集中補習が増えたことが統計から確認できます。
令和時代は ICT の進展により、オンデマンド動画・AIドリルを組み合わせた「個別最適化補習」が注目されています。教員は学習ログをリアルタイムで分析し、個別フィードバックを行うことで学びの質を向上させています。
「補習」の類語・同義語・言い換え表現
「補講(ほこう)」は大学で正規授業が休講になった際の振替授業を指し、対象と目的が限定されます。一方「追講(ついこう)」は欠席者向けに行われる追加講義で、学部や講師によって使い分けられます。
「リメディアル教育」「フォローアップ授業」「リカバリー学習」などの外来語・カタカナ語も、補習とほぼ同義に扱われるケースがあります。ただしリメディアル教育は大学新入生の基礎学力不足を是正する意味で用いられるなど、対象が限定されることがあります。
【例文1】大学では英語の基礎力向上を目的にリメディアル教育を導入している。
【例文2】欠席者のための追講が試験前に設定された。
「補足学習」「追加指導」なども場面に応じて言い換えられますが、ニュアンスが微妙に異なるため文脈の確認が重要です。
「補習」の対義語・反対語
補習の反対概念は「本授業」「正規授業」「正課」などが挙げられます。本授業はカリキュラムに組み込まれた必修授業であり、補習はそれを補う位置づけにあります。
また「発展授業」「特進講座」は平均レベルを超える内容に挑むため、補習と対照的に「加速学習」を目的としたプログラムといえます。ただし、補習が基礎固めだけとは限らず応用内容を扱う場合もあるため、二分的な捉え方には注意が必要です。
教育学では「延伸(エンリッチメント)」と「リメディエーション」を対比させる文脈があり、補習はリメディエーション側に属します。反面、ギフテッド教育などで実施される発展講座は延伸に分類されるのが通例です。
「補習」と関連する言葉・専門用語
教育分野では「学習指導要領」との関連が不可欠です。正規授業で扱う範囲は指導要領で定められているため、補習はその範囲を前提に設計されます。
「個別最適化学習」は AI やデータ分析を用いて、学習者の理解度に応じた教材を提供する手法で、補習との親和性が高いとされています。「フィードバックループ」「学習ログ解析」などの専門用語も補習実践を語るうえで欠かせません。
その他、「放課後子ども教室」「寺子屋事業」「夜間中学」なども、補習的役割を果たす取り組みとして行政文書に登場します。実務では「チュータリング(個別指導)」と組み合わせることで学習効果が向上すると報告されています。
「補習」についてよくある誤解と正しい理解
誤解①「補習は成績不振者だけが受けるもの」→実際には学力上位者が応用問題に挑戦する場として設定されることも少なくありません。
誤解②「補習を受けると落第を免れない」→補習は理解を深める手段であり、学年評価の減点要素ではありません。時間割や評価基準を確認すればネガティブなイメージは払拭できます。
誤解③「補習=居残り」は過去のイメージです。現在は放課後プログラムやオンライン教材が主流で、学習者が自主的に選択できる環境が整っています。
正しい理解としては「学習のセーフティーネットかつ発展の場」であり、主体的に活用することで成果が最大化されます。教員側も学習者の心理的負担を軽減するため、ポジティブな動機付けを意識することが重要です。
「補習」という言葉についてまとめ
- 「補習」は正規授業で不足した学びを補う追加学習を指す言葉。
- 読み方は「ほしゅう」で、音読み同士の熟語として定着している。
- 江戸後期の寺小屋から始まり、明治以降の学制で制度化された歴史を持つ。
- 現代ではオンライン化が進み、基礎補強から応用発展まで幅広く活用される。
補習は「欠けた部分を補い、学びを完結させる仕組み」として教育現場に深く根付いています。学校内外で多様な形式が展開されており、学習者の目標やライフスタイルに合わせてカスタマイズできる柔軟性が魅力です。
一方で「成績不振者のための罰則」という誤解が残るのも事実です。補習の本質は学習機会の確保とモチベーション維持にあり、主体的に活用することで学びの連鎖が強固になります。正しい理解と適切な設計を通じて、補習はこれからも学習者の成長を支え続けるでしょう。