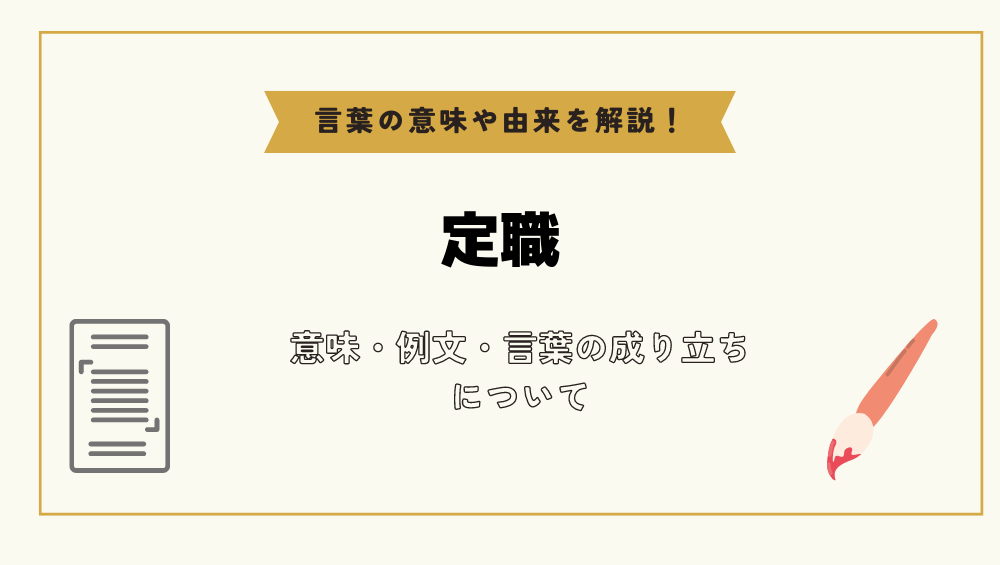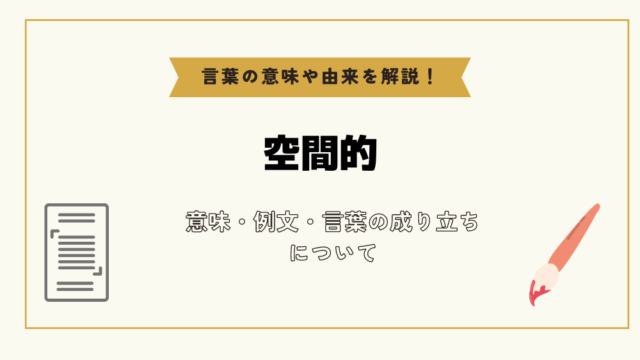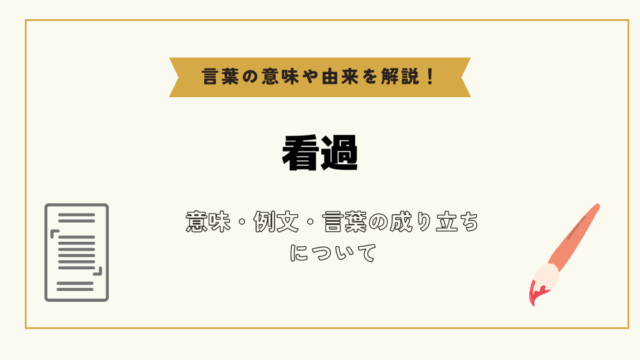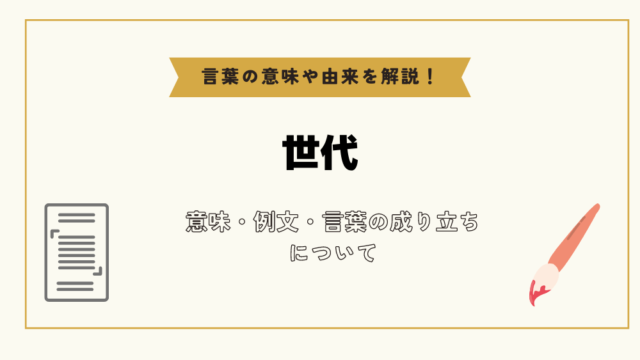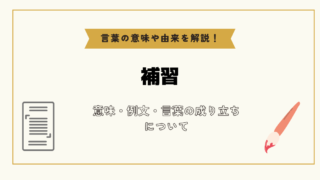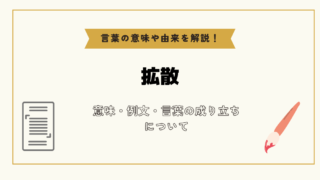「定職」という言葉の意味を解説!
「定職」とは、継続的かつ安定して従事する仕事や職業を指す言葉で、臨時・アルバイト・派遣などの短期的な雇用形態と対比されることが多いです。社会保険や福利厚生が整い、長期的に雇用が見込める仕事である点が特徴です。一般的にはフルタイム勤務を念頭に置きますが、正社員であれば必ずしも週40時間に限定されるわけではありません。
定職のニュアンスには、生活基盤を支える「収入の安定」と、働く人の「社会的信用」の二つの要素が含まれます。住宅ローンや各種ローン審査で有利になるのは、この信用が評価されるからです。
一方で、最近はリモートワークやフリーランスが普及し、雇用形態が多様化しています。そのため「定職」の定義も企業ごと、業界ごとに幅があるのが現状です。
重要なのは、契約期間の定めがなく、労働基準法に基づく保護を受けながら働ける環境かどうかという点です。法令上は「期間の定めのない雇用契約」が定職とみなされることが多く、派遣社員でも無期雇用であれば定職に分類されるケースがあります。
最後に、定職は個々人のキャリア形成やライフプランに深く関わる概念です。安定志向だけでなく、自己実現や働き方の柔軟性をどう両立させるかが、現代の就労観では問われています。
「定職」の読み方はなんと読む?
「定職」は一般に「ていしょく」と読みます。「さだめしょく」と読まれることはありませんので注意しましょう。訓読みを使わず、音読みで統一されるため文字変換でも一発で出やすい語です。
「定」は「定まる」「固定」のイメージを持ち、「職」は「職業」を示します。二字熟語としては読みやすい部類に入るものの、就職活動を始めたばかりの学生などは誤読することがあります。
辞書表記では「てい‐しょく【定職】」と中黒が入ることが多いですが、文章中では中黒を省くのが一般的です。会話でのアクセントは頭高型(て↗いしょく)で発音されることが多いものの、地域差はさほど大きくありません。
「定食」と同音異義語であるため、飲食業界の話題と混同しないようにするのがポイントです。ビジネスメールや履歴書で誤字があると信用を損なう恐れがありますので、読みと書きの両面で気を配りましょう。
「定職」という言葉の使い方や例文を解説!
定職は日常会話から公的書類まで幅広く登場します。就職活動、転職相談、ローン審査など、安定性を確認したい場面でキーワードになります。肯定的に使う場合が多い一方、柔軟な働き方を否定するニュアンスを含むこともある点に注意しましょう。
使い方のポイントは「就労形態の安定性」を示したいときに限定して用いることです。単にフルタイムで働いていても短期契約であれば定職とは言いません。逆にフルリモートでも無期雇用なら定職と表現できます。
【例文1】彼はフリーランスをやめて定職に就き、収入が安定した。
【例文2】住宅ローンを組むために、まずは定職を探すことにした。
上記のように「定職に就く」「定職を持つ」という形が最も一般的なコロケーションです。なお「定職を得る」「定職がある」といった表現も自然に使えますが、「定職する」は誤用なので避けましょう。
就労支援の現場では「定職率」「定職維持」という派生語も登場します。これらは就労継続支援A型・B型事業所などで雇用の定着度を測る指標として活用されています。
「定職」という言葉の成り立ちや由来について解説
「定職」は中国古典に起源を持つわけではなく、日本国内で明治期以降に定着した和製漢語と考えられています。「定」は律令制度下で使われていた「官職を定める」の文脈から派生しましたが、「定職」という二字熟語自体は文献上それ以前に確認されていません。
明治維新後の職業安定政策や近代的労働市場の形成の中で、無期限雇用を区別する言葉として誕生したとされています。当時、「職工」が一時的労働者を指し「定職工」が常雇いを指した事例があり、この語が縮約して「定職」となりました。
江戸時代には「常雇い」「終身雇」「用人」など、類似の概念を示す言葉が存在しましたが、明治後半には「定職」が新聞や雑誌で一般化します。その背景には工場法の施行や労働組合の発足があり、労働条件の安定が社会的に注目され始めたことが影響しています。
つまり「定職」の由来は、近代日本が雇用の長期安定を制度化していくプロセスと密接に関わっているのです。戦後の高度経済成長期には終身雇用・年功序列とセットで用いられ、サラリーマン文化を象徴するキーワードの一つとなりました。
「定職」という言葉の歴史
「定職」が一般に浸透し始めたのは大正から昭和初期にかけてです。職工の需要が高まり、都市部で常用雇用が当たり前になると、短期雇用と区別するためにこの語が多用されました。
戦後の高度成長期に企業の終身雇用制度が拡大すると、「定職」は安定した人生設計の象徴語として定着しました。同時に、大学卒業後に正社員として入社し定年まで勤め上げるモデルが「定職」によって肯定されました。
バブル崩壊後は非正規雇用が増え、「定職」という概念が再び注目されます。派遣法改正や就職氷河期を経て、正社員の希少価値が高まったことで「定職」の意味が相対的に重くなりました。
現代では「定職=正社員」が必ずしも絶対ではなく、無期雇用派遣や専門職契約など、多様な形態を包含する語へと変容しています。こうした変化は、働き方改革やテクノロジーの進展によってさらに加速すると見込まれています。
「定職」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「常勤」「正社員」「常用雇用」「本職」などがあります。これらは雇用期間の安定性を示す点で共通しますが、細かなニュアンスは異なります。
「常勤」は勤務形態に焦点を当てた言葉で、フルタイム勤務を示します。「正社員」は労働契約の形態を規定し、会社による社会保険・福利厚生の適用が前提です。「常用雇用」は労基法上の期間の定めのない雇用を意味し、公的統計で用いられる専門用語です。
「本職」は副業に対するメインの仕事を指す場面で多用され、職種の安定性より優先度を示すケースが多い点が特徴です。文脈によっては「専業」「本業」と言い換えられます。
国際的には「regular employment」「permanent job」などが近い表現です。翻訳の際は雇用期間の定めがない点を明示すると誤解を防げます。
「定職」の対義語・反対語
「定職」に明確に対立する概念は「不定職」や「臨時職」です。現在では「非正規雇用」「アルバイト」「派遣社員」などが対義的に扱われます。
厚生労働省の統計では、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・嘱託などが「非正規雇用」と分類され、定職と区別されています。ただし無期雇用派遣や地域限定正社員など、中間的な形態も出現しており境界は必ずしも明確ではありません。
フリーランスや個人事業主は組織に雇用されない働き方であり、定職の枠外と見なされることが一般的です。一方、副業解禁により「定職+副業」という複線型キャリアも増えています。
対義語を使う際は「安定性の低さ」を示すのか「雇用契約の有無」を示すのか、意図をはっきりさせることが重要です。誤解を避けるために、統計用語か日常用語かを文脈で区別するよう心掛けましょう。
「定職」についてよくある誤解と正しい理解
誤解の一つに「定職=公務員のような絶対的安定」と考えるものがありますが、民間正社員でもリストラや倒産のリスクは存在します。安定性の程度は業界や企業体質によって大きく変わります。
次に、「定職に就けば将来安泰」という見方も過大評価です。終身雇用が揺らぐ現代では、スキルアップや社外ネットワーク構築が欠かせません。また、転職市場で評価される経験や資格を身につけることも必要です。
【例文1】定職に就いていても学びを続けなければキャリアが停滞する。
【例文2】定職があるからといって所得が右肩上がりとは限らない。
もう一つの誤解は、定職がワークライフバランスを阻害するという先入観ですが、昨今は正社員でもテレワークや時短勤務が選択できる企業が増えています。重要なのは企業文化と制度の確認です。
最後に、「定職=終身雇用」という固定観念から自由になれば、多様なキャリア戦略を描きやすくなります。将来的に転職や独立を視野に入れていても、定職で基盤を固めるメリットは大きいのです。
「定職」を日常生活で活用する方法
就労支援センターやハローワークでは、定職を目指す求職者に対して職業訓練やキャリアカウンセリングを提供しています。まずは自己分析を行い、自分の強みや適性を把握しましょう。
次に、求人票で「正社員」「無期雇用」「直接雇用」などの表記を確認し、定職かどうかを見極めることが重要です。派遣会社経由の求人でも、派遣先の直接雇用化制度がある場合は定職へのルートとなり得ます。
【例文1】資格取得支援制度を活用して定職にステップアップする。
【例文2】転職エージェントから定職の求人を紹介してもらう。
定職に就いた後も、生活設計に役立つ制度を利用すると効果的です。住宅手当や企業型確定拠出年金など、福利厚生をフル活用することでライフプランが安定します。
さらに副業や社内異動制度を活かせば、定職に留まりながらキャリアの幅を広げることが可能です。安定と挑戦を両立させる発想が、これからの時代には欠かせません。
「定職」という言葉についてまとめ
- 「定職」は長期的かつ安定した雇用関係にある仕事を示す言葉。
- 読み方は「ていしょく」で、「定食」との混同に注意。
- 明治期の常用雇用の区別から生まれ、戦後に終身雇用と結び付いた。
- 現代では雇用形態の多様化に伴い、無期雇用かどうかを見極めることが重要。
定職は、生活基盤を支える収入の安定と社会的信用をもたらす一方で、終身雇用の崩壊や働き方の多様化により、価値観が揺れ動いている概念です。読み書きは簡単でも、背景にある労働市場の変遷や制度を理解することで、より適切に使いこなせます。
現代では無期雇用派遣や限定正社員など新しい形態が登場し、境界が曖昧になっています。そのため求人選択時には契約内容を詳細に確認し、自分のキャリア戦略と照らし合わせることが肝要です。「定職」という言葉を正しく理解し、活用することで、安定と成長を両立させた働き方を実現しましょう。