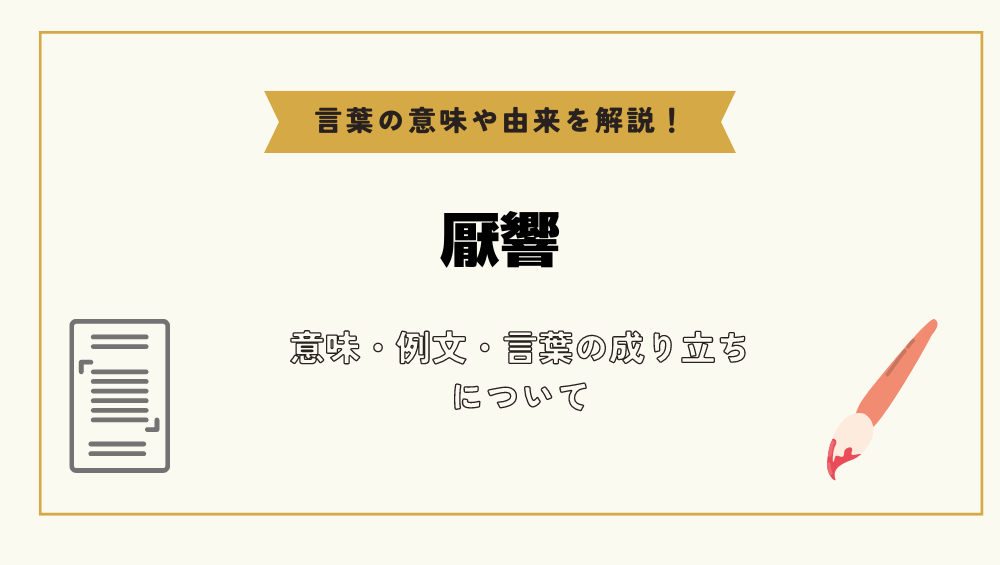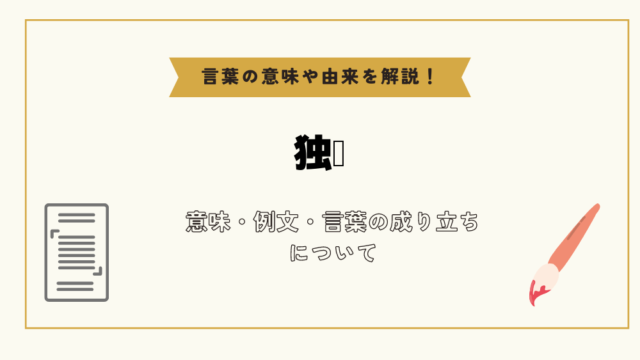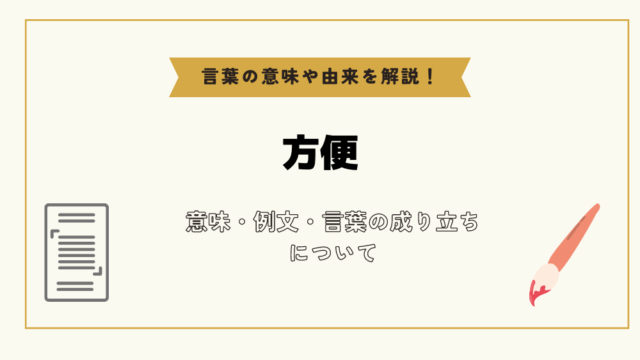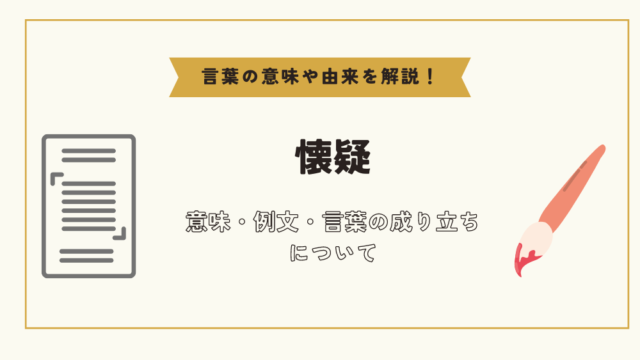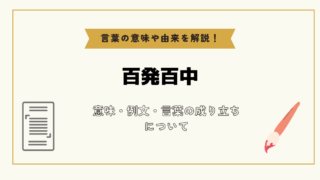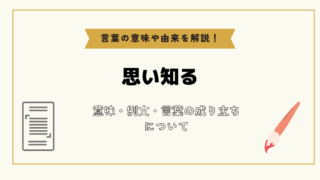Contents
「厭響」という言葉の意味を解説!
「厭響」とは、日本語の方言で「うんざりする」「嫌になる」という意味を持つ言葉です。
何かしらの理由で不快感や嫌悪感を抱いた時に使われることがあります。
例えば、音楽のリズムや音色が自分に合わないと感じた時などに「厭響する」と言います。
「厭響」の読み方はなんと読む?
「厭響」は、読み方は「えんきょう」となります。
漢字の「厭」と「響」のそれぞれの読みを組み合わせています。
正しい読み方を知ることで、適切な言葉の使用ができます。
「厭響」という言葉の使い方や例文を解説!
「厭響」はネガティブな感情を表す言葉ですが、個人的な意見や感情を表現する際によく使用されます。
例えば、「あの曲は私にとって厭響の曲だ」という風に使います。
このように、「厭響」という言葉を使うことで、自分の感情や意見を正確に表現することができます。
「厭響」という言葉の成り立ちや由来について解説
「厭響」という言葉は、日本語の方言や俗語の一つとして使われています。
具体的な成り立ちや由来については明確な文献や情報は存在しませんが、日本の地域ごとに方言が異なることや、話し手の個性や感覚によって新しい言葉が生まれることがあるため、そのような背景から生まれたものと考えられます。
「厭響」という言葉の歴史
「厭響」という言葉の具体的な起源や歴史については、特定の出典や文献が見つかりません。
しかし、方言や俗語は長い時間の中で地域や時代によって変化してきたものであり、現在の形になるまでには歴史の流れが存在していると考えられます。
一般的には、方言や俗語は口頭伝承や日常会話によって広まっていくので、個々の言語の変化の一部として位置づけられます。
「厭響」という言葉についてまとめ
「厭響」という言葉は、日本語の方言や俗語として使われる言葉であり、「うんざりする」「嫌になる」といった意味を持ちます。
音楽のリズムや音色に対して感じる不快感などに使われることがあります。
正しい読み方は「えんきょう」となります。
具体的な成り立ちや由来、歴史に関しては明確な情報は得られませんが、方言の一つとして広まり、日本語の多様性を感じさせる言葉となっています。