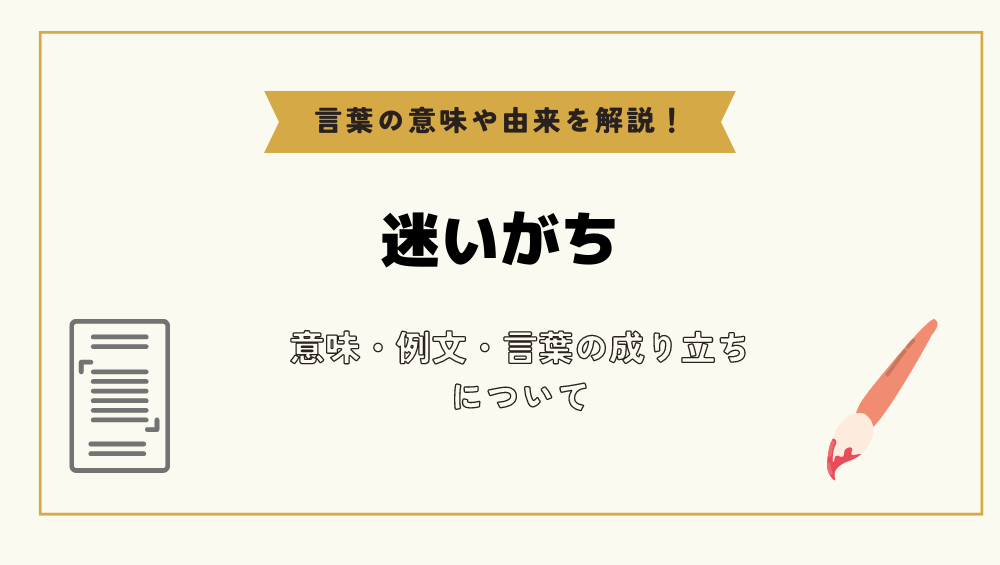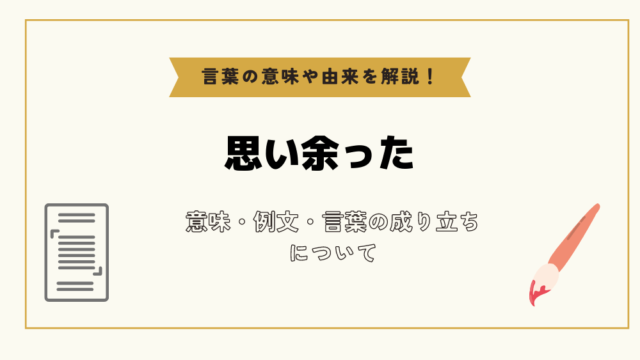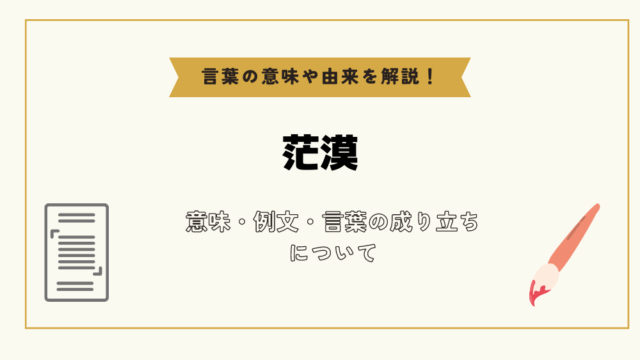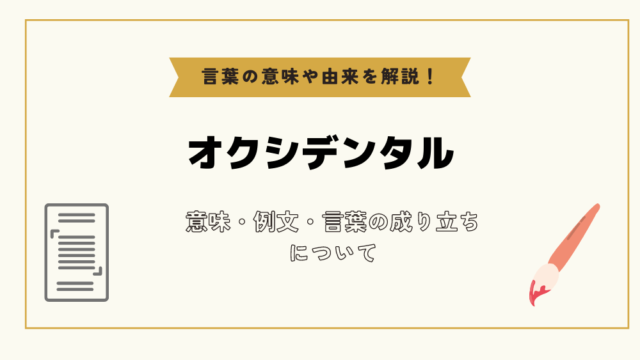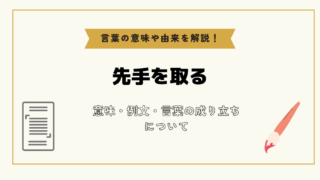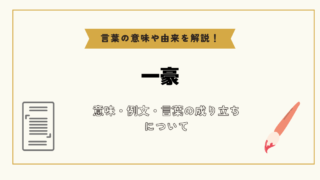Contents
「迷いがち」という言葉の意味を解説!
「迷いがち」という言葉は、迷ったり悩んだりする傾向があることを表します。
何か選択や判断をしなければならない場合や、自信がなくて決断できない場合などによく使用されます。
例えば、新しい仕事に挑戦することに迷いがちだったり、友人との約束を取り決める時に相手がどの日程が良いか迷いがちだったりするのです。
「迷いがち」の読み方はなんと読む?
「迷いがち」という言葉は、「まよいがち」と読みます。
この読み方は、通常の日本語の読み方に基づいています。
迷いがちに近い意味を持つ言葉として「迷いやすい」「迷いが多い」という表現もありますが、意味は同じです。
「迷いがち」という言葉の使い方や例文を解説!
「迷いがち」という言葉の使い方は非常に幅広いです。
例えば、「私はいつも何を食べるか迷いがちです」という表現は、食事の選択に悩んでいることを示しています。
また、「彼は将来の進路について迷いがちなようです」という表現は、将来の進路を決めることに迷っていることを意味しています。
このように、さまざまな場面や状況で「迷いがち」という言葉を使うことができます。
「迷いがち」という言葉の成り立ちや由来について解説
「迷いがち」という言葉の成り立ちや由来については明確な情報はありませんが、日本語の普通の文法に基づいて作られた表現です。
「迷い」という動詞「迷う」の連用形「迷い」と、現れる傾向を示す助詞「がち」が結合してできました。
このような表現は、同様の意味を持つ言葉として「迷いやすい」という表現も存在します。
「迷いがち」という言葉の歴史
「迷いがち」という言葉は、日本語の一部として古くから存在していたと考えられますが、具体的な歴史については詳しく分かっていません。
ただし、迷ったり悩んだりすることは人間の性格や性質に密接に関連しており、言葉として表現されることも多いものです。
したがって、「迷いがち」という表現も日本語の歴史とともに発展してきたものと考えられます。
「迷いがち」という言葉についてまとめ
「迷いがち」という言葉は、迷ったり悩んだりする傾向があることを表す表現です。
何か選択や判断をしなければならない場合や、自信がなくて決断できない場合などによく使用されます。
この言葉の読み方は「まよいがち」となります。
また、使い方や例文も多様であり、さまざまな場面で活用できます。
「迷いがち」という言葉は、日本語の一部として古くから存在していたと考えられますが、具体的な由来や歴史については詳しく分かっていません。