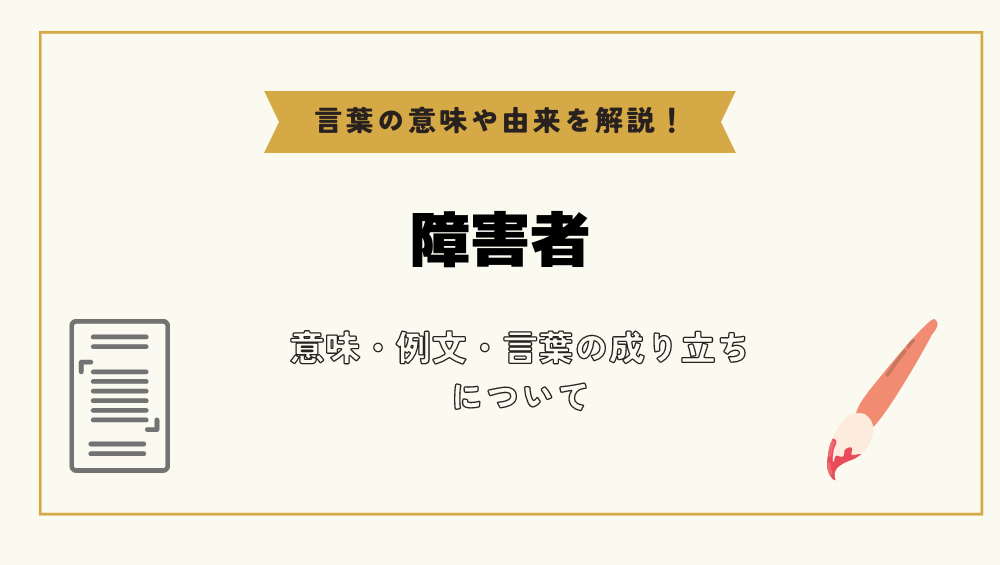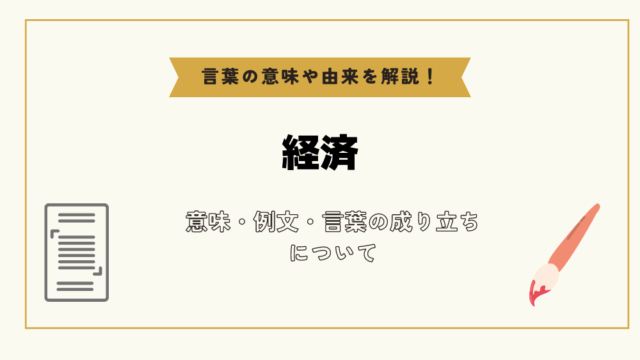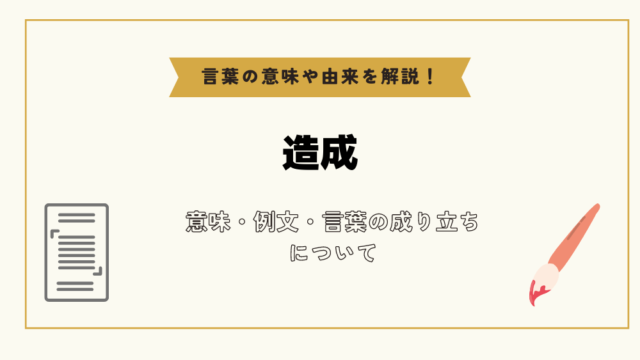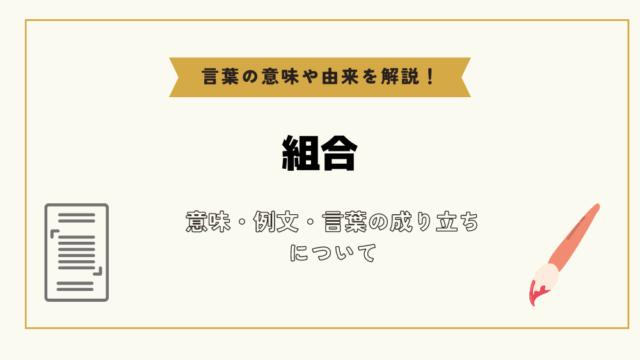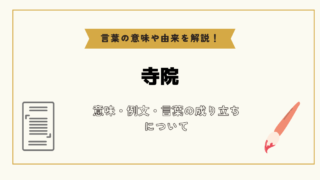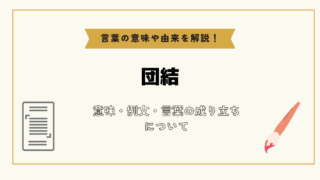「障害者」という言葉の意味を解説!
「障害者」とは、身体・知的・精神などの機能障害が長期にわたり日常生活や社会参加に制限を受ける人を指す総称です。日本では障害者基本法や障害者差別解消法などの法律において定義が定められており、医学的な診断だけでなく、社会的なバリアによって生じる不利益までを含めて考える点が特徴です。つまり、障害自体よりも「社会と環境」との相互作用が人を障害者にしている、という現代的な理解が広がっています。
社会的モデルの観点では、階段しかない駅構内や点字ブロックの欠如など、環境側の障壁がある限り障害は解消されません。この考え方は「障害は人ではなく環境がつくる」というキャッチコピーで端的に示されることもあります。そのため、支援策は個人への補助だけでなく、バリアフリー化や合理的配慮の提供など、社会全体の仕組みづくりが重視されています。
一方、日本の公的制度では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の三種類が発行され、障害の種別や程度を客観的に示す指標として用いられます。手帳の有無は行政サービスや雇用支援の対象を決める実務上の基準ですが、障害の有無を人間の価値と結びつけるものではないことに留意が必要です。
海外では“Person with Disabilities”と表記され、英語圏でも「障害のある人」という人間を主体にした呼称が推奨されています。いずれの文化でも、ラベリングが偏見や差別につながる可能性があるため、呼称を使う場面では当事者の意向を尊重することが世界的な潮流になっています。
日常会話や文章で「障害者」という言葉を使う際は、その人の属性を説明する補助的な情報として扱い、個人を特定するラベルとして濫用しない姿勢が求められます。また、公的文書では法令の表記に合わせつつ、解説記事や講演などでは「障害のある人」という柔らかい表現を併記するケースが増えています。
これらの動きは「ユニバーサルデザイン」を推進する公共政策とも結びつき、多様な人が自立しながら共に暮らせる社会づくりを後押ししています。呼称の選択が抱える重みを理解し、背景にある権利保障の視点を忘れないことが重要です。
「障害者」の読み方はなんと読む?
「障害者」の読み方は「しょうがいしゃ」で、三拍で発音されます。「がい」にアクセントが置かれる人もいれば、標準語では平板に読む場合もあり、地域差や話者の癖が出やすい語です。児童や学生向けの読み仮名付き教材では「しょうがいしゃ」と平仮名で統一されることが多く、視覚障害者向けの点字資料にも同じ読みが採用されています。
漢字は「障(さわ)りを害する者」という字面からネガティブな印象を与えやすいとの指摘があり、「障がい者」とひらがな交じりで表記する自治体やメディアもあります。ただし、法律名や手帳名には漢字表記が使われているため、行政手続きや公式文書では「障害者」が現行の正式表記です。
発音の注意点として、早口で続けざまに言うと「しょうがいちゃ」と聞こえる場合があるため、プレゼンテーションや公共の場ではゆっくり区切ると誤解を避けられます。また外国語話者に説明する際は、“しょうがいしゃ”をローマ字で“shogaisha”と示し、併せて英訳“Person with Disabilities”を添えると伝わりやすいです。
「障害者」という言葉の使い方や例文を解説!
障害の有無で社会参加のチャンスが制限されないよう「障害者」という言葉は政策議論や権利擁護の文脈で多く使われます。医療・福祉の現場でも対象者を示す専門用語として用いられますが、当事者個人に対して使う際は敬意を欠かさない表現が大切です。
近年は「障害をもつ人」「障害当事者」と言い換えて柔らかなニュアンスを出す場面も増えています。ただし法律や制度を説明する文章では正式名称を省略なく記載する必要があります。
【例文1】自治体は障害者が安心して利用できる公共交通の整備を進めている。
【例文2】企業が障害者雇用を拡大し、誰もが働きやすい職場環境を整えている。
口語では「障がい者」とひらがな表記にすることで当事者の心理的負担を軽減する試みもありますが、読みやすさや年齢層によっては漢字の方が理解しやすい場合もあります。複数の配慮をバランス良く取り入れることが求められます。
「障害者」という言葉の成り立ちや由来について解説
「障害」という語は奈良時代の文献にも登場し、元来は「さわり」や「妨げ」を意味していました。江戸期には医学書で身体機能の欠損を表す語として用いられ、明治以降の西洋医学導入とともに“handicap”の訳語として定着しました。
明治後半には「障害児」「障害兵士」などの派生語が見られ、戦後の社会福祉制度の整備で「障害者」が法令用語として確立しました。当時は「身体障害者福祉法」(1949年)が最初期の使用例で、その後「知的障害者福祉法」「精神障害者保健福祉法」へと拡大しました。
由来の背景には、戦争で負傷した復員兵や工業化による労働災害など、社会の変化に伴い支援対象が拡大した歴史があります。翻って今日ではインクルーシブ教育や雇用機会均等など、支援の枠を超えた「共生社会」の実現がキーワードとなっています。
「障害者」という言葉の歴史
戦前・戦後を通じて「障害者」の社会的地位は大きく変化しました。1950年代は施設収容中心の福祉政策が主流でしたが、70年代からは地域で暮らす「ノーマライゼーション」の理念が浸透し、自立生活運動が活発化しました。
1981年の国際障害者年は、国連が「完全参加と平等」を掲げた世界的転換点です。この年を契機に日本でも障害者基本法(旧法)が制定され、障害者福祉は権利保障の視点へと舵を切りました。
2000年代に入り障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行や障害者差別解消法の成立を経て、差別禁止と合理的配慮が法的義務化されました。2021年には合理的配慮の提供義務が民間事業者にも拡大し、社会全体で責任を分担する体制が整いつつあります。
歴史を振り返ると、「障害者」という言葉は福祉の受け手を示すだけでなく、社会を変革する主体として位置付けられるようになっています。
「障害者」の類語・同義語・言い換え表現
障害者を直接的に指す言葉としては「障害のある人」「障がい者」「障害当事者」などが挙げられます。これらは尊厳を重視し、個人を主体に置く表現として広まっています。
福祉現場では「利用者」「サービス利用者」と呼ぶことも多く、支援と対等な関係を示すニュアンスを加味しています。国連条約の公用訳に倣って「障害者(障害のある人)」と併記するスタイルも一般化しています。
欧米で用いられる“PWD(People with Disabilities)”や“Disabled person”は状況に応じて使い分けられ、学術論文では“PwD”の略号が頻出します。いずれも当事者の希望を尊重し、差別用語を避ける点は共通しています。
「障害者」の対義語・反対語
障害者の対義語として「健常者」が挙げられることがありますが、最近ではこの区分自体が二分法的で不適切と指摘されています。
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)では、誰もが程度の差こそあれ機能制限を有すると考え、「健常/障害」の線引きを明確に置かないモデルが推奨されています。そのため、健常者という語を使用する際は、比較概念として必要かどうかを慎重に検討する必要があります。
日本語の口語では「一般の人」「障害のない人」といった表現も見られますが、暗黙の優劣を孕む恐れがあるため注意が必要です。
「障害者」についてよくある誤解と正しい理解
一般に「障害者は特別扱いを望んでいる」という誤解がありますが、実際は公平な機会と合理的配慮を求めている場合が多いです。特別扱いではなく、障壁を取り除くための具体的なサポートが必要とされています。
また「障害者は働けない」というステレオタイプも誤りで、就労支援やテクノロジーの進歩により多様な働き方が広がっています。テレワークや合理的配慮の導入によって、専門職やクリエイティブ分野で活躍する人も増えています。
社会的コストがかかるという観点のみで語られることもありますが、バリアフリー化は高齢者や子育て世代など多くの市民に恩恵をもたらす「共益投資」として評価されています。
「障害者」に関する豆知識・トリビア
国際パラリンピック委員会(IPC)が定める競技分類では、視覚障害・車いす使用など10種類以上の障害クラスが存在します。これにより公平な競技環境が確保されています。
日本で障害者手帳を最年少で取得できる年齢に下限はなく、生後間もない乳児でも医師の診断と保護者の申請で交付が可能です。一方、年齢上限もなく、高齢期になってから取得するケースも多く見られます。
点字ブロックは1967年に日本で発明され、世界約50か国に広まりました。黄色が多いのは視認性と国内規格の両面から採用された結果です。東京メトロでは点字ブロックの幅が通常より広い試験区画も存在し、歩行ナビゲーション改善の研究が続いています。
「障害者」という言葉についてまとめ
- 「障害者」とは長期的な機能障害により生活や社会参加に制限を受ける人を指す法的・社会的な用語。
- 読み方は「しょうがいしゃ」で、漢字・ひらがな混在表記が併用される。
- 明治期に定着し、戦後福祉制度とともに法令用語として確立した歴史をもつ。
- 呼称の選択は当事者の尊厳と合理的配慮を重視し、場面ごとに最適な言い換えが推奨される。
障害者という言葉は制度・歴史・文化的背景が複雑に絡み合った用語であり、一語で多くの文脈を内包しています。意味や成り立ちを正しく理解することで、誤解や偏見を減らし、建設的な議論が可能になります。
読み方や表記も状況に応じた選択が求められ、法令解説では正式名称、日常会話では「障害のある人」といった柔らかい表現を使い分けるとスムーズです。最後に、呼称よりも大切なのは個々人の人格や意思を尊重する姿勢であり、その意識こそが真の共生社会を形づくる鍵となります。