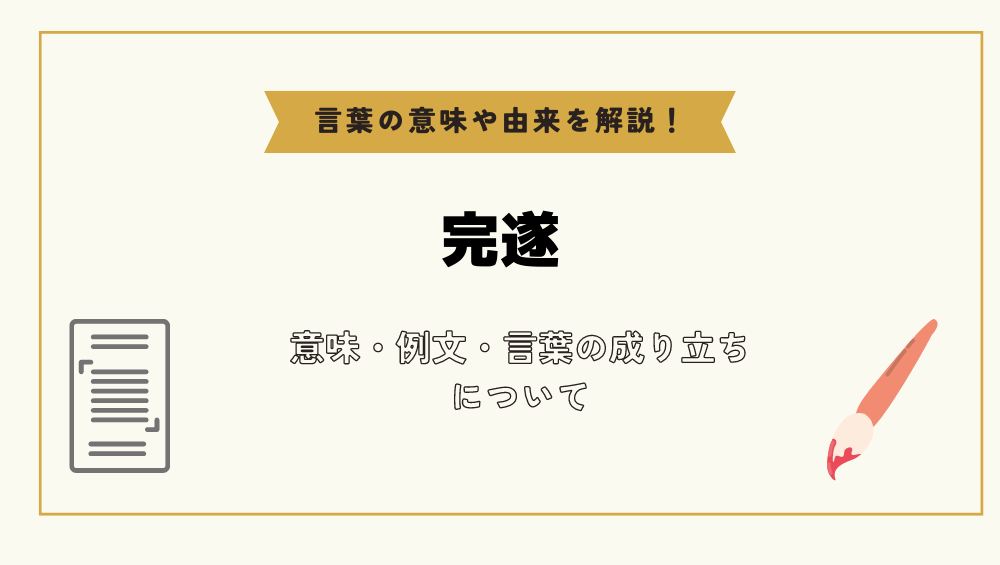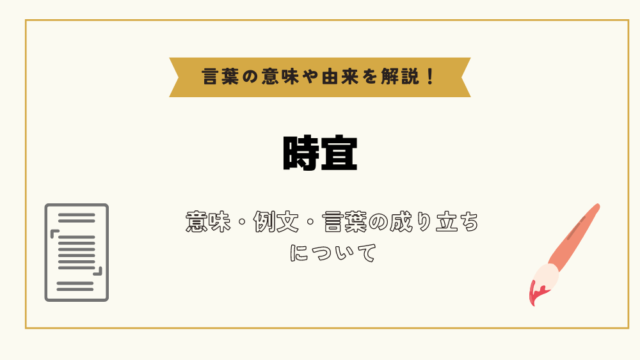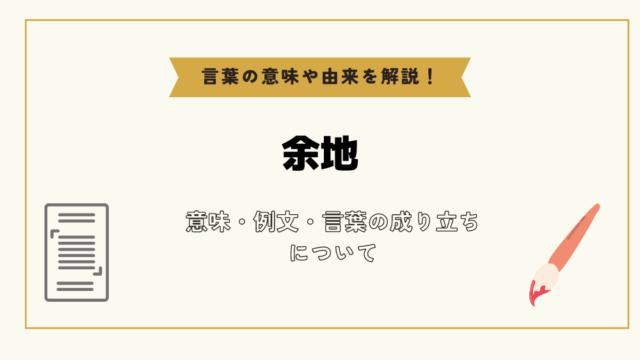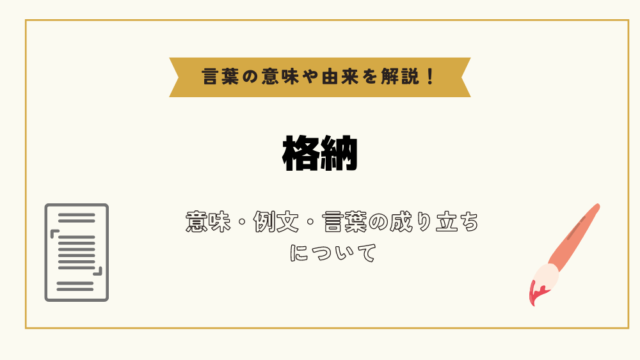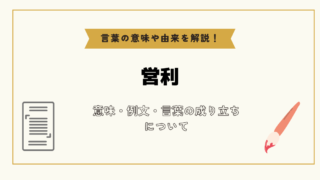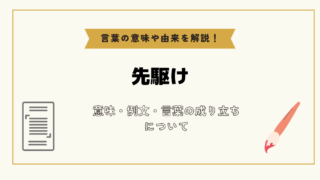「完遂」という言葉の意味を解説!
「完遂(かんすい)」とは、計画や任務、目標などを最初から最後までやり抜き、欠けることなく完全に成し遂げることを示す言葉です。
この語は「完」と「遂」の二字で構成され、それぞれ「完全」「成し遂げる」という意味を持ちます。
言い換えるならば、途中で妥協したり、一部のみを終えたりするのではなく、目的を100%達成した状態を指す、とても力強い表現です。
第二段落ではニュアンスを確認しましょう。
「完了」や「達成」よりも、意志や努力の重点が高く、「最後まで責任を負ってやり抜く」という含みが強くなります。
困難を乗り越えた先にこそ「完遂」という言葉が似合う、というイメージを持つと理解しやすいです。
続いて使用場面を想像すると、ビジネスのプロジェクト、学術研究、長期の自己目標など大規模・長期的な取り組みが多い傾向にあります。
ただし日常会話で使っても誤りではなく、「やり終える」よりもやや硬く、相手に真剣さを伝える効果があります。
最後に注意点です。
「完遂」は名詞形またはサ変動詞「完遂する」で使いますが、動詞としての活用は「完遂した」「完遂できる」と続けます。
「完遂させる」と他動詞的に使う場合もありますが、主体が複数いる場合は「プロジェクトを完遂させたチーム」のように主語と目的語を意識しましょう。
「完遂」の読み方はなんと読む?
まず読み方は「かんすい」です。
音読みの熟語であり、訓読みや当て字は存在しません。
「完」を「かん」、「遂」を「すい」と読むため、表記揺れも少なく、一度覚えれば迷いにくいのが特徴です。
誤読例として「かんつい」「かんずい」と濁音化したり、「かんつう」と送り仮名を誤るケースがありますが、いずれも誤りです。
特に口頭で「完遂」を使う機会が限られるため、聞き取りの際に混同が起こりやすい点に注意しましょう。
読みやすさのコツとして、二拍構成で区切ると滑らかに発音できます。
「かん・すい」と一拍ずつ区切るイメージで発声すれば、抑揚が自然になり相手にも伝わりやすくなります。
「完遂」を文章に書く際は常用漢字表に含まれるため、公文書・ビジネス文書・学術論文でも問題なく使用できます。
ただし小学生~中学生向けの教材では、難度を考慮してひらがな書き「かんすい」とルビが併記されることがあります。
「完遂」という言葉の使い方や例文を解説!
「完遂」は名詞として目的語に据えるか、「完遂する」というサ変動詞として用います。
誰が・何を・どのように完遂したのかを具体的に示すと、文章全体の説得力が格段に上がります。
【例文1】新製品開発プロジェクトを期限内に完遂するため、部門間で連携体制を強化した。
【例文2】彼は長年の研究課題を完遂し、ついに論文を発表した。
上記のように、目的語は「プロジェクト」「研究課題」「任務」「計画」など、ある程度の規模や期間を要するものが多いです。
小さなタスクにも使えますが、大げさに聞こえる場合があるため、コンテクストに合わせて「達成」や「完了」と言い換えることも検討しましょう。
「完遂」は主体の努力や粘り強さを強調するうえで効果的です。
一方で失敗の責任を明確にする場面では「完遂できなかった」「完遂を阻まれた」など、否定形や受動態で用いられることもあります。
なお敬語表現では「完遂いたしました」「完遂させていただきます」のように、謙譲語や丁寧語と組み合わせて用いると良いでしょう。
「完遂」という言葉の成り立ちや由来について解説
「完遂」は中国古典語に源流を持つとされ、漢籍においては「完」を完全・完備、「遂」を遂行・成就の意味で用いていました。
日本へは奈良~平安期に漢文の受容とともに伝わり、宮中行事や律令制度の文書で「事ヲ完遂ス」という表現が見られます。
二字熟語の構造上、前の字が状態を示し、後の字が行為を示すため「完全な形で遂げる」という一気通貫のニュアンスが生まれました。
同様の構造を持つ語に「完了」「完結」などがありますが、「遂」の字が入ることで「過程を含めた行為性」が強調されます。
「遂」は「とげる・とぐ」と訓読みでき、万葉集などで「遂ぐ」という表現が散見されます。
そこから転じて、鎌倉以降の武家文書や軍記物語では「大義ヲ完ク遂グ」という言い回しが武功や忠義を示す語として用いられました。
明治期には西洋由来の「ミッション」「プロジェクト」などの訳語として採用され、行政・軍事・実業界で標準語化。
現代では一般メディアにも浸透し、硬めの文章で目的達成を示す際の便利なキーワードとして確立しています。
「完遂」という言葉の歴史
古代中国で成立した「完遂」は、唐代の文献『新唐書』などに「事を完遂す」という形で確認できます。
日本最古級の記録は平安後期の史書『玉葉』で、「院の御企を完遂せしむること難し」と記されており、政治的計画達成を示す語でした。
鎌倉~室町期には武家の覚え書きに頻出し、特に合戦の決着や城郭建設の完了報告で用いられました。
江戸期になると幕府の公用文から庶民の読み物まで広がり、明治維新後の軍政改革で「任務完遂」がスローガン化したことで一般化が加速します。
昭和期には企業経営やスポーツ界へも波及し、1964年東京オリンピックの報道資料で「国民的プロジェクトを完遂した」と使われた記録があります。
平成以降はIT業界でも「システム移行を完遂」など、多分野で定着しました。
現在ではデジタルネイティブ世代にも浸透し、SNSでも「タスクを完遂した!」とカジュアルに投稿される一方、官公庁や学術界では依然として重厚な語感を保っています。
「完遂」の類語・同義語・言い換え表現
「完遂」に近い意味を持つ語には「達成」「成就」「完了」「遂行」「貫徹」などがあります。
それぞれ微妙なニュアンスの違いがあるため、場面に応じて選択すると表現の幅が広がります。
【例文1】長期目標を達成する。
【例文2】計画を貫徹する。
「達成」は結果に焦点があり、過程への言及は弱めです。
「成就」は願望が叶うニュアンスが強く、精神的・宗教的文脈でよく使われます。
「遂行」は任務を粛々とこなすイメージで、ビジネス文書で頻用される一方、「完遂」はより完璧さを強調する点が特徴です。
「貫徹」は信念や方針を途中で曲げない様子を示し、結果よりも姿勢を示すケースが多いです。
これらの語を使い分けることで、文章の硬軟や意図をコントロールできます。
「完遂」の対義語・反対語
「完遂」の反対は「未完」「中断」「挫折」「放棄」などが挙げられます。
中でも「未完」は単に終わっていない状態、「挫折」は困難に負けて継続できなかった状態を表します。
【例文1】彼らの計画は資金不足で未完に終わった。
【例文2】途中のトラブルで任務が挫折した。
「完遂」が100%達成を意味するのに対し、「中途半端」「半端」「断念」は0~50%程度の進捗で止まったニュアンスを含む点が対比として分かりやすいです。
特にビジネスの報告書では「未達」「未完了」など数値化しやすい語が好まれ、文学的表現では「志半ばで倒れる」など比喩が用いられる傾向があります。
「完遂」を日常生活で活用する方法
「完遂」はフォーマルな印象が強いものの、日常生活でも目的意識を高める言葉として活用できます。
例えば家事や学習計画を「完遂目標」と位置づけると、途中で妥協しにくくなりモチベーションの維持に役立ちます。
【例文1】今週中に部屋の片付けを完遂するぞ。
【例文2】毎日30分のジョギングを半年間完遂したい。
目標設定の際には「いつまでに」「何を」「どうなったら完遂か」を明確にし、進捗管理シートやアプリで可視化すると効果的です。
またチーム活動では「完遂報告会」を設け、成果と課題を共有すると次のプロジェクトにも活かせます。
言葉の持つ重みを意図的に利用し、「絶対にやり抜く」という覚悟を言語化することでセルフコントロール力が高まります。
「完遂」についてよくある誤解と正しい理解
誤解1は「完遂=大規模案件でしか使えない」というものです。
確かにビジネス文脈でよく見かけますが、日常タスクでも問題なく適用できます。
誤解2は「完遂=成功」というイメージですが、実際には「計画通りに終わった」だけであり、質的成功や目標数値の達成とは別概念です。
質が低くても計画通りなら完遂、質が高くても途中変更が多ければ完遂ではない、という切り分けがポイントです。
誤解3として「完遂」は自動詞だと思われがちですが、文法上はサ変動詞であり目的語を取る他動詞的用法が一般的です。
【例文1】タスクを完遂する。
【例文2】計画が完遂された。
正しく理解することで、文章の説得力が増し、誤用によるコミュニケーションロスを防げます。
「完遂」という言葉についてまとめ
- 「完遂」は計画や任務を最初から最後まで完全に成し遂げることを示す語。
- 読み方は「かんすい」で表記揺れは少ない。
- 古代中国由来で平安期から日本文書に登場し、近代に一般化した。
- 硬い印象を持つが日常タスクにも応用でき、目標管理に有効。
「完遂」は二文字ながら強い決意と成果を同時に感じさせる便利な言葉です。
歴史的背景を知り、類語・対義語と使い分けることで文章表現の幅が広がります。
また、目標設定やチームビルディングにおいても「完遂」というキーワードを掲げることで、メンバー間の意識統一が図れます。
硬い表現と敬遠せず、シーンに合わせて積極的に使いこなし、日々のタスクを気持ちよくやり抜きましょう。